企業の成長と競争力を維持するためにも、新規事業の立ち上げは企業において不可欠な取り組みです。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む現代においては、新規事業の成功はますます重要となっています。
これまで当社、スパイスファクトリーでは、経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、多くのお客さまの新規事業開発をデジタル活用の観点から支援してまいりました。
今回はその経験も踏まえながら、新規事業の定義からその重要性、そして具体的なプロセスについて、成功事例を交えながら詳しく解説していきます。
Contents
新規事業とは
まずは新規事業の定義や重要性など、基本的な要素についてご紹介します。
新規事業の定義
新規事業とは、既存の製品やサービスとは異なる、新しいビジネスモデルや市場を開拓する活動を指します。
企業の成長戦略の一環として行われるものであり、市場競争力の強化や事業リスクの分散、多角化戦略の実現、新たな顧客ニーズへの対応などを目的とします。
近年ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、デジタル技術やデータを活用して、これまでにない切り口で新規事業を展開することが重要になっています。
関連記事:DXを新規事業に取り入れるには?事例に学ぶコストを抑えて小さく始める方法
新規事業の重要性と必要な理由
新規事業が重要である理由はさまざまですが、ひとつは企業の成長と競争力の維持のためです。市場は常に変化しており、新しいニーズや技術が次々と登場します。
これに対応し続けるためには、既存のビジネスモデルに依存するだけでは不十分であり、新しい事業の創出が必要となります。
また、事業リスクの分散という観点からも新規事業の開発が求められます。既存の事業が市場の変化や競合の浸透によって衰退するリスクを軽減するためにも、事業を複数持つことは有効です。
一方で、日本企業においては新規事業の創出や市場形成が苦手という現状もあります。
経済産業省による「社会実装を支援するサポート産業の実態とその振興に関する調査」では、市場に投入された新規事業の占める売上高の割合は、全体のわずか6.6%にとどまっているという結果も紹介されています。これは、米国の11.9%と比較すると大きく差がある状況です。
同資料では、ルール形成を含めて市場創出を目指した企業は、CAGR(Compound Annual Growth Rate:年平均成長率)が約4%に達しているというデータも紹介されています。これは、日本企業の平均である0.8%と比較すると非常に大きな数字といえます。
このように、日本においては新規事業への取り組みを苦手とする企業が多く、他企業に先駆けて積極的に新規事業に取り組むことで、高い成長率の実現につながります。
。
新規事業を立ち上げるタイミング
新規事業を立ち上げるべきタイミングは「市場の環境」と「自社の環境」という2つの観点から見定めます。
市場環境の観点では、消費者のニーズやトレンドの変化を捉えることが重要です。新しいライフスタイルや嗜好が生まれている場合、それに応じた新規事業を展開することで競争優位を確立できます。
たとえば、以下のような例が考えられます。
- リモートワーク向けのコラボレーションツール
- ヘルスケアを意識したデバイスやアプリの提供
- AIを活用したタレントマネジメントや人材の採用
自社環境の観点では、既存のビジネスが成熟しているかどうかが一つのポイントです。市場が飽和状態にある場合、新たな成長の機会を見つけるために新規事業を展開することが効果的でしょう。
また、競合他社が新しい技術やサービスを導入している場合、それに対抗するためにも新規事業の立ち上げが必要となります。
新規事業を立ち上げるプロセス
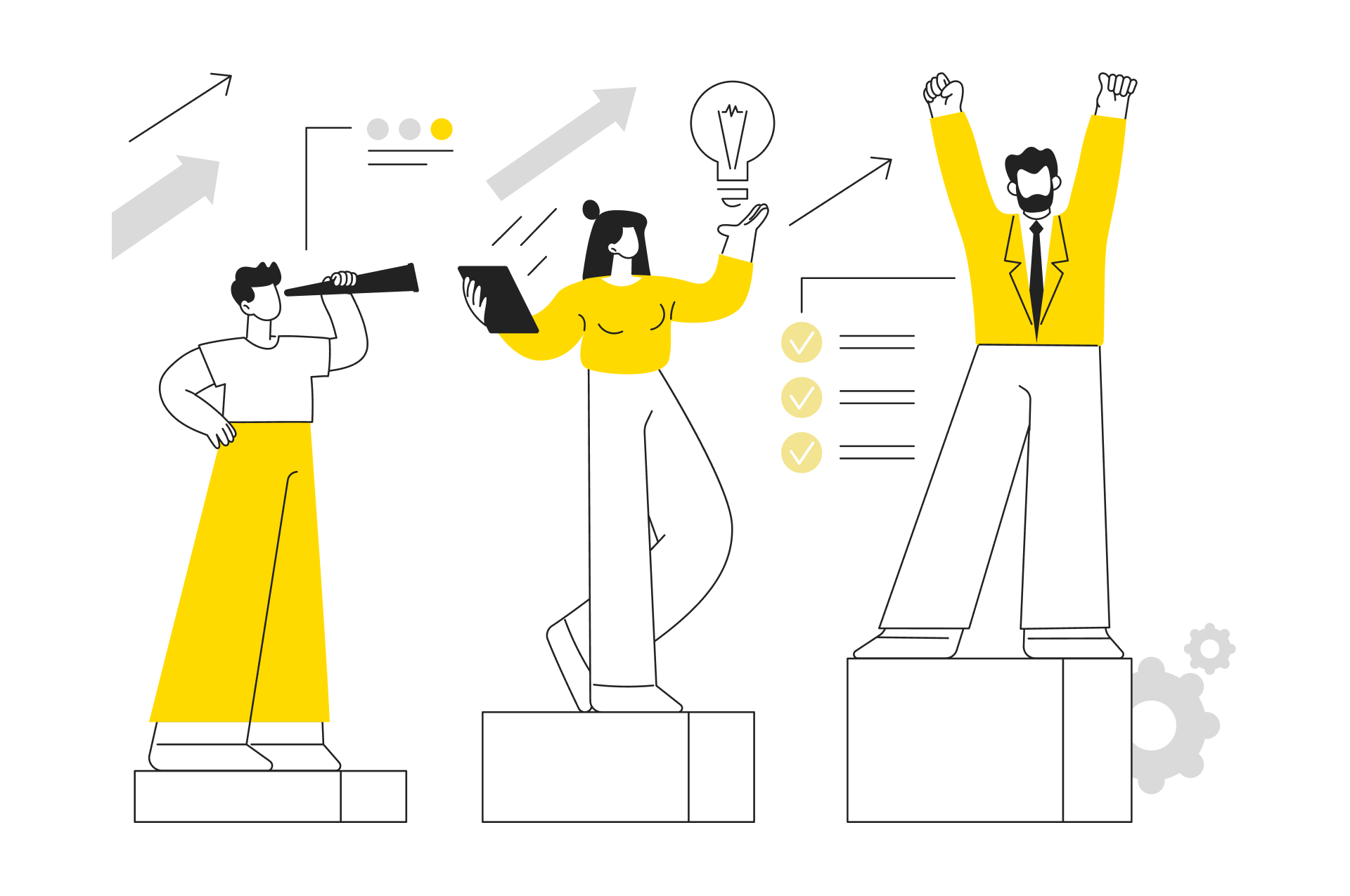
以下では、新規事業の一般的な立ち上げプロセスについてご紹介します。
1. 責任者のアサイン
新規事業の立ち上げには責任者が不可欠です。責任者は、事業の方向性を決定し、戦略を策定し、チームを指揮する役割を果たします。
新規事業の立ち上げは大きな負荷がかかるものであるため、責任者は専任で担当するべきでしょう。経営層や上司は、適切な人材を選定したうえで明確な責任と権限を与えることで、責任者が動きやすい環境を作ります。
責任者の選定は新規事業の成否を左右するため、リーダーシップや業界知識、戦略的思考を持つ人物を選ぶことが求められます。
2. アイデアの発想
まずは精度ではなく数を重視して、アイデア出しを行っていきます。ブレインストーミングや市場のトレンド分析を通じて、多様な視点から新規事業の種を見つけ出します。
発想したアイデアが優れているかを確認するためにおすすめなのが「他人に話してみる」という方法です。自分自身では優れたアイデアだと思っていたものも、他人に話してみると思ったよりも価値が伝わらなかったりもします。
3. 事業ドメインの決定
事業ドメインとは、企業が事業を展開する領域や範囲、競争領域を指す言葉です。
多数のアイデアの中から、実現可能性が高く、戦略的に重要なものをフォーカスする事業ドメインとして決定します。
事業ドメインを選ぶ際には、企業の強みやリソースを最大限に活用できる領域であることが求められます。
たとえば、すでに木材の加工技術や製造設備を保有している家具製造会社であれば、その技術を活用して新たに木製のPCやマウスを製造する事業に参画すると、シナジー効果を得ることができます。
事業ドメインの選択にあたっては、後述する「SWOT分析」や「PEST」分析などのフレームワークの活用も有効です。フレームワークを利用することで、自社が置かれている環境や参入すべき事業ドメインを把握しやすくなります。
4. 事業理念・コンセプト・ビジョンの明確化
選定されたアイデアを基に、事業の理念やコンセプト、ビジョンを整理します。新規事業開発においてよくあるのが、方向性のブレです。
メンバーが限られる初期フェーズにおいては方向性が明確であっても、プロジェクトが進んでいくうちにメンバーも増え、統制がとりにくくなっていきます。
このような事態を防ぐためにも、具体的な事業モデルや価値提供の方法を策定し、プロジェクトメンバーやステークホルダーと共有することが重要です。
5. 市場・競合・自社の調査
新規事業開発を進める上では、必ず市場・競合・自社に関して調査や整理を行い、現状を把握します。
市場調査
市場については、ニーズ調査として想定顧客層へのヒアリングやアンケートなどを行います。調査を通して、想定する製品やサービスは市場とマッチするのか、どのような点を重視すべきなのかを把握します。
自社にニーズ調査のノウハウがない場合、調査会社を活用するのもおすすめです。市場調査のノウハウやデータを持った調査会社を利用することで、効率的な市場調査が可能となります。
スパイスファクトリーで産学連携の一環として、東京大学未来ビジョン研究センター/グローバル・コモンズ・センター様のサステナビリティ消費行動に関する実証実験の例
参考:https://note.com/spice_factory/n/n810c565a2432
競合調査
競合調査として、対象となる市場にはどのような競合が存在し、各社がどの程度のシェアを持っているのかを整理します。
既存の製品やサービスが存在する場合、その改善点を洗い出し、新たな市場機会を探ることが一つのアプローチとなります。実際に製品やサービスを利用してみて、不便に感じる点や不満点などが見つかれば、新規参入にあたって絶好のブラッシュアップポイントとなるでしょう。
自社分析
最後に、自社の分析を行います。企業自身の強みや弱み、所有する設備や人材などのリソースを把握し、競争優位性を確保するための戦略を検討します。
なお、このように市場・競合・自社の3つの観点で分析を行うことを3C分析と呼びます。3C分析についての詳細は後述します。
6. 事業アイデアの数値的な分析・予測
収集したデータを基に、事業の具体的な分析と予測を行います。新規事業は当然ながら利益の確保を目的として行われるものですので、数字に基づく根拠ある分析が必要です。
新規事業の効果を測定するためによく用いられる指標は以下のとおりです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 売上高 | 事業からどの程度の売上を生み出すか |
| 投資対効果 | 投資額に対してどの程度の期間・割合で収益が回収できるか |
| 顧客獲得数 | 事業においてどの程度の顧客を獲得するか |
| 顧客満足度 | 顧客は製品・サービスに満足しているか |
| 顧客生涯価値 | 獲得した顧客はトータルでどの程度の利益を提供するか |
新規事業の立ち上げ段階では、各指標が各年でどのように推移していくのか、見込みを立てます。
各指標は相互に関係するものです。顧客数が増えれば売上高も増える傾向にありますし、投資対効果も出しやすくなります。
7. 新規事業立ち上げ環境の整備
新規事業を成功させるためには、さまざまなリソースを確保する必要があります。まずは予算の確保です。
新規事業の投資判断にOKを出してもらうためには、経営層の承認が必要となります。これまで整理してきた事業コンセプトや投資計画を基に、経営層への説明を行い、合意を得ます。
予算に基づき、必要なリソースの確保を進めます。必要なスキルを持った人材の確保、必要な設備や材料の調達、デジタルインフラの整備などを行います。
特に難しいのが、スキルを持った人材の確保です。デジタル技術を活用した事業を行う場合は、デジタルに精通した人材が不可欠となります。社内にエンジニアがいない場合、社外人材の確保も検討します。
8. 要件定義の実施
特にデジタル技術を利用した新規事業開発を行う場合には、必ず要件定義のプロセスを設けます。要件定義とは、開発するシステムに求める機能や性能を定義するプロセスであり、システム開発の最序盤に行う作業です。
要件定義を行わない、もしくは不十分なままプロジェクトを進めてしまうと、プロジェクトが迷走する原因となります。
要件定義を通して初めて、実際に構築するシステムの具体像が見えてきます。提供する機能やサービスの提供方法など、具体的なプロダクトが明確化され、関係者間での認識が統一されます。
また、要件定義を行うことで必要な費用やスケジュールも確定されます。
要件定義について詳しくは以下の記事でもご紹介しております。併せてご覧ください。
9. 施策の実行・効果検証
これらのプロセスを踏まえ、新規事業の実行に着手します。要件定義で定めたスケジュールや予算に従って、事業で活用するためのシステムを用意します。
また、事業内容にあたっては取引先や協業先、監督官庁などとの調整が必要となるケースもあります。
新規事業開発にあたっては、常にブラッシュアップを繰り返すことが重要です。事業を進める中で必要に応じて改善点を見つけ、迅速に対応することで、事業の成功率を高めます。
ブラッシュアップにおいては、実際に動作するプロトタイプを活用するとよいでしょう。プロトタイプを想定顧客に利用してもらうことで、より具体的なフィードバックを得やすくなります。
そのためにも、PoC(Proof of Concept:概念実証)のフェーズを設けてプロトタイプを構築し、想定顧客に利用してもらいます。
プロトタイプの開発においては、高速にプロトタイプを開発する「ラピッド・プロトタイピング」という手法も有効です。PoCやラピッド・プロトタイピングについては以下の記事もご覧ください。
関連記事:PoCとは。ビジネスにおけるPoC活用メリットや進め方を徹底解説
関連記事:ラピッド・プロトタイピングとは?導入目的・メリットとプロセスを分かりやすく解説
PoCを含め、事業を進める中では顧客やステークホルダーからのフィードバックを得るチャンスがあります。このフィードバックを基に、事業の持続的な成長を目指し、継続的な改善を行います。
新規事業の立ち上げに役立つフレームワーク

不確実性の高い新規事業開発においては、フレームワークの活用が有効です。フレームワークを活用することで、考慮漏れのリスクが減り、計画の精度を高めることができます。
ここでは、主要なフレームワークを4つご紹介します。さらに、詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてお読みください。
PEST分析
PEST分析は、企業が直面する外部環境を政治(Politics)、経済(Economics)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの視点から分析する手法です。
新規事業開発において行う外部要因分析において活用できるフレームワークとなります。
各要因の具体例は以下のとおりです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 政治的要因 | 政府の政策、規制、税制、貿易障壁 |
| 経済的要因 | 経済成長率、為替レート、インフレーション率、失業率 |
| 社会的要因 | 人口動態、文化、ライフスタイル、教育水準 |
| 技術的要因 | 新技術の開発、技術革新の速度、技術インフラの整備状況 |
PEST分析により、新規事業に影響する外部環境を抜け漏れなく、総合的に評価することができます。
SWOT分析
SWOT分析では、組織や事業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を総合的に評価します。新規事業における市場参入可否の分析において有効なフレームワークです。
| 要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 強み(Strengths) | 組織が優れている点や競争優位を持つ要素 | 技術力、ブランド力、リソースの豊富さ |
| 弱み(Weaknesses) | 組織が改善すべき点や競争上の劣位性 | 資金不足、技術の遅れ、マーケティング力の不足 |
| 機会(Opportunities) | 外部環境の変化や市場動向による成長の可能性 | 新市場の開拓、技術革新、規制緩和 |
| 脅威(Threats) | 外部環境の変化により直面するリスクや障害 | 競争の激化、経済不況、規制強化 |
SWOT分析を活用することで、自社の現状を正確に把握しやすくなります。
3C分析
3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場環境を分析する手法です。各要素について、以下のような観点で分析を行います。
| 領域 | 観点 |
|---|---|
| 顧客(Customer) | ターゲット市場のニーズや購買行動を明らかにする |
| 競合(Competitor) | 市場での競合他社の動向や強み・弱みを評価する |
| 自社(Company) | 企業自身の強みや弱み、リソースを把握し、競争優位性を築くための戦略を検討する |
顧客・競合・自社の3つの要素は、新規事業開発において必ず整理すべきものです。3C分析を活用することで、企業は市場の全体像や自社の参入可能性を理解し、効果的な戦略を策定することが可能となります。
ポジショニングマップ
ポジショニングマップは、企業や製品が市場内でどのような位置づけにあるのかを視覚的に示すためのツールです。
ポジショニングマップは二次元のグラフとして描かれることが多く、縦軸と横軸には競争要因や顧客にとって重要な属性が配置されます。
一例としては「価格と品質のポジショニングマップ」や「シェアと顧客満足度のポジショニングマップ」などが考えられます。
ポジショニングマップを作成することで、企業は市場内の競合他社との比較を視覚的に行うことができ、自社の強みや改善点を明確に理解できます。
また、新規事業を進める中で市場環境の変化に応じてポジショニングマップを見直すことも、持続的な競争力を維持するためには大切です。
新規事業を成功させるためのポイント
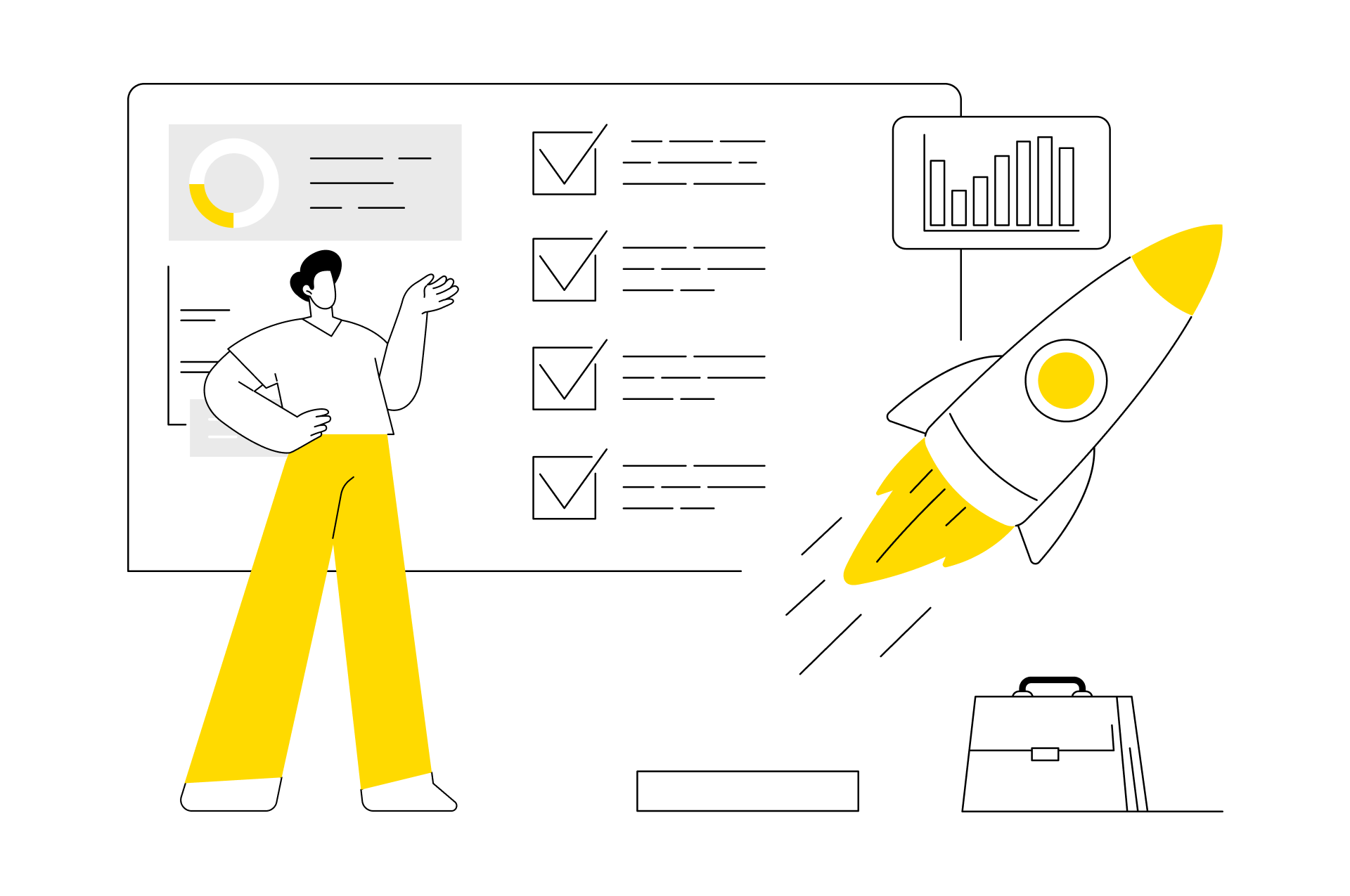
ここでは、新規事業を成功させるためのポイントについて、デジタル活用の観点も含めながらご紹介します。
要件定義を重視する
新規事業開発において、デジタル技術を活用する場合によくあるのが「アジャイル開発を採用するから要件定義は行わずにプロジェクトを進めよう」と考えてしまうケースです。しかしながら、アジャイル開発であっても要件定義プロセスは必要です。
実際に当社では、アジャイル型のシステム開発プロジェクトを実施する際にも、多くの場合でユーザー視点を取り入れた要件定義を実施しています。要件定義を実施することで、開発するシステムの全体像が見えやすくなり、効率的かつ手戻りの少ないシステム開発が実現できます。
また、新規事業開発においてはユーザー体験を重視し、顧客満足度を高めることも重要な観点です。そこで当社では、要件定義段階からUI/UXデザイナーが参画することを推奨しています。
これにより後工程での手戻りを減らしつつ、「ユーザーがより使いやすい」システムの開発につながりやすくなります。
フィージビリティスタディやPoCにより評価を行う
不確実性の高い新規事業の取り組みの成功確率を高めるためには、フィージビリティスタディによる調査・分析、PoC(概念実証)をうまく活用することをおすすめします。
よくあるのが「新規事業をスタートしたものの、技術的もしくは費用的な理由により実現ができなかった」というケースです。
フィージビリティスタディやPoCを通して、技術的な実現性や費用対効果などの確認を行うことで、このような失敗の影響を最小化し、事業の実現が困難な場合でも早期の撤退が可能となります。
ユーザーの声を聴く
開発するプロダクトが市場にフィットしなければ、事業目標の達成は困難です。本番開発前にプロトタイプを利用してユーザーの声を聞き、フィードバックを行うべきです。
ユーザーに利用してもらうための最小限の機能を備えたプロダクトをMVP(Minimum Viable Product)と呼びます。ユーザーからのフィードバックを早期に受けるために、まずMVP開発を行います。
PoCやMVP開発を実施する際には、アジャイル開発手法の採用が効果的です。アジャイル開発は柔軟かつ素早く必要な機能を構築することに優れます。
MVP開発やアジャイル開発について、詳しくは以下の記事でもご紹介しておりますので、併せてご覧ください。
※関連記事:MVP開発とは?アジャイル開発との違い、実施プロセスや注意点を解説
※関連記事:新規事業担当者必見。“アジャイル開発”で小さく始めるシステム開発
高速にPDCAを回す
新規事業開発は迅速性が重要です。市場環境が変化しやすい現代においては、検討に時間をかけすぎてしまうと、せっかくの参入機会を失ってしまうことにもなりかねません。
素早く市場に参入しながら、高速にPDCAサイクルを回し、継続的に改善を行うことが重要です。
新規事業においては、立ち上げ期から段階的に事業拡大のグロース期へと移り変わっていきます。高速でPDCAを回すことで、事業と投資の精度を高め、新規事業から事業拡大へと進んでいくことがポイントです。
スパイスファクトリーが支援した新規事業開発の事例
最後に、当社が実際に支援した新規開発事業の事例をご紹介します。
【事例1】本田技研工業株式会社様
当社では、世界的な自動車メーカーである本田技研工業株式会社様のPoCプロジェクトを支援しました。プロジェクトにおいてはプロトタイプ開発から検証、システム開発への移行まで一貫してサポートを実施いたしました。
本プロジェクトでは新規事業の市場ニーズを把握するため、プロトタイプ開発とリサーチを2ヶ月という短期間で実施。プロジェクトではターゲットから具体的なフィードバックを得るために、ユーザーの導線まで作りこんだ高解像度のプロトタイプを開発しました。
※参考:本田技研工業株式会社|PoC支援
【事例2】伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は、コンサルティングからシステム開発まで多岐にわたる事業を展開しています。当社では、同社のDX新規事業の支援を行いました。
プロジェクトでは当社メンバーが同社のチームの一員として参画しました。プロトタイプの開発においてはアジャイルネイティブである当社が全面的に担当。
チーム内の議論で見えてきた新規事業のコンセプトや最低限の機能要件といった事業の軸となる情報を基に、高速でプロトタイピングを行いました。
本プロジェクトにはマーケターとUI/UXデザイナーも参加し、プロトタイプのデザインだけでなく、リサーチやデザインシンキングのワークショップを提供しました。
※参考:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社|DX新規事業支援
【事例3】株式会社holografy様
IT コンサルティング事業などを展開されている株式会社holografy様は、新規事業としてライフスタイルブランド『inch blank_.』がリリースされました。
当社では、プロダクトアイデアを元にブランド立ち上げ〜デザインへの落とし込みまでを行いました。 コンセプト構築後は、ブランドの視覚化を実施。ブランドロゴやパッケージのデザインに至るまで、弊社で制作を行っております。
新規ライフスタイルブランドの立ち上げにあたっては「どこから着手したら良いのか」、「なにをしたら良いのか」などの不安はつきものです。そうした不安の解消のため、定期的なミーティングでお互いのTODO整理と進捗状況の更新を行い、非同期のコミュニケーションでは Slack を活用することで細かい疑問の解消や、課題の解決を行いました。
※参考:株式会社holografy | ライフスタイルブランドの新規立ち上げ
まとめ
今回は、新規事業開発について、当社スパイスファクトリーの知見も踏まえ、解説を行いました。
新規事業開発においてデジタルを活用するケースが増える中、「社内にデジタルに関するスキルセットを持った人材がいない」という声を聞く機会も増えています。
当社では、記事中で紹介した事例の他にも、これまで多くの企業の新規事業開発を支援して参りました。
アジャイル開発に精通したエンジニアやUI/UXデザイナーなど、高いスキルを持った豊富な人材がサポートを行います。
「新規事業開発においてPoCやMVP開発を行いたい」「アジャイル型でプロダクトを開発したい」といった方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
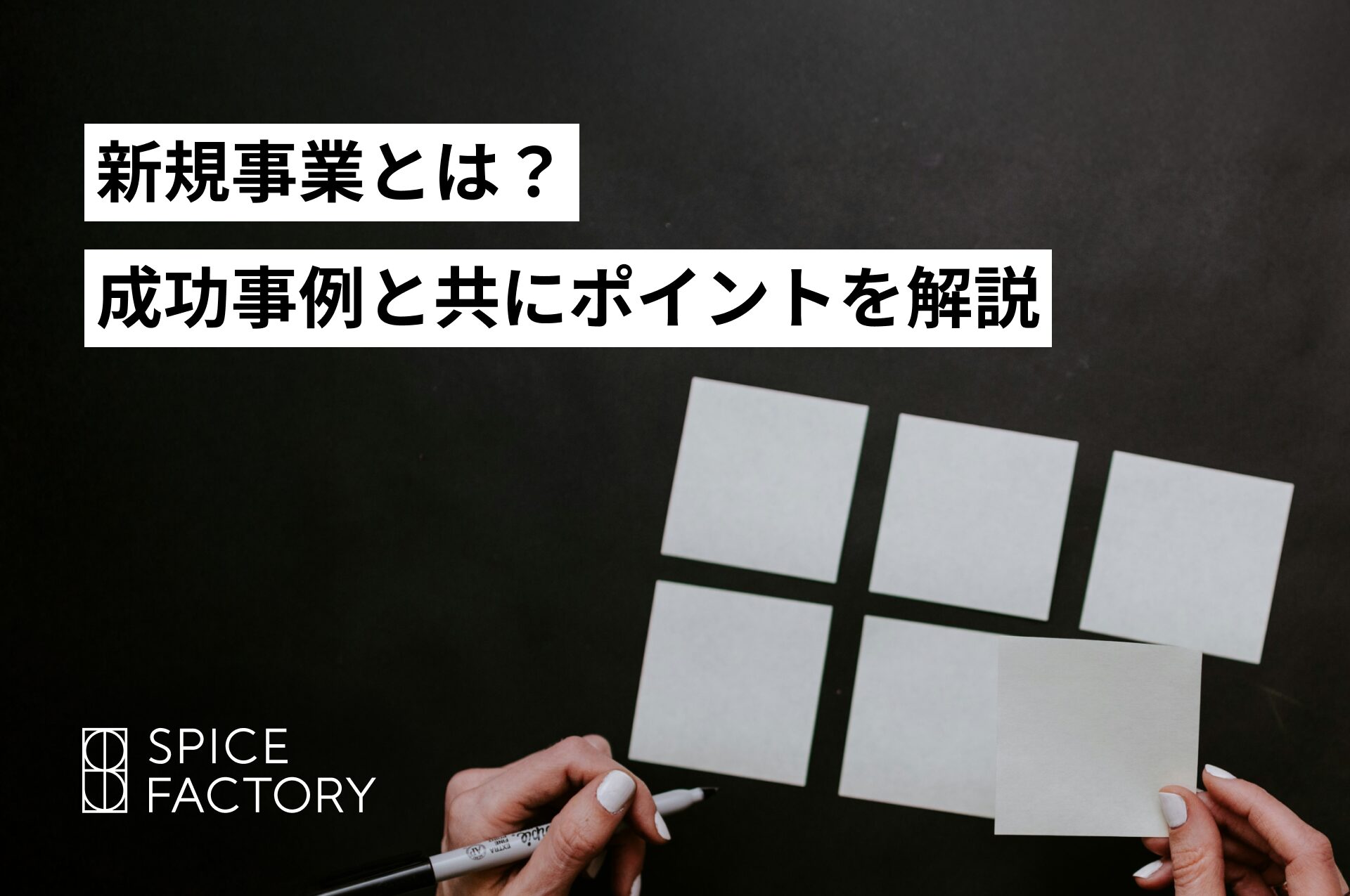
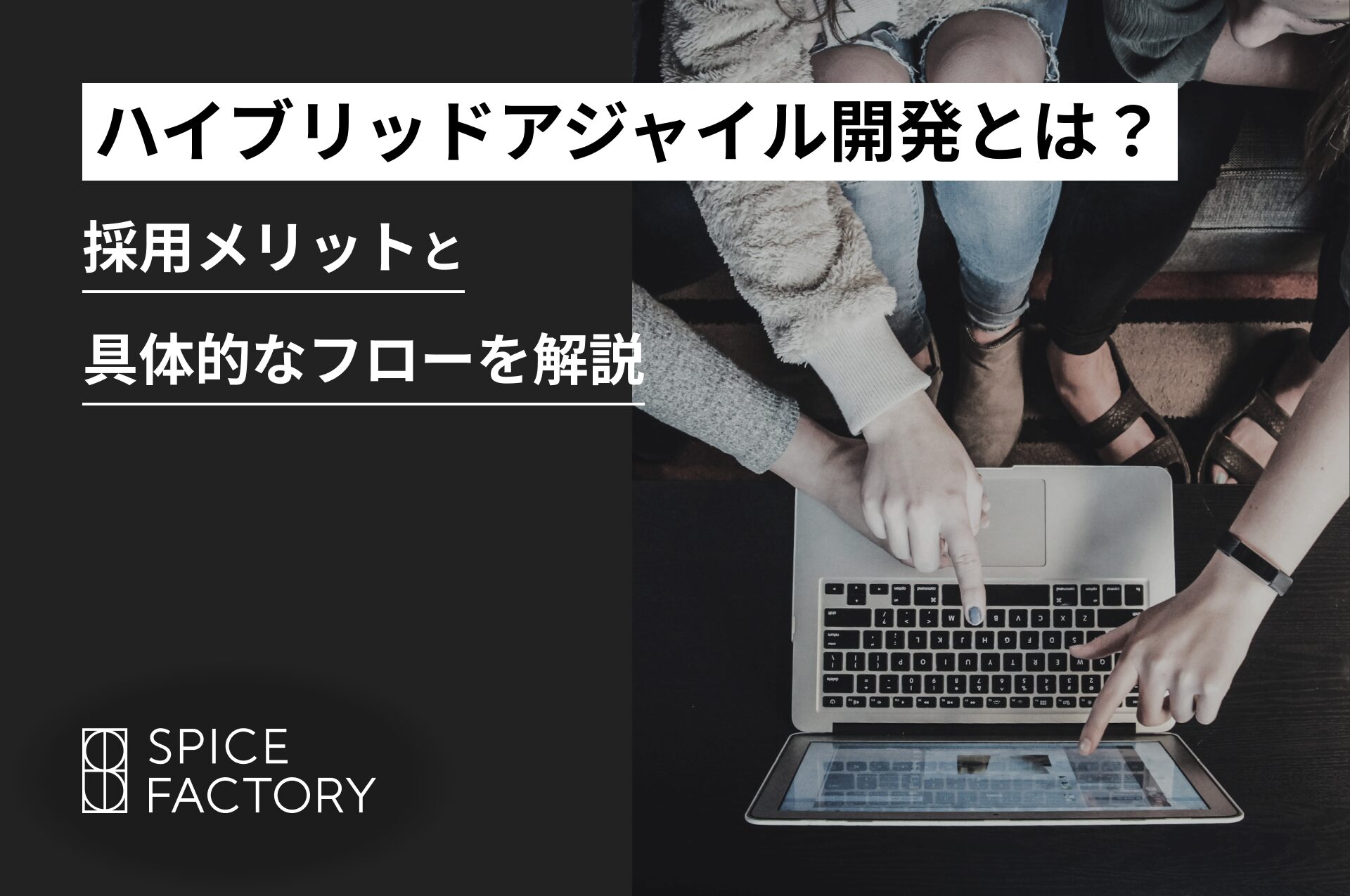
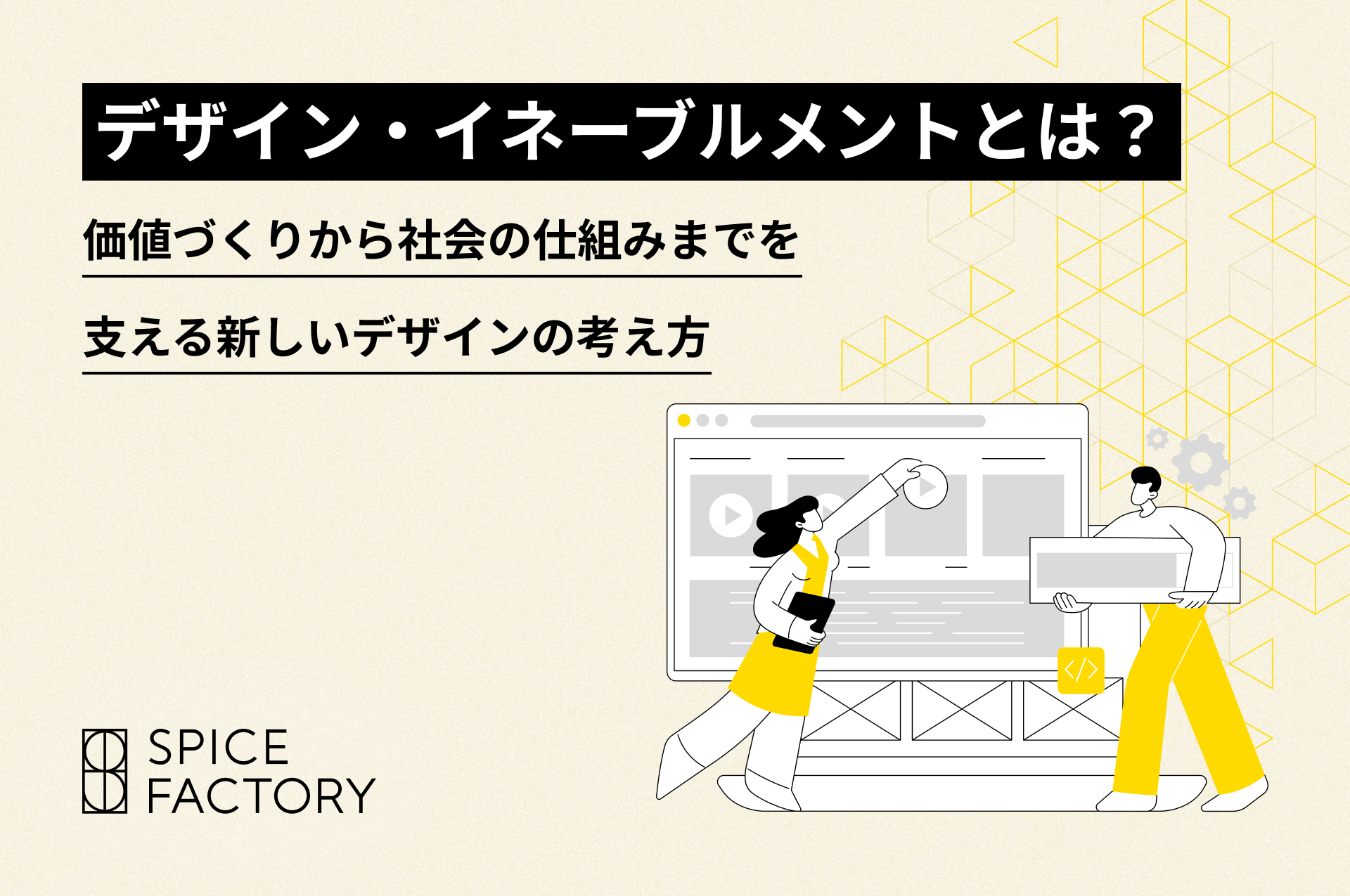

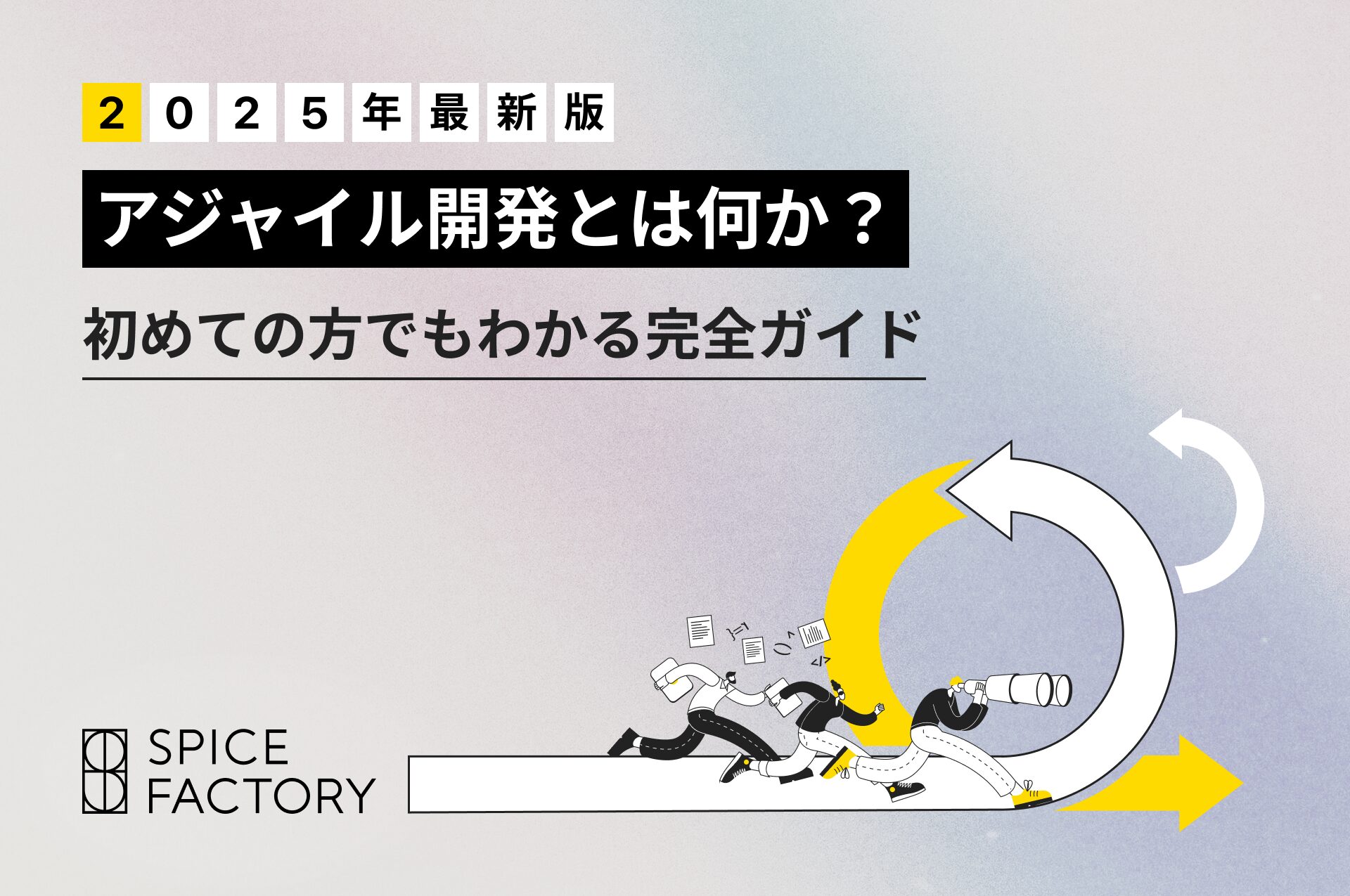


About The Author
スパイスファクトリー公式
スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。