物流DXとはデジタル技術を活用して物流業界のビジネスプロセスやサービスを革新する取り組みです。
近年、物流業界には人手不足や環境問題、小口配送の増加、システムの老朽化などさまざまな課題を抱えており、これらの問題を解決する手段としても注目されています。
しかし、物流DXの種類は幅広いため「何から始めたらいいか分からない」「取り組み方が分からない」と迷う企業は少なくありません。
本記事では、物流DXの市場動向や、物流業界の課題解決に役立つ導入事例を中心に解説します。
Contents
物流DXとは
物流DXとは、「物流」と「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を組み合わせた言葉です。
物流業務のプロセスやビジネスモデルを変革するためにデジタル技術やデータを活用することを指します。
単なるデジタル化に留まらず働き方改革や、ビジネスモデルの革新につなげる点が大きな特徴です。国土交通省も物流DXを積極的に推進しており、デジタル化実証やデジタル化の手引き、導入事例をまとめています。
荷物の受け取りや配送、納品などの一連の流れをデジタル化し、業務効率の向上、生産性アップ、コスト削減、課題解決、顧客満足度の向上を目指す取り組みです。
代表的な事例としてIoTセンサーを活用した在庫管理、AIによる配送ルートの最適化、ロボットによる倉庫内作業の自動化などが挙げられます。
昨今の物流業界を取り巻く環境
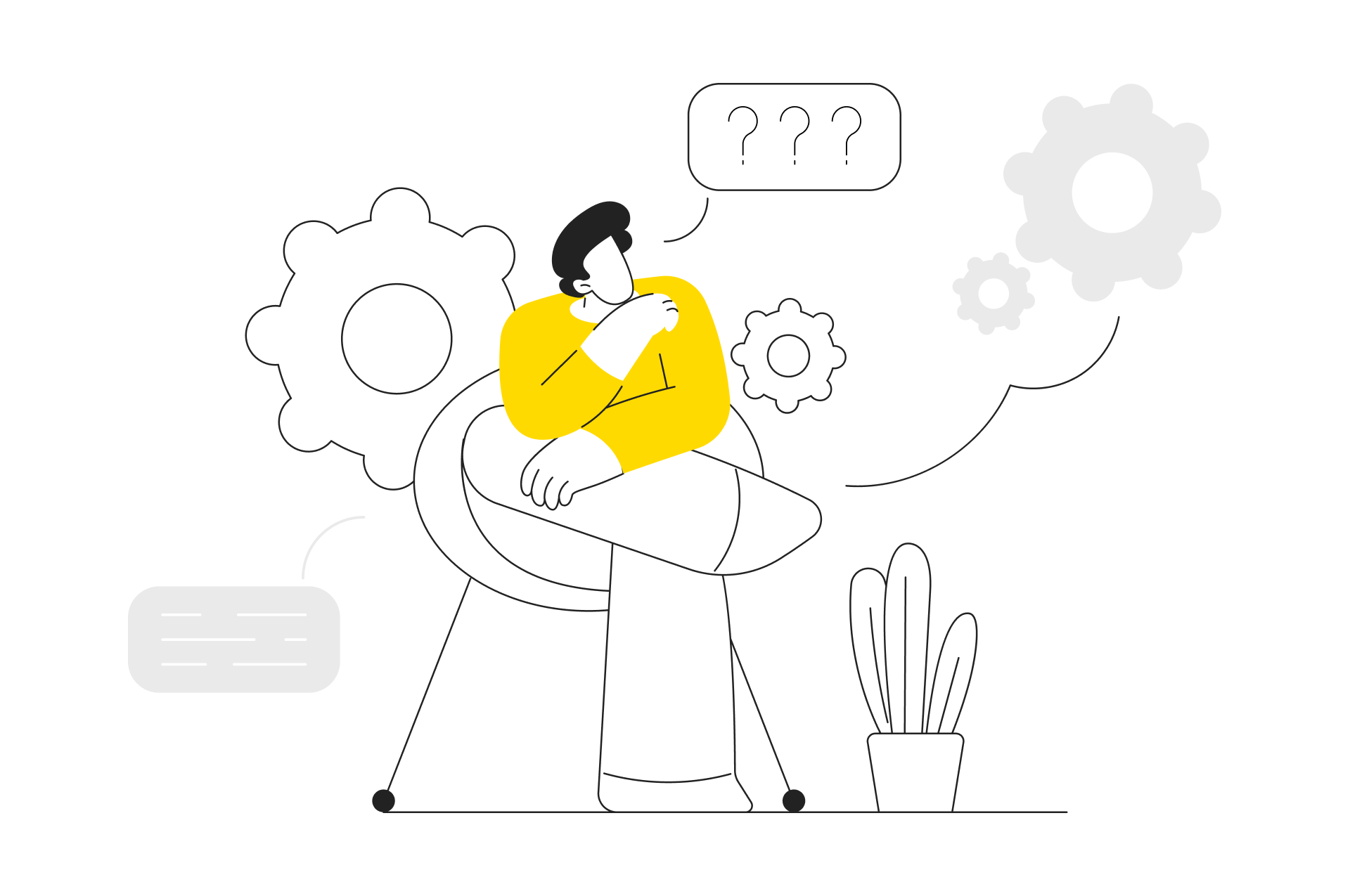
物流業界を取り巻く昨今の状況を詳しくみていきましょう。
EC市場の拡大成長での小口配送の増加
近年、EC市場の急成長によって配送件数が急増しています。なかでも特に課題とされているのが小口配送の増加です。
企業から企業へ発送する従来の大口配送に比べ、個人宅へ届ける小口配送は積載効率が悪く配送回数や手間が増え業務負担が大きくなります。個人宅は不在であるケースも多く、再配達の増加も深刻な課題です。
物流DXの導入で配送状況のリアルタイム管理や受取人の状況に合わせた配送が可能になれば、再配達の削減につながります。さらに、街中への宅配ボックスの設置やAIによるルート最適化を組み合わせることで、配送効率の向上と業務負担の軽減が見込めるのです。
労働環境の悪化と人手不足
物流業界では長時間労働や過重労働などによる労働環境の悪化が深刻な課題となっています。特にドライバーは高齢化が進み若年層の人材確保が困難な状況です。
加えて2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、1人のドライバーが運べる荷物量が減少しています。
物流DXは労働環境の改善や人手不足の改善にも有効です。たとえば、配送ルートの最適化による走行距離の削減や業務スケジュールの自動化による作業時間の平準化が図れます。また、倉庫内作業にスマートデバイスを活用すると負担軽減や作業効率の向上につながります。
参照:「国土交通省説明資料 働き方改革PR動画完成発表会『はたらきかたススメ!~みんなで進もう 働きやすい未来へ~』」
システムの老朽化とIT技術への対応の遅れ
物流業界では基幹システムの老朽化も課題です。レガシーシステムの残る企業では業務の一部にデジタル化を取り入れたものの情報の一元管理が難しく、紙ベースの管理や手作業の業務フローの残るケースも見られます。
IT人材や資金の不足によりIT技術への対応が追いついていない企業も少なくありません。このようなケースでは物流DXによるクラウドシステムの導入も効果的です。業務フローの効率化や作業負担の軽減につながり業務全体の最適化が期待できます。
環境問題
物流業界では「環境負荷の高さ」が長年の課題とされています。特にトラック輸送を中心とした現在の物流システムではCO2排出量が多い状況です。
2050年のカーボンニュートラルを実現するには物流業界全体での取り組みが欠かせません。
無駄な配送や再配達が重なると環境負荷が増大します。物流DXの導入で共同配送やルートの最適化、配送時間の事前指定などが進み、走行距離の削減や積載効率の向上につながります。結果的にCO2排出量の軽減が期待できるのです。
物流業界における2030年問題
日本では少子高齢化が進み2030年ごろには65歳以上の高齢者が全人口の3割以上になると予想されています。「2030年問題」とはこの影響を受けて労働力人口の減少や社会保障費の増大などをはじめとしたさまざまな課題が社会全体で顕在化することを指します。
物流業界においても2030年にはドライバー数が現在の65%程度にまで減少すると推計されています。その結果、およそ35%の荷物が運べなくなるという深刻なシナリオが示されているほどです。
物流の3割以上が滞る事態は社会全体に大きな影響を及ぼすでしょう。危機を回避し持続的な物流体制を構築するためには、業務の効率化や自動化を進める物流DXの導入が不可欠です。
物流DXに向けた3段階のプロセス
物流DXに向けて3段階のプロセスがあります。自社の現状を把握するためにもそれぞれのプロセスを確認しておきましょう。
デジタイゼーション
デジタイゼーション(Digitization)とはアナログ情報をデジタルに変換するプロセスです。たとえばこれまで紙の注文票やFAXで注文を受けていたものをメールでの受信に切り替えることもデジタイゼーションの1つです。
紙ベースでやり取りしていた情報をデジタル化すると紙の保管や管理が不要になり、データ共有や検索がスムーズになります。さらにデータとして履歴が残るため情報の行き違いを防止できる点もメリットです。
デジタライゼーション
デジタライゼーション(Digitalization)とはデジタル化した情報を活用し業務を効率化するプロセスです。たとえば注文情報をデータ化するだけでなく、バーコードをつけて倉庫管理システムと連携させて在庫の把握や出荷指示に活用することもデジタライゼーションです。専用のPOSシステムを使用するケースもあります。
従来、業務ごとに分けていた情報に共通コードをつけてシステム全体で連携すると作業負担やミスの軽減につながります。
デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)とはデジタル技術を使いビジネス全体を変革するプロセスです。データ化によるただの業務の効率化や改善にとどまらず、デジタルを利用してビジネスモデルの変革を目指します。
デジタライゼーションでは、POSの導入やバーコード管理などで業務効率化を実現しました。デジタルトランスフォーメーションではデジタルデータやITシステムを活用し、無駄のない物流網の構築などビジネスモデルの変革につなげます。
物流のDX化が課題解決のキーポイントになる
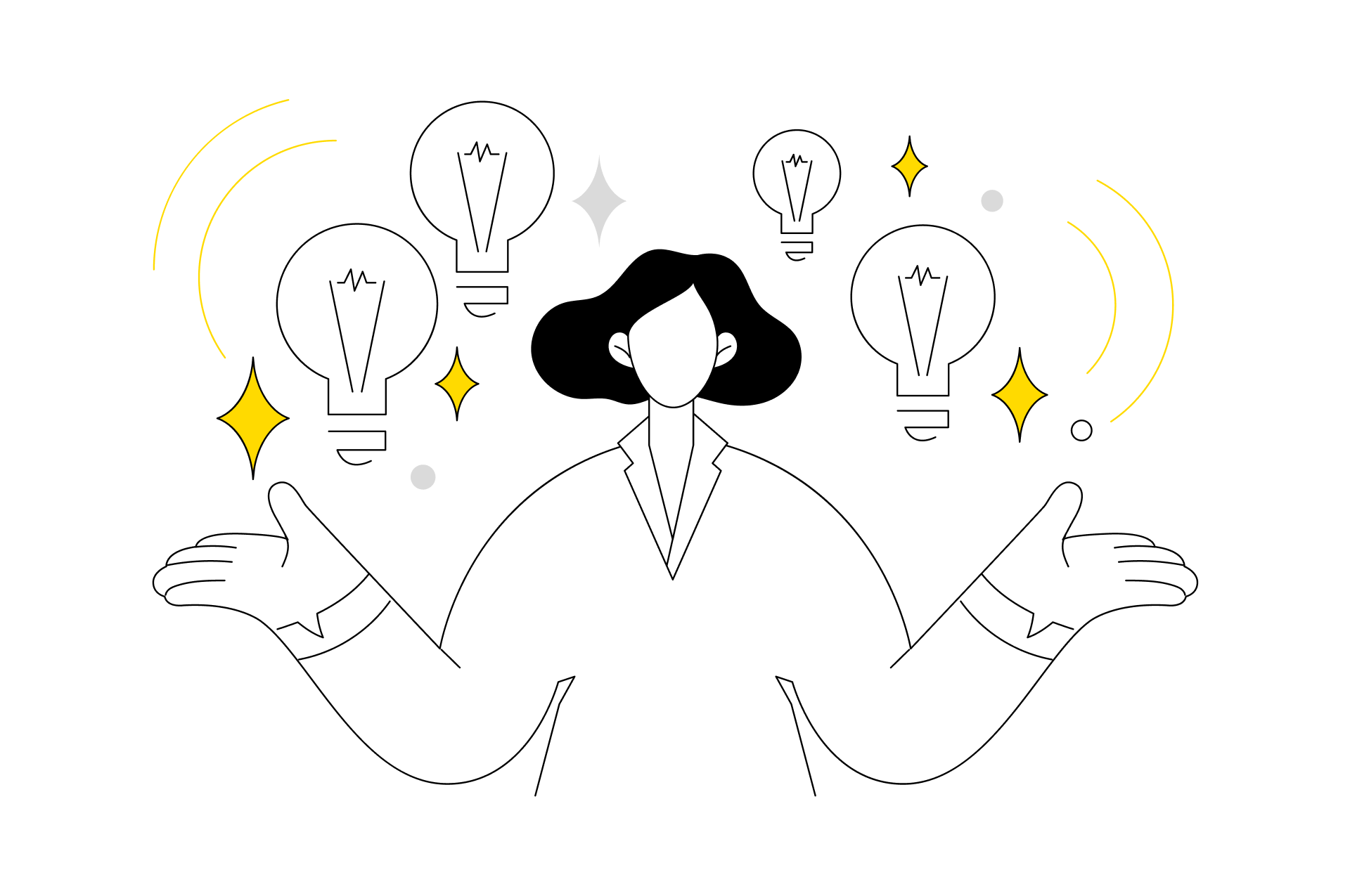
物流業界が抱えるさまざまな課題を解決するには物流のDX化が不可欠です。ここでは具体的な解決策例を紹介します。
業務フローの見直しでコスト削減
紙ベースの業務をデジタル化すると処理時間の短縮につながります。入力作業や集計の自動化による人件費削減も見込めるでしょう。
さらに紙や印刷にかかるコスト削減も期待できます。書類のデータ化やクラウドの活用で保管庫の管理コストの削減にもつながります。
情報をデータ化することで紙ベースの時と比べ情報を探し出す手間や時間が大幅に短縮できるのもメリットです。
倉庫内管理の自動化
倉庫内をデジタル化し、ロボットや自動搬送装置を導入すると作業時間の短縮や業務負担の軽減が見込めます。人手による作業負担を減らすため、労働環境の改善も期待できるでしょう。
デジタル化を進めると作業の標準化にもつながり、熟練者だけでなくとも精度とスピードの向上が期待できます。
在庫管理の効率化
バーコードやセンサーを活用すると在庫数や保管場所を正確に把握できるため、在庫管理の効率化につながります。
リアルタイムで在庫情報を更新すれば在庫データをもとに発注や補充のタイミングの最適化が可能です。過剰在庫や在庫不足を軽減できるのもメリットです。
配送ルートの可視化で最適化
デジタル化で配送ルートを可視化すると渋滞情報や配送状況をリアルタイムで把握できるのがメリットです。
状況に応じて最適な経路を選択できるので、配送の効率化で燃料コストや配送時間の削減が期待できます。配送ルートの可視化によってさらに効率的に配送することが可能になるでしょう。
ドローン配送
ドローン配送は遠隔地や過疎地、災害時の配送手段として注目されています。配送時間の短縮や交通渋滞の緩和、人手不足の解消につながる配送手段として期待されているのです。
さまざまな企業が実証実験に取り組み成果報告を出しており、一部では実用化も進んでいます。
日本では運行管理システムの整備が不十分であり、今後の進展が期待されている技術です。
配送の自動化
配送の自動化として自動運転車両や無人配送ロボット自動運航船などで実証実験が進んでいます。たとえば高速道路における自動運転トラックやオフィス街での小型配送ロボットなどです。
また、自動運航船は長距離輸送の効率化が期待されています。
このように、幅広い分野で配送の自動化が進めば人手不足の解消につながり、また、アナログな業務で起きがちだった書き間違いや伝達ミスなどのヒューマンエラーの防止が見込まれる場合もあります。
物流DX推進におけるポイント
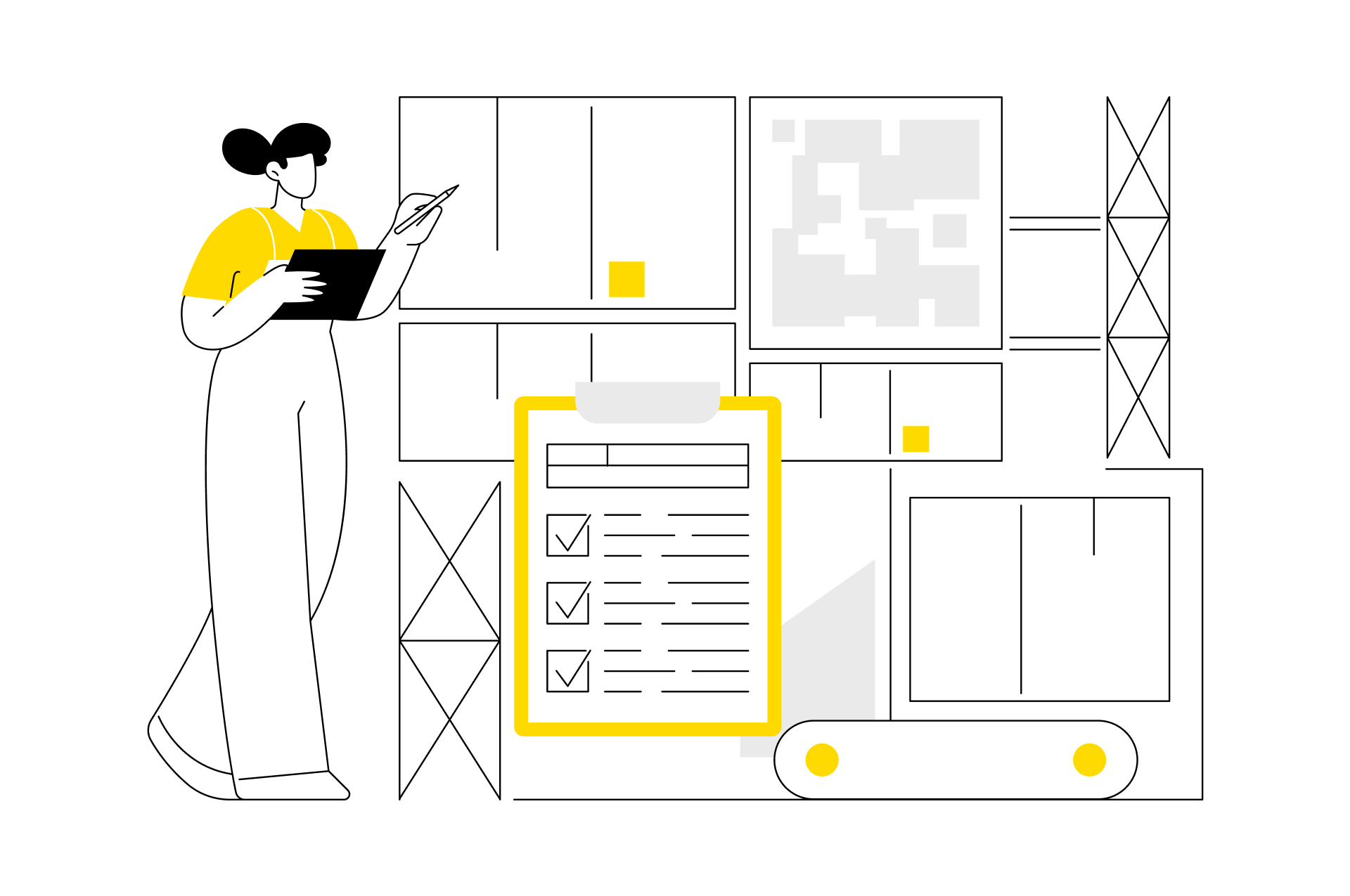
物流DX推進において気を付けるべきポイントを3つ紹介します。
UI/UXの最適化
多忙な物流現場では直感的に使えるシステムの導入が不可欠です。担当者が変わる都度、システムの使い方を説明しなければ使えないのでは非効率的です。
また、複雑なUI/UXは入力ミスなどトラブルの元にもつながります。現場に最適化したUI/UXを導入すると業務の効率化が期待できます。
ノーコードで使用できる
物流現場では顧客要望に対応するために作業内容の変更や追加が起こることも珍しくありません。そのたびにエンジニアに依頼してシステムを変更すると手間や時間がかかります。
ノーコードで運用できるシステムであれば、現場の担当者が自ら調整できるため、改善事項をすぐに反映できるのが利点です。トラブル時の迅速な対応や業務改善のスピード向上、運用コストの削減が見込めるでしょう。
スマートフォン対応であること
物流現場は歩き回ることが多く両手が塞がる場面も少なくありません。パソコンやタブレットを扱うのが困難な環境も多く手軽に使える端末が求められます。
時間や場所を問わず気軽にシステムを利用するには、ポケットやカバンに入れて簡単に持ち運べるスマートフォンが最適です。スマートフォン対応のシステムなら現場での進捗確認や作業報告もリアルタイムでスムーズに行えるので情報共有や業務のスピードアップが見込めます。
スパイスファクトリーが実現できること
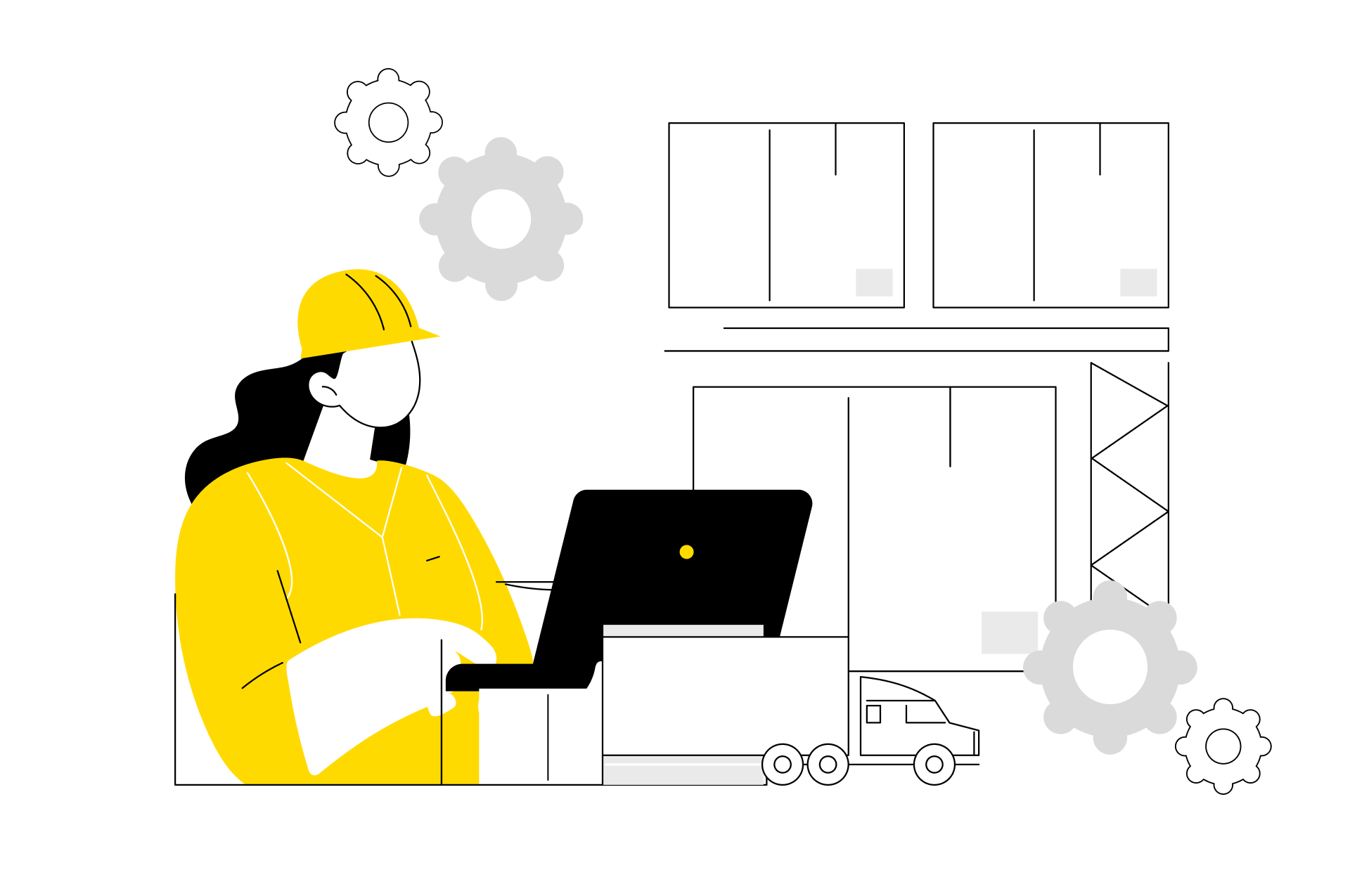
物流DXは幅広く、どこから手を付ければいいか迷う企業も少なくありません。ここでは物流DXの実現のためにスパイスファクトリーが実現できる2つの強みを紹介します。
UI/UX
高性能なシステムを導入しても複雑な操作では現場の担当者が負担を感じるでしょう。場合によっては入力ミスなどにつながることもあります。多忙な現場でいち早くシステムを根付かせるには、直感的で使いやすいUI/UXデザインが欠かせません。
スパイスファクトリーでは現場で使う人の視点に立ったUI/UXデザインを重視しています。誰でも使いやすいシステムを構築し業務効率化を支援します。
アジャイル開発
スパイスファクトリーは小さな単位で開発と改善を繰り返すアジャイル開発を得意としています。さらにPoCと呼ばれる試作開発前の検証プロセスにも重点を置いているのが特徴です。
一気にすべてを作り上げるのではなく現場でのフィードバックを受けながら改善を重ね最適なシステムを構築します。完成後に担当者が「使いにくい」と感じることのないよう現場で本当に使えるシステムを提供できるのが強みです。
スパイスファクトリーが上流工程から入り、質の高い要件定義・UI / UX設計を行い、かつアジャイル開発を用いてスピーディにアウトプットを生み出すことで、現場との目線を合わせつつ、本質的な課題解決に繋がるシステムリプレースを実現します。
ラピッドプロトタイピング
ラピッドプロトタイピングとは完成品を作る前に試作品をスピーディにつくる手法です。試作品を現場で活用してもらいフィードバックを受けるため、イメージのずれや使いにくさを防止できるのが利点です。
スパイスファクトリーでは、ラピッドプロトタイピングを案件によって導入しています。後戻りのコストを抑え効率的にシステムを開発できるため開発の効率化とスムーズな現場での活用を後押しします。
物流DX特化型チームを構築
物流業界が抱える2030年問題に本格的に向き合うため、スパイスファクトリーでは「物流DX支援特化型チーム」を立ち上げました。当チームには、物流業界の課題に精通した株式会社データ・シェフ様が物流DX専門コンサルタントとして参画しています。
業務フローの可視化や現場に即した改善提案を通じて、DXの定着と生産性向上を支援する取り組みです。誰もが直感的に使えるUI/UXや人的リソースを最大限に活用できるシステム設計により、物流業界の効率化と持続的な業務改善を実現します。
物流DXの事例紹介
実際の現場ではどのように物流DXが進められているのでしょうか。ここでは企業が実際に取り入れた具体的な事例を紹介します。ぜひ参考にしてください。
佐川ヒューモニー株式会社|「VERY CARD」創業以来のシステム基盤大刷新
電報サービスを提供する佐川ヒューモニー株式会社様では、ECサイトの使いやすさを向上させて顧客からの注文データをスムーズに取得できる仕組みを構築しました。
初めてサイトに訪れたユーザーでも直感的に操作できるUI/UXを採用し、顧客満足度の向上を実現しています。さらに、運用管理者にも使いやすく将来の拡張にも柔軟に対応できるシステムです。
未来を見据えた物流DXとして、ECサイトから物流現場までの情報連携を強化した好事例です。
Johnstone Supply|クラウド型在庫管理システム「Infor WMS」
アメリカの空調機器卸売業者Johnstone Supplyでは業務が拡大するなかで、在庫管理データの整合性が取れなくなるという課題を抱えていました。この課題を解決するために、クラウド型在庫管理システム「Infor WMS」を導入しています。
入荷・出荷・業務進捗の一元管理により入力作業の効率化につながりました。操作性の高い画面で新入社員でも10日程度で使いこなせるのが魅力です。スタッフの生産性が大幅に向上しただけでなく、在庫精度が99.9%と大幅に改善して大きな成果を上げています。
関連記事:【国土交通省】物流・配送会社のための 物流DX導入事例集 事例3|Johnstone Supply
湯浅運輸|輸送業務支援ソリューション「SSCV-Smart」
湯浅運輸ではトラックが増えアナログでの管理に限界を感じていました。そのため、輸送業務支援ソリューション「SSCV-Smart」を導入し、運行指示書のペーパーレス化と業務の効率化を実現しています。
受発注、運行指示、配車管理に加えて労務管理や調達管理などを網羅しており、これまで属人化していた事務作業の標準化と自動化が可能になりました。さらに、荷主と輸送業者をインターネットでつなぎ、案件獲得から輸送、請求書の発行まで管理できます。トラックの稼働状況も可視化され、ドライバーと事務員の負担軽減につながりました。
関連記事:【国土交通省】物流・配送会社のための 物流DX導入事例集 事例16|湯浅運輸
オープンロジ|共通物流プラットフォームで倉庫・配送をDX
従来、物流業務は倉庫や配送ごとにシステムが分断され、アナログ管理や属人的なオペレーションが常態化していました。オープンロジはこれを解決するため、誰でも簡単に使える共通物流プラットフォームを構築し、物流業界全体のDXを推進しています。
このプラットフォームでは、API連携による受注・在庫・配送情報の一元管理が可能で、倉庫や配送事業者との連携も標準化されたUI上で完結。複雑な物流業務を簡素化し、可視化と自動化を実現しました。さらに、在庫や輸送手段を柔軟に組み合わせることで、最適な物流ネットワーク構築と業務効率化を支援しています。属人化の排除、業務負担の軽減にも寄与しています。
関連記事:オープンロジ、35.5億円のシリーズD資金調達を実施~テクノロジーとデータを活用した物流プラットフォームの構築を加速~
物流DXはビジネスモデルの変革が最重要課題
物流業界では環境問題や労働力不足、システムの老朽化など多くの問題を抱えています。デジタル化にとどまらずビジネスモデルの変革に直結する物流DXはこれらの問題を解決する手段として注目されています。
さらに、ロジスティクスの進化を通じて「モノを運ぶ」以上の新たな価値を提供できるのも大きな強みです。
2030年に向けて物流を取り巻く環境はさらに深刻化していくと予想されています。いち早く物流DXに取り組むことが企業にとって急務と言えるでしょう。
私たちスパイスファクトリーは、物流業界のDXを支援するための具体的な解決策をご提案しています。無料で資料をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
当社は【2025年最新版】DX支援おすすめ企業4選に掲載されています。
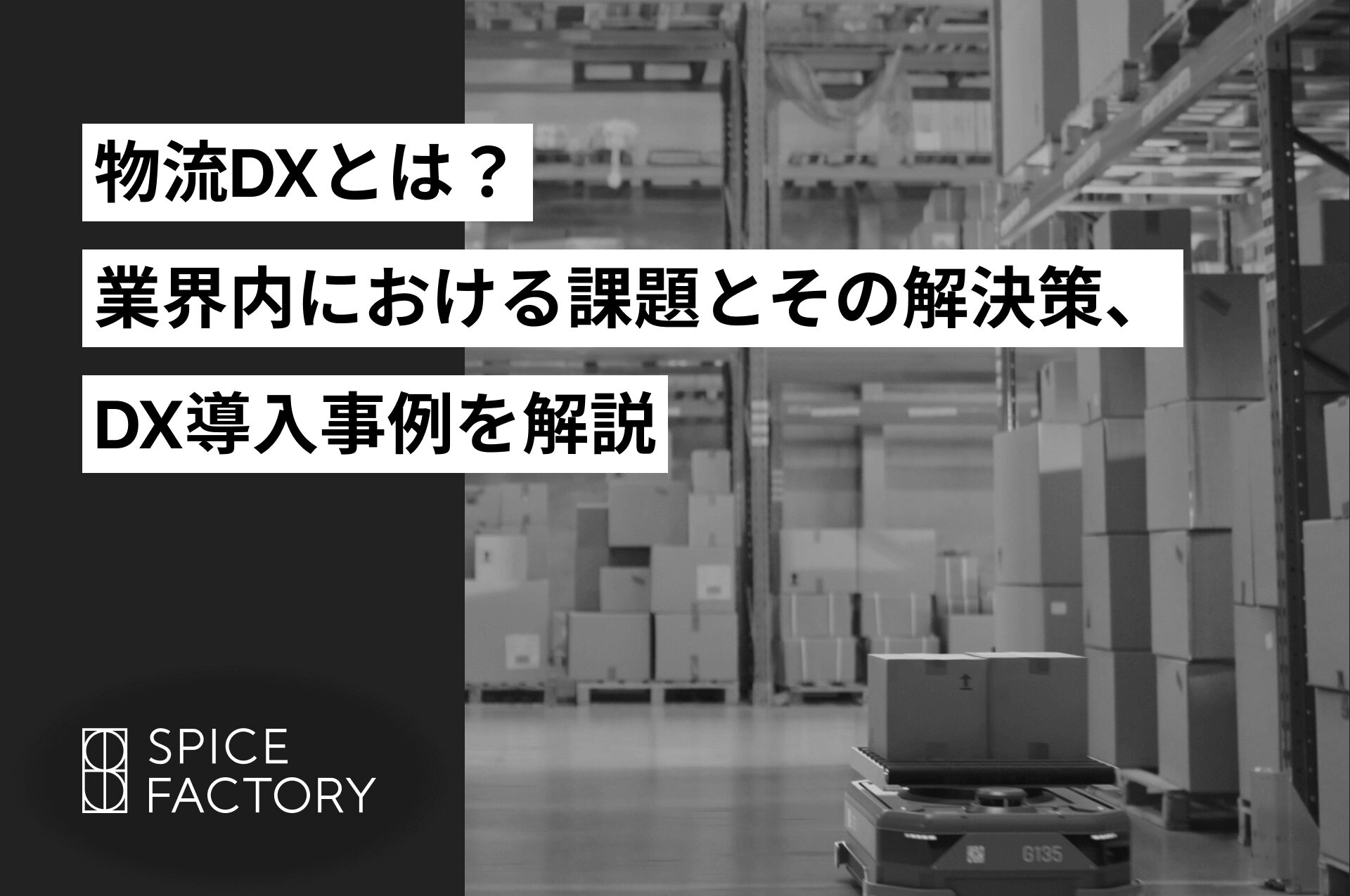
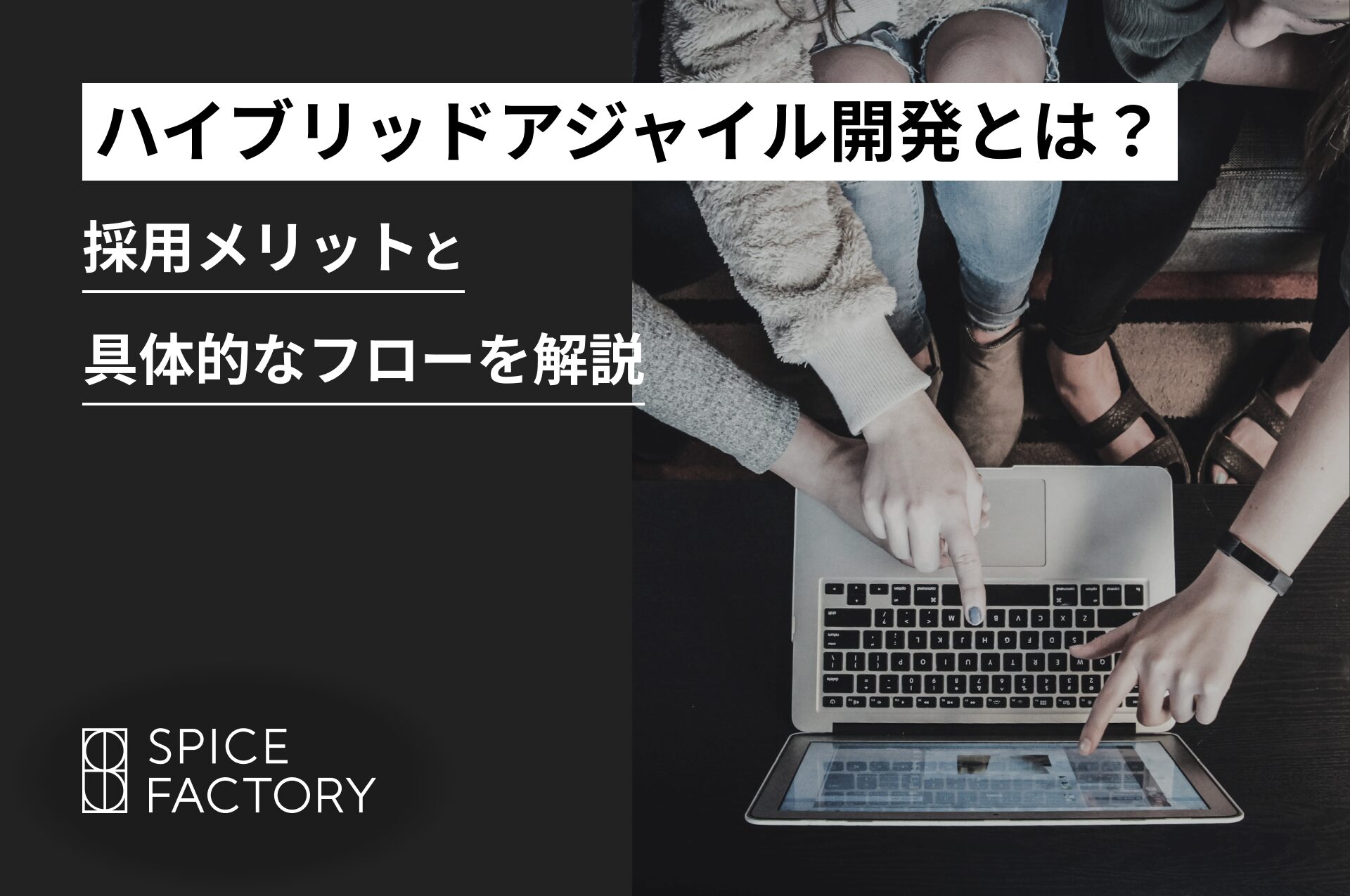
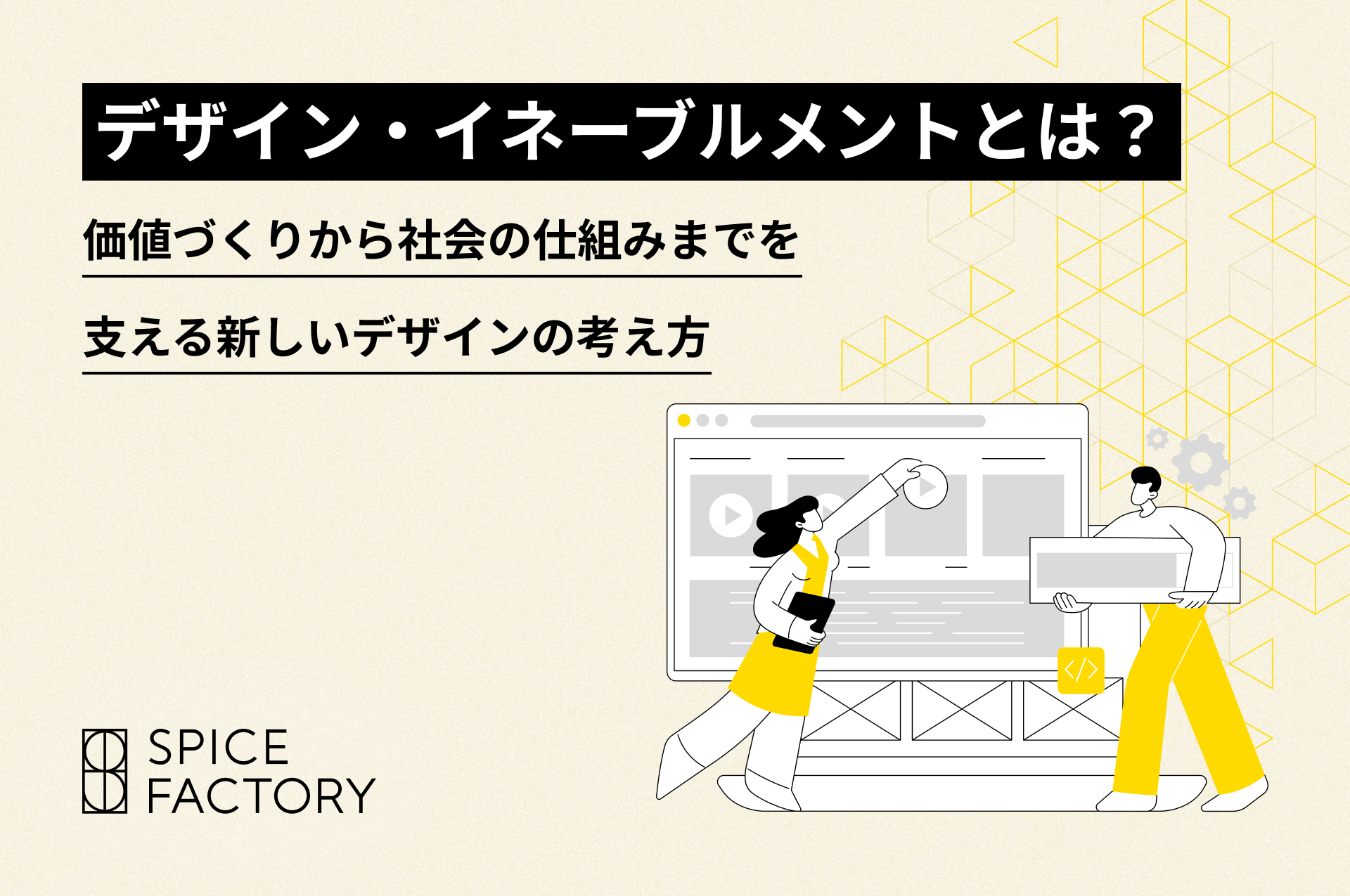

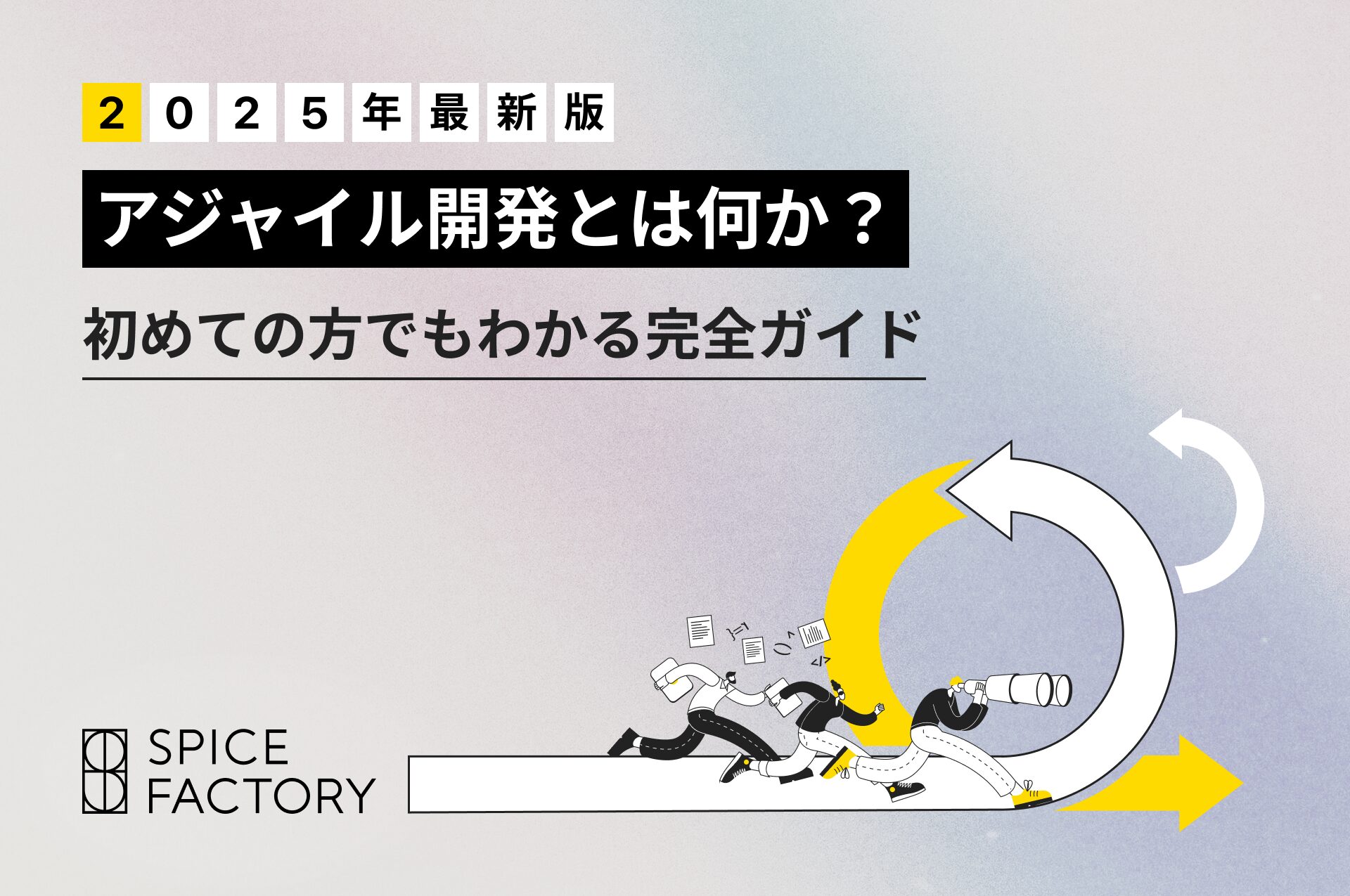


About The Author
スパイスファクトリー公式
【監修】株式会社データ・シェフ|代表取締役 濵田 雅人(はまだ まさと) 業務改善コンサルティング会社の代表取締役として、業務フローの改善やデータ活用支援を提供。これまでに物流運営会社やシステム開発会社での物流関連システムの企画・設計・導入を担当し、効率化の推進に寄与。特に物流業界における業務改善やDX支援に注力し、豊富な現場経験に基づいた実践的なアドバイスが強み。物流センターの運営や経営に関するノウハウを持ち、理論だけでなく、システム開発等の知見を掛け合わせた具体的な現場改善策を提案できる点で高く評価されている。