新規事業開発やレガシーシステムの刷新、 新規ITシステムの導入などにおいては一般的に多額の投資が必要となります。
事前にその実現可能性や妥当性についてフィジビリティスタディを通して評価を行うことで、大きな失敗を避けることにもつながります。
フィジビリティスタディとは何なのか?そして、PoCとの違いや具体的な実施例、記入例にも触れていきます。
この記事では、様々な企業の新規事業開発を支援してきた当社、スパイスファクトリーが、フィジビリティスタディについてご紹介します。
また、弊社スパイスファクトリーでは豊富な実績があります。弊社の概要やサービスプラン、過去の導入実績などをまとめた資料をご用意しました。気になる方はこちらからダウンロードしてください。
Contents
フィジビリティスタディとは?
はじめに、フィジビリティスタディの概要についてご紹介します。
フィジビリティスタディの概要
フィジビリティスタディとは、計画された事業やプロジェクトなどが実現可能か、実施することに意義や妥当性があるかを多角的に調査・検討する取り組みを指す言葉です。
「フィジビリティ(feasibility)」とは「実現可能性」を意味する英単語であり、実現可能性について事前に検証するのがフィジビリティスタディの位置づけです。
新規事業の開発や ITシステムの導入においては、多額の投資が必要となります。投資の可否を判断するために、フィジビリティスタディを行い、その妥当性を判断します。
フィジビリティスタディのメリット
フィジビリティスタディを実施する主なメリットは以下のとおりです。
リスクや課題の明確化
フィジビリティスタディでは、事業やプロジェクトの実施前に、多角的な視点から検証を行います。
これによりリスクや課題を明確化し、見切り発車による失敗や無駄な投資を回避できます。
意思決定の精度向上
フィジビリティスタディを実施することで、投資判断を行う経営層をはじめとしたステークホルダーに対して、客観的な根拠を提示できます。これにより、意思決定の精度を高められます。
課題解決方法の検討
技術・市場・財務・運用などの様々な観点から検証を進める過程で、リスクや課題に対する対処方法の糸口が見えてくる点もポイントです。
対処可能な課題については、事前に対応策を検討することで、事業やプロジェクトの成功確率を高められます。
フィジビリティスタディの種類と検証ポイント
フィジビリティスタディを実施する上では様々な考え方が存在しますが、ここでは「技術面」「財務面」「市場面」「運用面」の 4つの観点で検証を行う例を紹介します。
これらの要素はそれぞれ以下のような位置づけのものです。フィジビリティスタディを行う対象にもよりますが、多くの場合これらすべての観点で検証が必要となります。
技術面のフィジビリティ
プロジェクトを進める上で必要となる技術や設備が、現実的に導入・運用可能かを評価します。
〇既存技術で対応可能か
社内外に既に存在する技術・設備で要件を満たせるかを、特許や学術論文、関連企業へのヒアリングなどにより調査します。
〇外部パートナーとの連携が必須か
社内に存在しない技術である場合、技術提供者との協業体制の可否や契約条件、知的財産の観点も含めて検討します。
〇新規開発が必要か
既存技術で対応できない場合、既存の技術とのギャップを踏まえ、どの程度の開発が必要であるか開発期間・コストの観点から検証します。
財務面のフィジビリティ
プロジェクトのコストを予想し、それに見合う収益・価値創出の見込みを検証します。
〇開発・運用コストの想定
設備投資や人件費など初期投資と保守費用や更新費用などのランニングコストを明確化し、コスト構造と投資規模を整理します。
〇投資回収の見込み
検討対象とする事業やプロジェクトの収益モデルに基づき、何年で投資を回収できるか、キャッシュフロー予測により検証します。
〇収益性の妥当性
価格設定や顧客獲得コスト、LTV(顧客生涯価値)など、ボトムアップで収益性を予測します。収益性の根拠となる各指標が現実的な予測となっているかがポイントです。
市場面のフィジビリティ
ターゲット市場におけるニーズの有無や競合調査、市場の成長性などを調査し、事業として成立するかを判断します。
〇市場規模・成長性
対象市場が十分な規模を持ち、今後の成長が見込まれるか、統計データや調査会社によるレポートなどを活用して調査します。
〇顧客ニーズとの合致
提供価値が顧客の課題や期待にフィットしているか、ペルソナ設計やユーザーインタビュー、ユーザーテストなどを通して推測します。
〇競合との差別化要素
競合企業との比較を行い、技術面や価格面などに優位性があるかを検証します。提供するサービスや商品の模倣困難性も重要な視点です。
運用面のフィジビリティ
事業やプロジェクトを継続的に運用するための人的なリソースや組織が整っているかを確認します。併せて、法令面で課題が無いかもチェックします。
〇必要な人材・スキルの有無
事業やプロジェクトを進める上で、必要なスキルを持った人材が十分な人数存在するかを検証します。不足がある場合、育成や再配置の計画も含めて検討します。
〇外注・採用による補完可能性
リソースが不足する場合、外部で補えるかを検討します。外部リソースを利用するコストは収益性にも影響するため注意が必要です。
〇法規制・業界基準のクリア
関連する法令を洗い出した上で、事業やプロジェクトの展開において抵触するものが無いかをチェックします。前例がない事業など、関係省庁との調整が必要となるケースもあります。
フィジビリティとPoCとの違い
フィジビリティスタディと混同されやすい概念に PoC(Proof of Concept:概念実証)が挙げられます。
PoC は、ビジネスアイディアなどの実証を目的とした、プロトタイプ開発や検証のことを指します。
一般的に、机上で行われるケースが多いフィジビリティスタディに対して、PoC はプロトタイプシステムの開発などにより実際にユーザーが触ることができる試作品を開発し、現実世界で試行・検証を行います。
PoC を実施すること自体にも一定のコストがかかるため、フィジビリティスタディで机上検証を行い、実現可能性が十分に高いと判断できた場合に PoC のフェーズに移るという進め方も採用されます。
PoC については以下の記事でもご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。
関連記事:「PoCとは。ビジネスにおけるPoC活用メリットや進め方を徹底解説」
フィジビリティスタディを実施すべきタイミング
一般的に、新規事業開発や新製品・サービス開発は以下の流れで実施されます。
- 事業・サービス構想
- フィジビリティスタディ
- コアバリュー策定
- PoC
- 本番開発
1.事業・サービス構想
事業やサービスのコンセプトメイキングや事業計画の立案を行う。
2.フィジビリティスタディ
市場規模や競合状況、技術的制約、法規制の有無などを確認し、机上で実現可能性を検証する。
3.コアバリュー策定
フィジビリティスタディの結果を踏まえ、事業やサービスの提供価値を定義する。
4.PoC
プロトタイプ開発やユーザーテストを通じて、ユーザーニーズとの合致や技術的実現性をさらに具体的に検証します。
5.本番開発
ユーザーに製品・サービスを提供するため、正式リリースできるプロダクトを開発する。
上記の流れのとおり、フィジビリティスタディは事業・サービス構想を行った後、その内容が妥当であるか、実現可能性はあるのかを検証するために実施されます。
その後、PoCなどを通してユーザーニーズへの合致状況の確認やプロダクトの品質向上、費用対効果の検証などを行い、本番開発に進む流れが一般的です。
フィジビリティスタディの進め方
フィジビリティスタディは、実施目的と対象を明確化しつつ、調査・分析による検証を行い、最終的な意思決定につなげていくプロセスで進めていきます。
目的と範囲を明確にする
フィジビリティスタディを始める前に、目的と範囲を明確にする必要があります。
技術面だけかコスト面も含める必要があるのか、法律面の検証は必要ではないのかといった視点で、対象範囲を整理します。
例えば、システムを活用して技術面で差別化した事業を提供するにあたってフィジビリティスタディを行う場合であれば、実用に足る精度でサービスが提供できるといった観点での検証が重要です。
この場合、技術検証を中心にフィジビリティスタディを進めていくこととなります。
調査と分析で実現可能性を検証する
目的と範囲を明確にしたら、実現可能性の検証を進めていきます。必要なリソース・技術的制約・見込みコスト・法令面の遵守など、構想の実現に向けて障害となり得る要素を洗い出し、現実的な事業やプロジェクトとして成立するかを検証していきます。
例えば、新規事業開発においてシステムを活用するケースであれば、既存システムとの連携可否やサービス提供に必要なデータ・コンテンツ等の利用可否、システム構築にかかるコストの想定などが必要となります。
また、市場調査や競合分析を通じて、新規事業やそれに伴うシステム投資に対する、経済的な妥当性を検討することも重要です。
評価・分析結果の取りまとめと報告
調査と分析が完了したら、結果を取りまとめ、経営層をはじめとしたステークホルダーへ報告します。
ここでは、意思決定可能なレベルで情報を整理・可視化することが重要です。
実施結果を単にまとめるだけでなく、事業やプロジェクトの成功シナリオ/失敗シナリオ、リスク要因とその対応策、事業化した場合の投資対効果など、実施の可否を判断できる観点で整理すべきです。
特に経営層に対しては、投資対効果をはじめとした経済的なインパクトやリスクを意識した報告が重要となります。
また、現場の責任者や担当者に対しては、導入プロセスや運用面の課題など実務に即した内容を明確化することがポイントです。
意思決定をする
フィジビリティスタディの目的は、検証の結果に基づいて行動を選択することにあります。
最終的に、採用、中止、延期、代替案の検討など、フィジビリティスタディの結果を踏まえて事業やプロジェクトの投資可否や実施可否を判断します。
特に、大規模プロジェクトや複数部門が関与する場合など、ステークホルダーが多いケースでは、意見をまとめるのも簡単ではありません。
フィジビリティスタディによるファクトにより、感情や前例に流されない意思決定がしやすくなります。
フィジビリティスタディで検討する項目と実践例
以下では、上述した「技術面」「財務面」「市場面」「運用面」という 4つの検討項目について、より具体的にご紹介します。
ここでは、新規事業開発として「生成AI を活用したコールセンターの顧客対応支援」を例として取り上げたいと思います。
フィジビリティスタディをイメージしやすいよう、検証項目の記入例をご用意しております。よろしければ下記よりダウンロードしご覧くださいませ。
①技術面
技術面は、本例のような新規事業における大きな差別化要素となります。一方で、その技術が一般に提供するために十分な品質であり、また現実的に利用できるのかについては検証が必要です。
コールセンターにおける生成AI を利用した顧客対応が現実的なものであるのか、文献や既存技術の調査を行います。
主な調査方法は研究論文や既存の開発事例の探索、生成AI を提供する企業へのヒアリングとなるでしょう。
ここで得られた情報から、生成AI により顧客対応が現実的に利用できる精度で行えるのかを机上で検討します。
②財務面
新規事業開発にはお金がかかります。今回実施しようとしているサービス開発にどの程度の投資が必要であるのか概算金額を把握します。
主に、プロダクトの開発コスト、宣伝・営業費用、導入や運用にかかる費用などが想定されます。
想定される投資金額をどのように賄うかも検討する必要があります。
自社が保有する資金で資金を賄えない場合は、外部からの調達について検討します。
大きくは金融機関からの融資と投資家からの投資という2つの選択肢があります。
融資は回収可能性が高いケースに、投資は回収可能性が低いものの大きなリターンが見込める可能性がある場合に活用されます。
今回例に挙げている挑戦的な新規事業の場合は、投資家からの投資や予算管理部門から決裁を引き出せるポテンシャルがあるかという観点での検討が必要でしょう。
③市場面
本サービスが市場においてニーズがあるかどうかもフィジビリティスタディの検討対象となります。
新規事業開発においては、既存の知識や人脈でのつながりなどからアイディアを思いつくことも多いですが、改めて提供するサービスに本当にニーズがあるのかを精査します。
市場調査のフレームワークとして良く知られているのがファイブフォースモデルです。
ファイブフォースモデルは、「業界内の競合」「代替品の脅威」「新規参入者の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」という 5つの観点で市場分析を行います。
コールセンターにおける顧客対応支援サービスにはどのようなものがあり、どのような価値を提供しているのか、また買い手となるコールセンター運営者はどの程度存在し、どの程度の投資余力があるのかなどを整理することで、市場分析を進めます。
④運用面
実際に新規サービスを提供していくためには、人的なリソースを含めた運用体制を整える必要があります。
一般的に、新規事業の提供においては「営業」「開発」「カスタマーサポート」などのメンバーが必要です。
近年では、カスタマーサクセスとして顧客の成功を支援する役割も重要視されつつあります。
特に生成AI を活用するという今回の事例では、開発担当者として AI に関するスキルを持ったエンジニアも必要でしょう。
これらのスキルを持った人的リソースを確保できるかもポイントです。
フィジビリティスタディに役立つデータ一覧
主に机上で実施するフィジビリティスタディを進めていく上では、各種文献を基に調査を行っていくことになります。
ここでは、特に技術調査や市場調査などに活用できるデータについてご紹介します。
こちらでご紹介させていただくものにつきましては外部サイトへ遷移いたしますので、あらかじめご留意くださいませ。
情報通信白書・DX白書
国内の IT・通信に関する技術動向や市場動向は、総務省が年次で刊行している情報通信白書※1や、IPA が取りまとめを行っている DX動向※2にて知ることができます。
令和 7年度版の情報通信白書では、社会基盤化したSNSやクラウドなどの動向やAIの爆発的な進展状況、国内外のICT産業の概況などについて整理がされています。
AIの動向については、国内外のLLMモデルの開発動向や企業・個人におけるAI活用状況が網羅的に調査・分析されており、参考となります。
DX動向2025では、国内のみならず、国外のDXに関する取り組み状況が分析されています。事業開発においてどのような技術が利用できるか、また先進的な企業はどのような技術を活用しているのかを把握できます。
IPAでは継続的にDXに関する調査を行っており、DX動向により企業のDX推進状況やDXに対するモチベーションなどの時系列変化を把握できるのもポイントです。
※1 引用記事:総務省「令和7年度版情報通信白書」
※2 引用記事:独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2025」
総務省統計局
市場調査を行う上で有効なのが政府の各省庁・機関が実施している統計調査です。これらの情報は、総務省統計局が一元的に取りまとめを行っています。
たとえば、市場調査を行う上では以下のような統計情報が参考になるでしょう。
〇国勢調査:地域別人口数、世帯状況、就労状態などを把握できる。5年間隔で実施されるため最新の状況とずれが生じる可能性がある点に注意が必要。
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/index.html
〇家計調査:家庭における家計の収支を把握できる。人々が何にどれだけお金をかけているのかを知ることができる。
https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html
〇サービス産業動向調査:産業分類別に売上高と従事する従業員数を月次で調査し、推移を確認できる。
https://www.stat.go.jp/data/mssi/index.html
〇小売物価統計調査:月次で主要品目についての販売価格を調査したもの。商品の価格変化状況を把握できる。
https://www.stat.go.jp/data/kouri/index.html
上記以外にも、目的に応じて様々な統計情報を活用できます。
民間コンサルティング企業の書籍
その他、民間コンサルティング企業においても様々なデータが公開されています。一例をあげると以下のとおりです。
〇野村総合研究所
https://www.nri.com/jp/knowledge/report
〇ボストン・コンサルティンググループ(BCG)
https://www.bcg.com/ja-jp/about/corporate-newsroom
〇NTTデータ経営研究所
https://www.nttdata-strategy.com/knowledge/reports/
フィジビリティスタディで大きな失敗を避けよう
この記事では、フィジビリティスタディの概要や実践例、検討項目、活用できるデータソースなどについてご紹介しました。
フィジビリティスタディの段階でどれだけ精度高く検証を行えるかは、その後の PoC や本番開発の成否にも影響します。
当社ではフィジビリティスタディだけでなく、超高速PoCサービス やプロトタイプ開発まで含めた支援サービスをご提供しております。
詳細を知りたい方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードしてください。
ご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
参考:スパイスファクトリー株式会社 100の失敗から見つける、強い新規事業。モノで語りながら推進する超高速PoCサービス提供開始
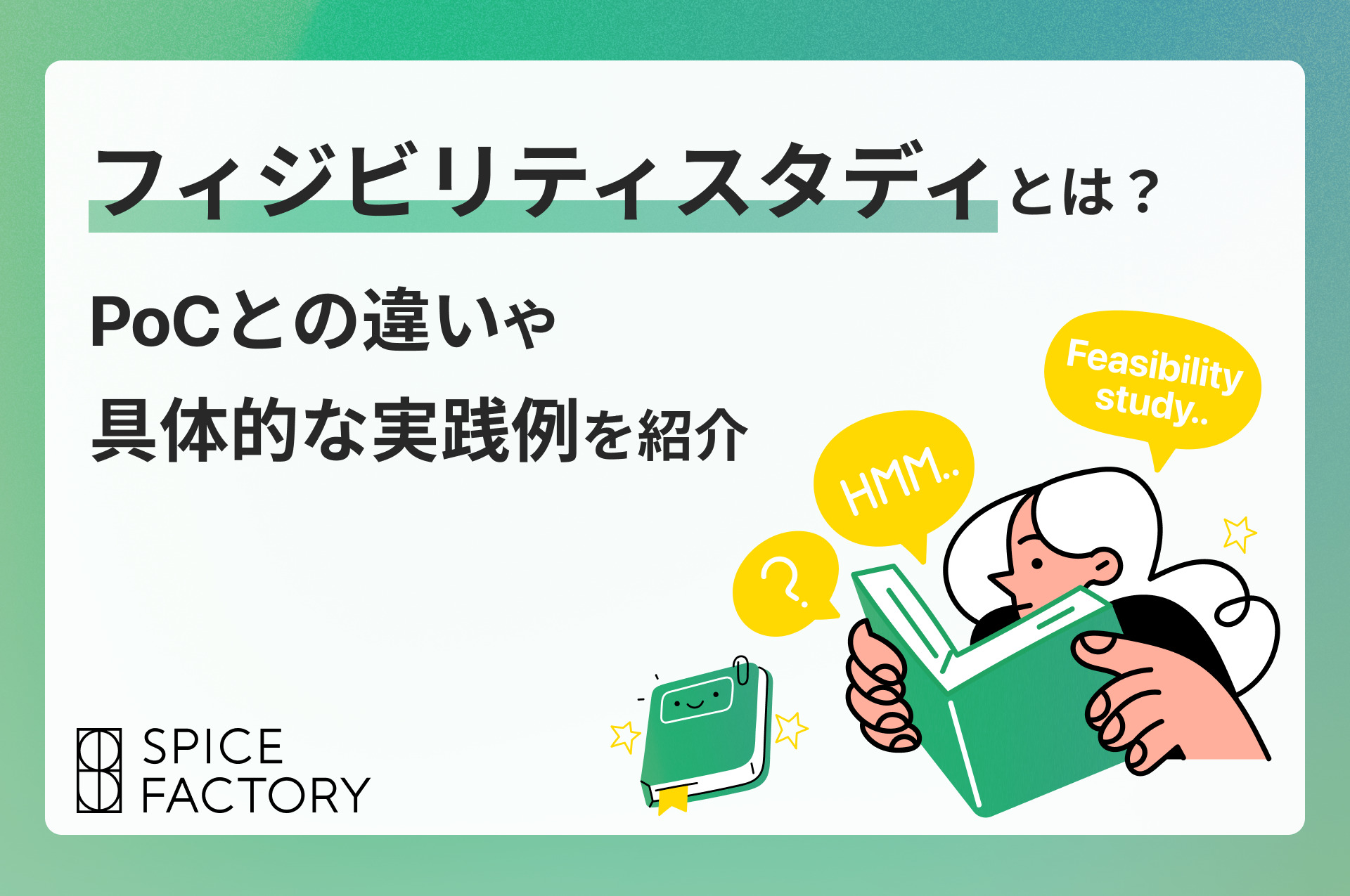
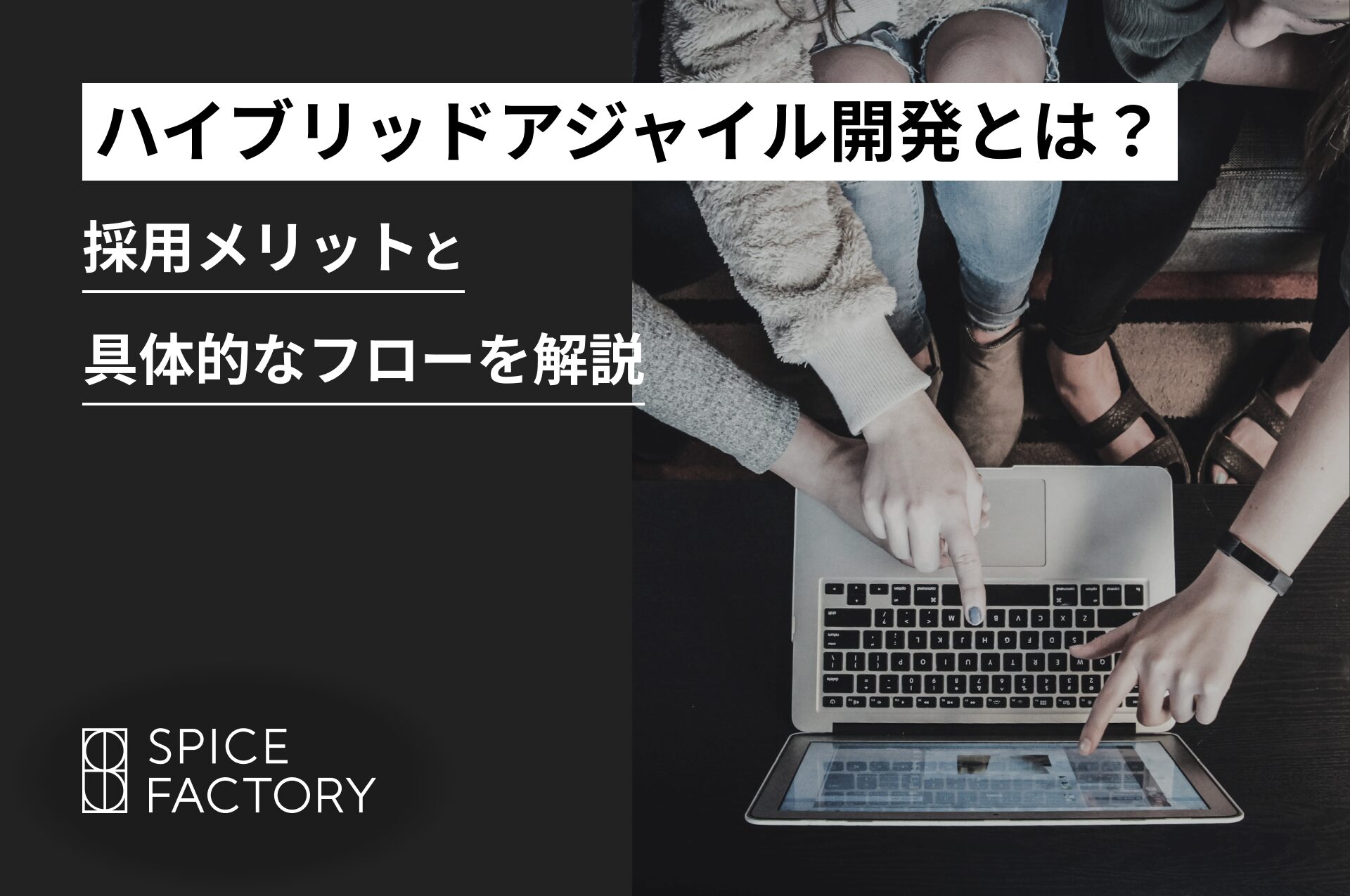
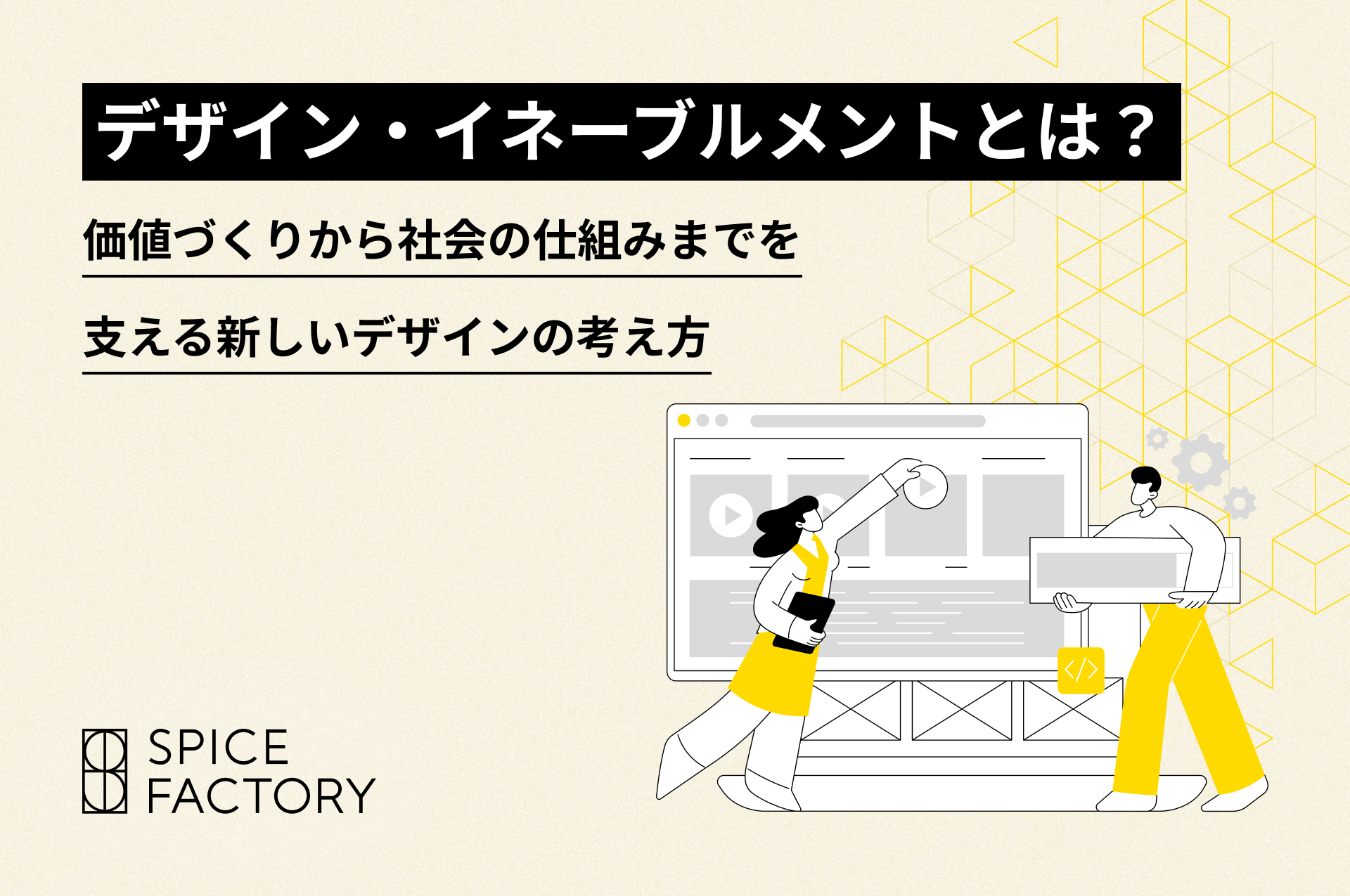

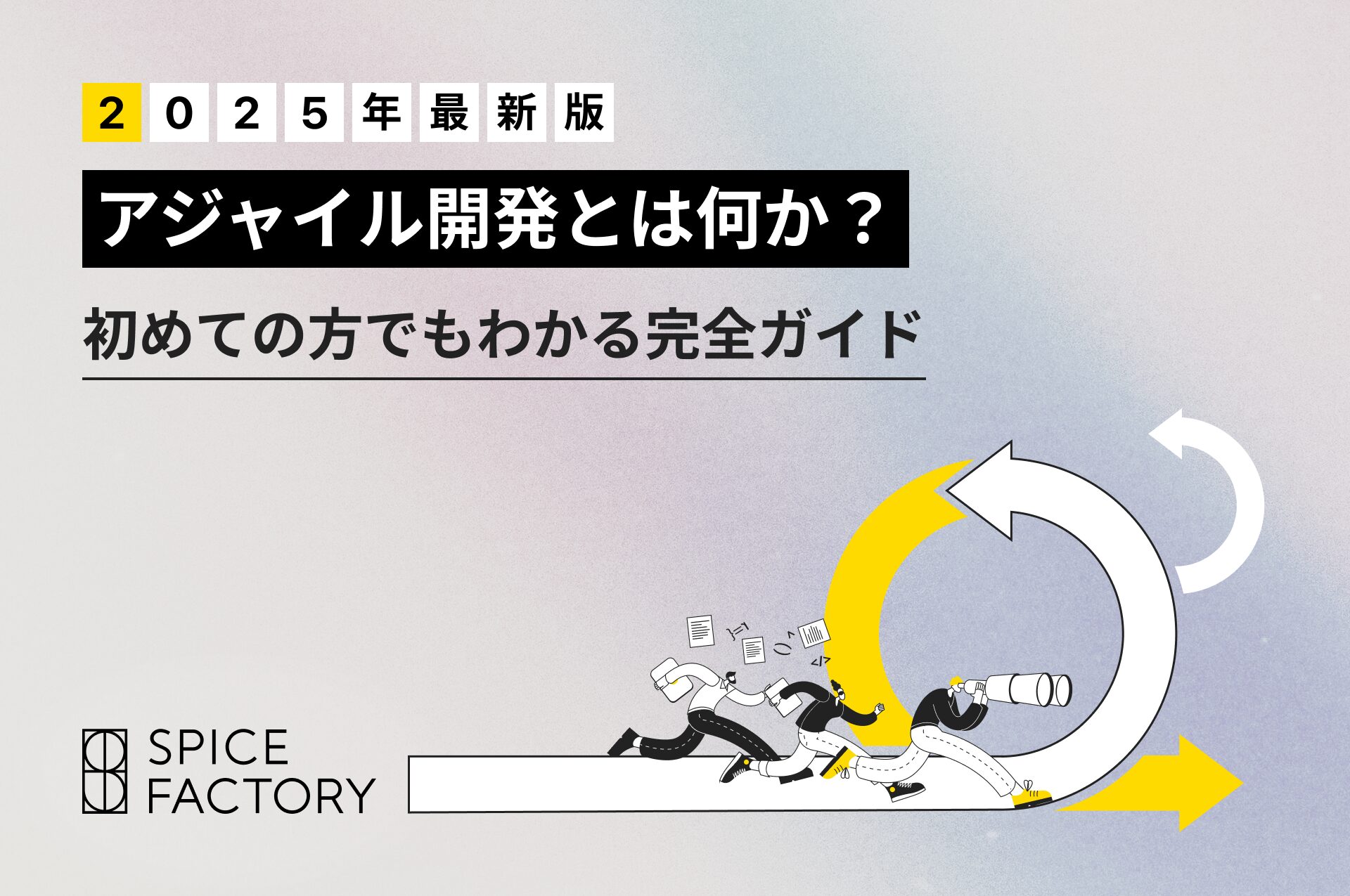


About The Author
スパイスファクトリー公式
スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。