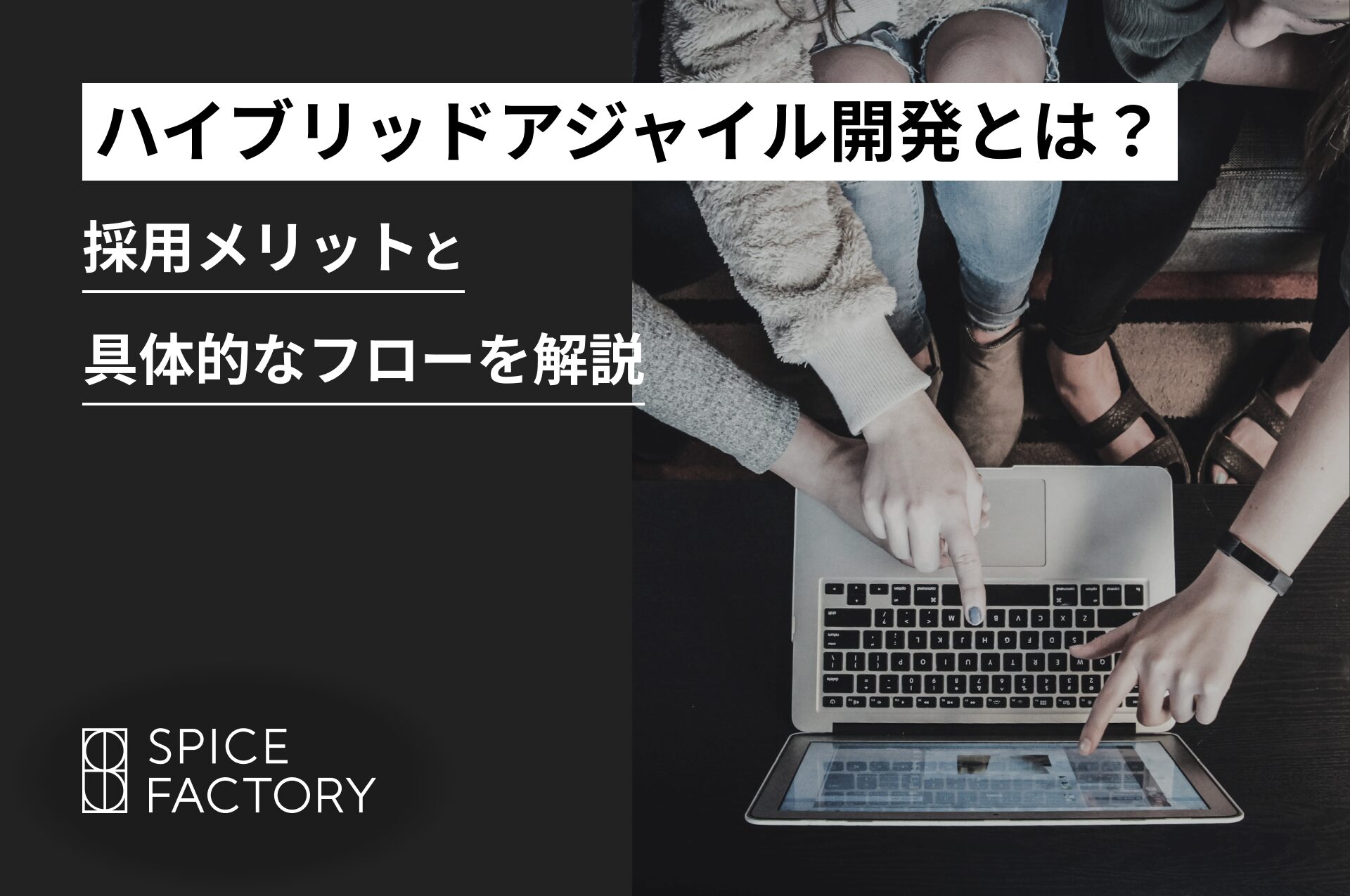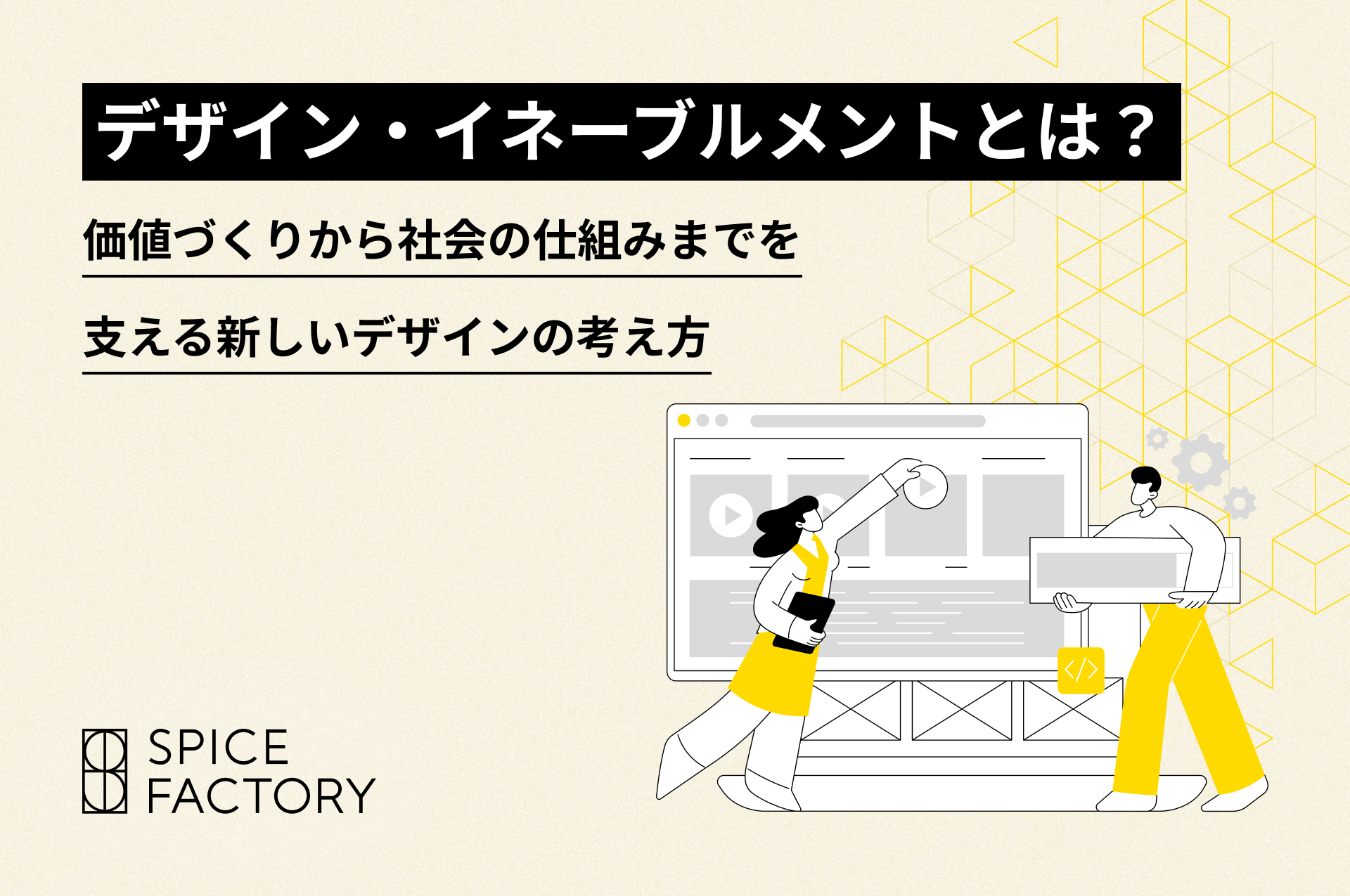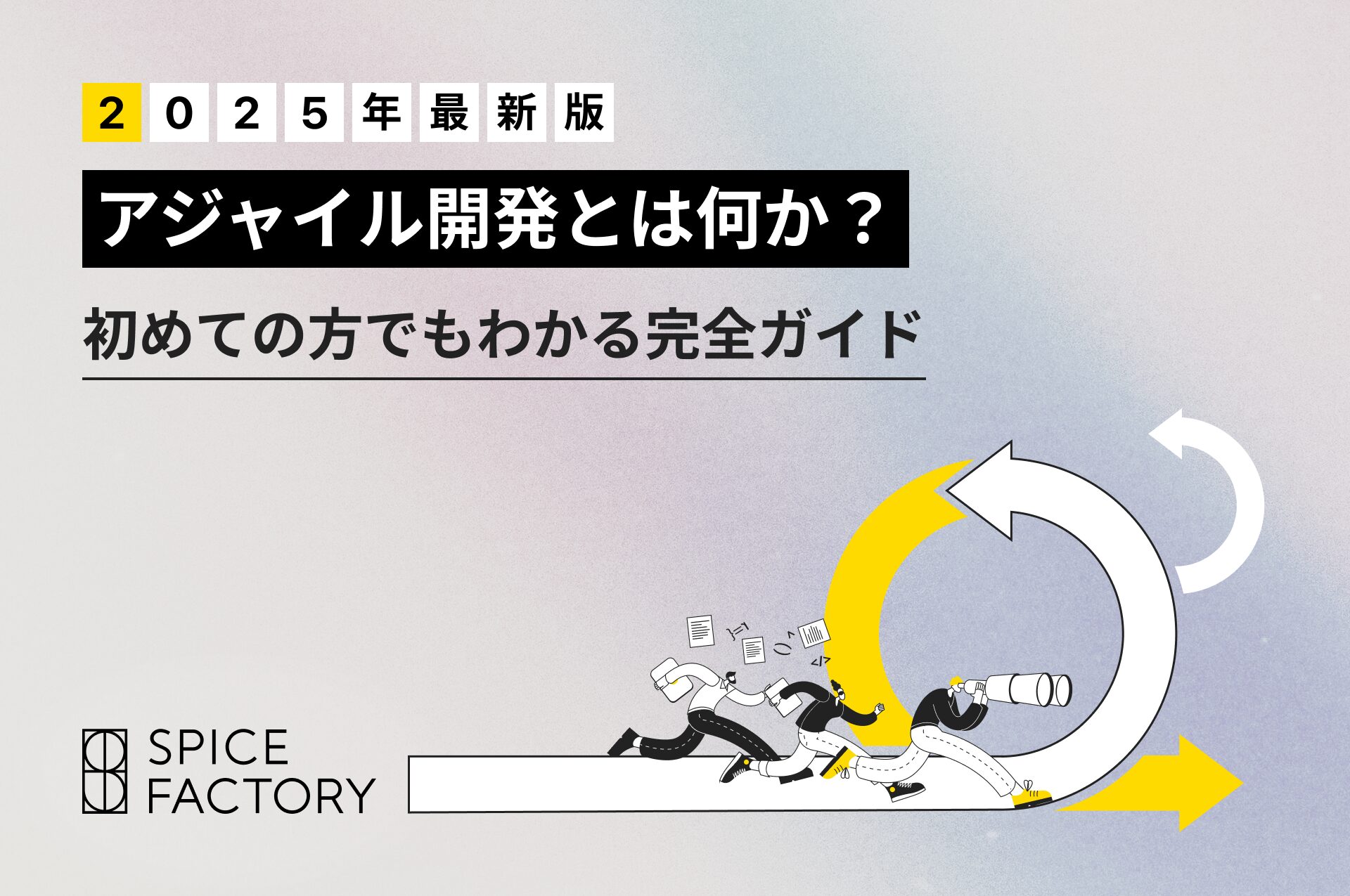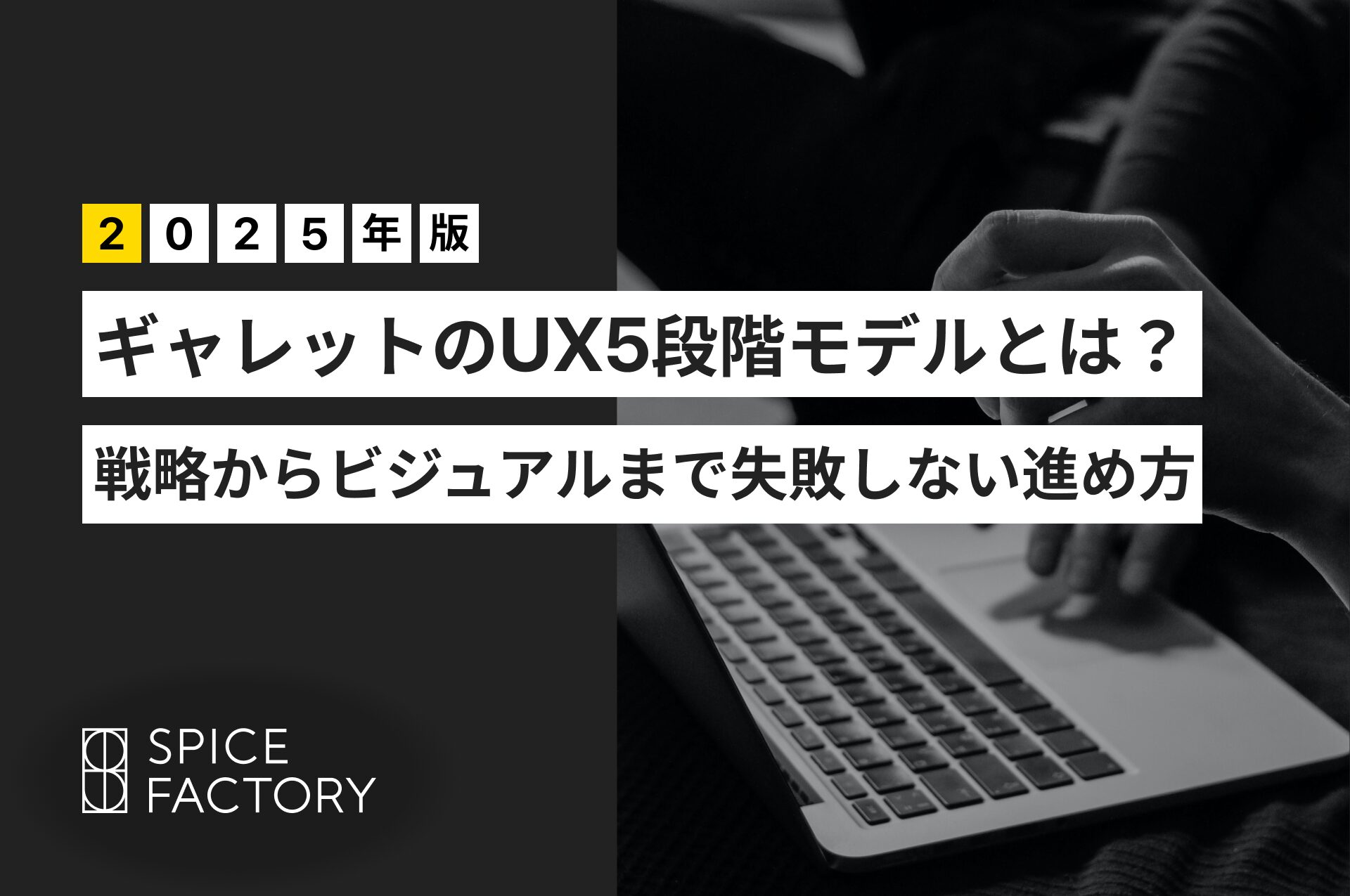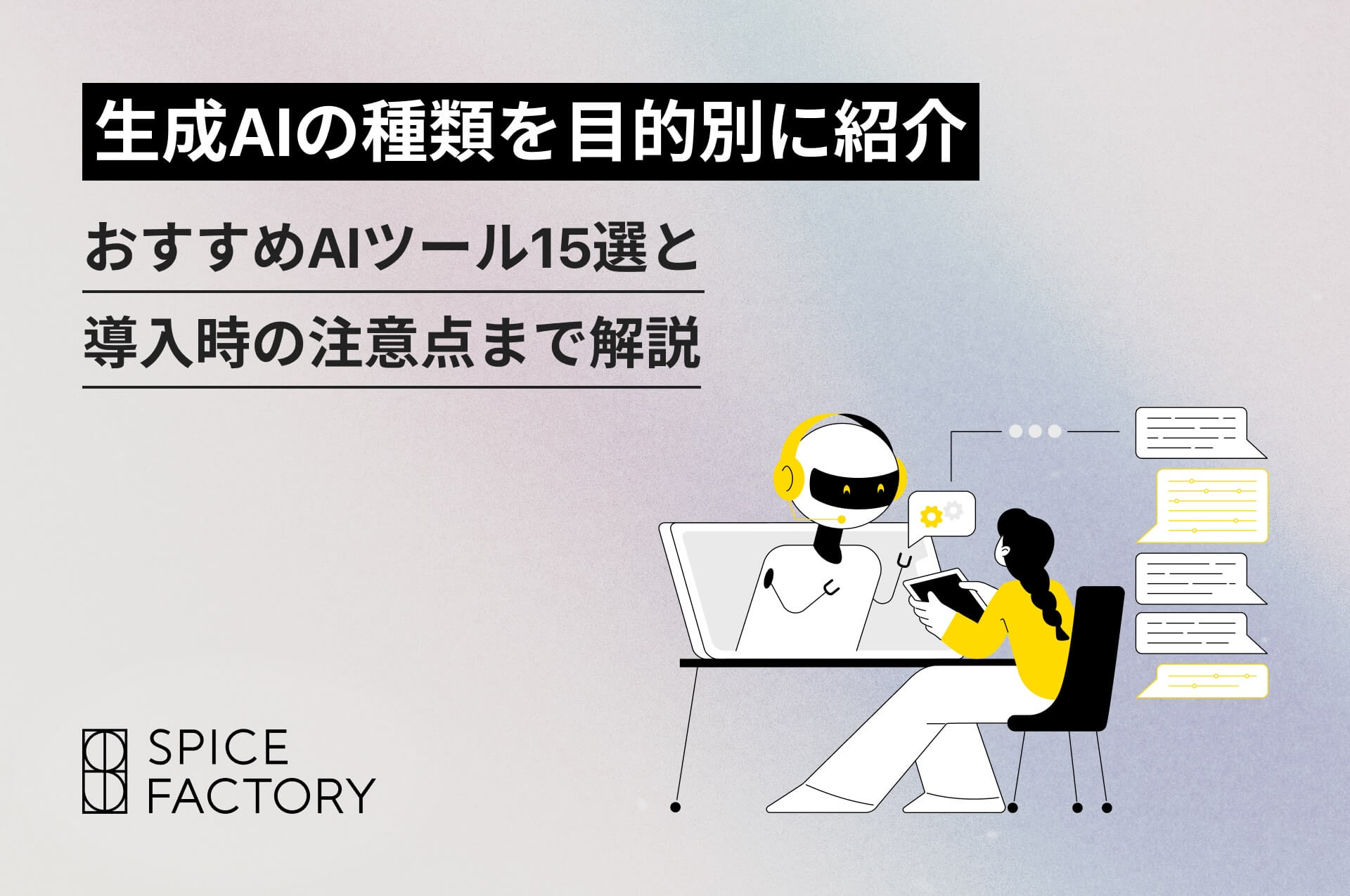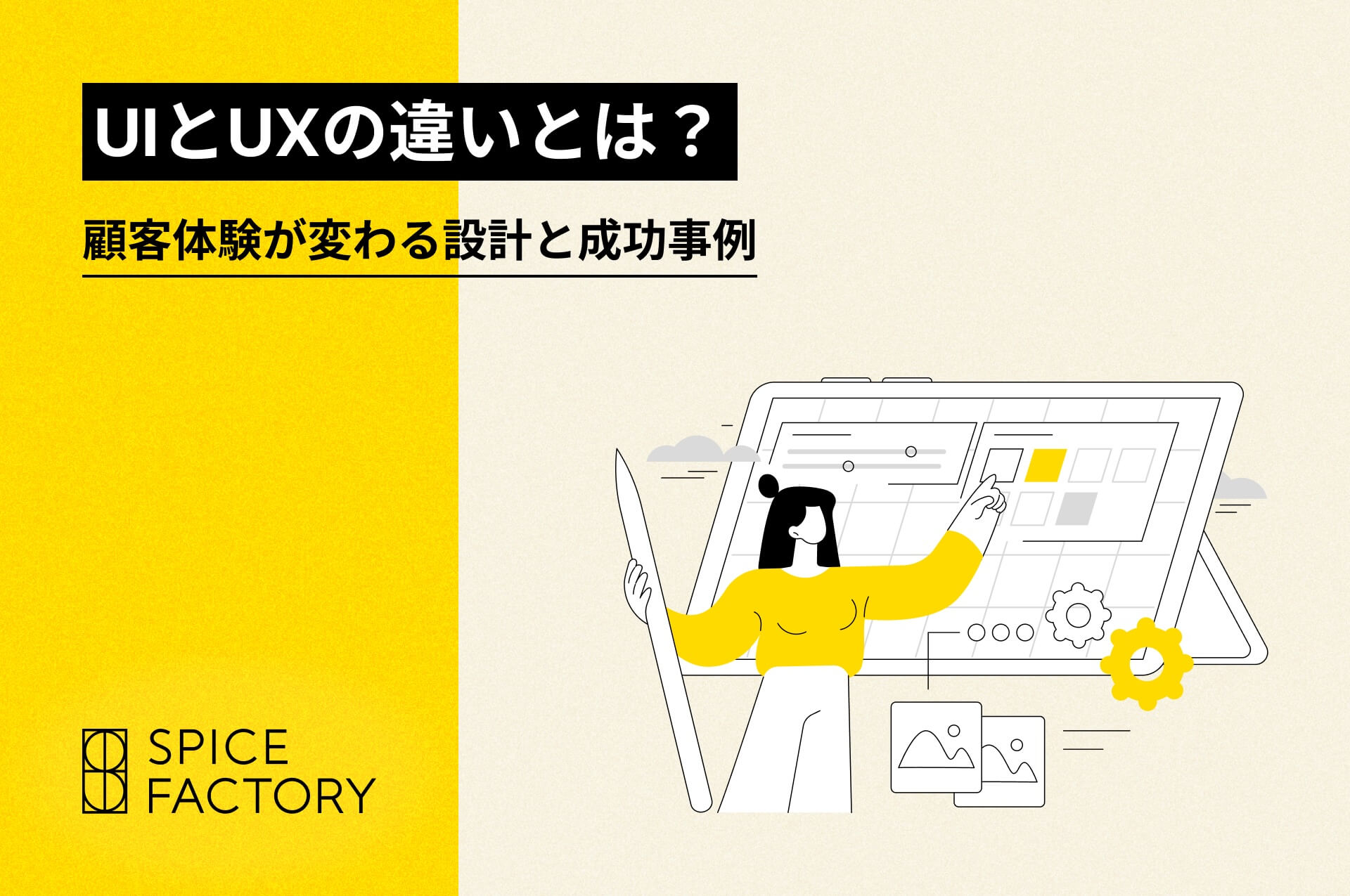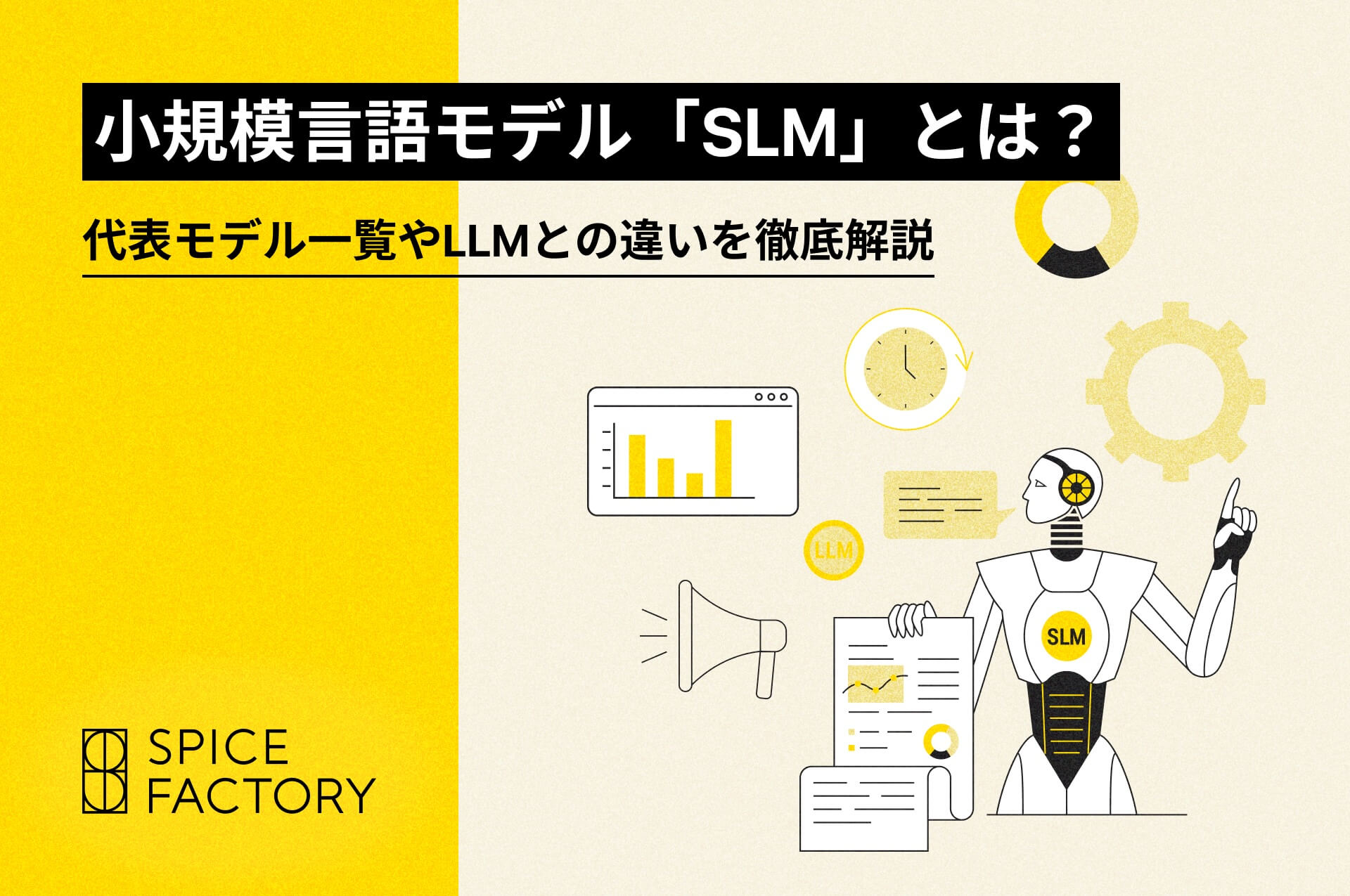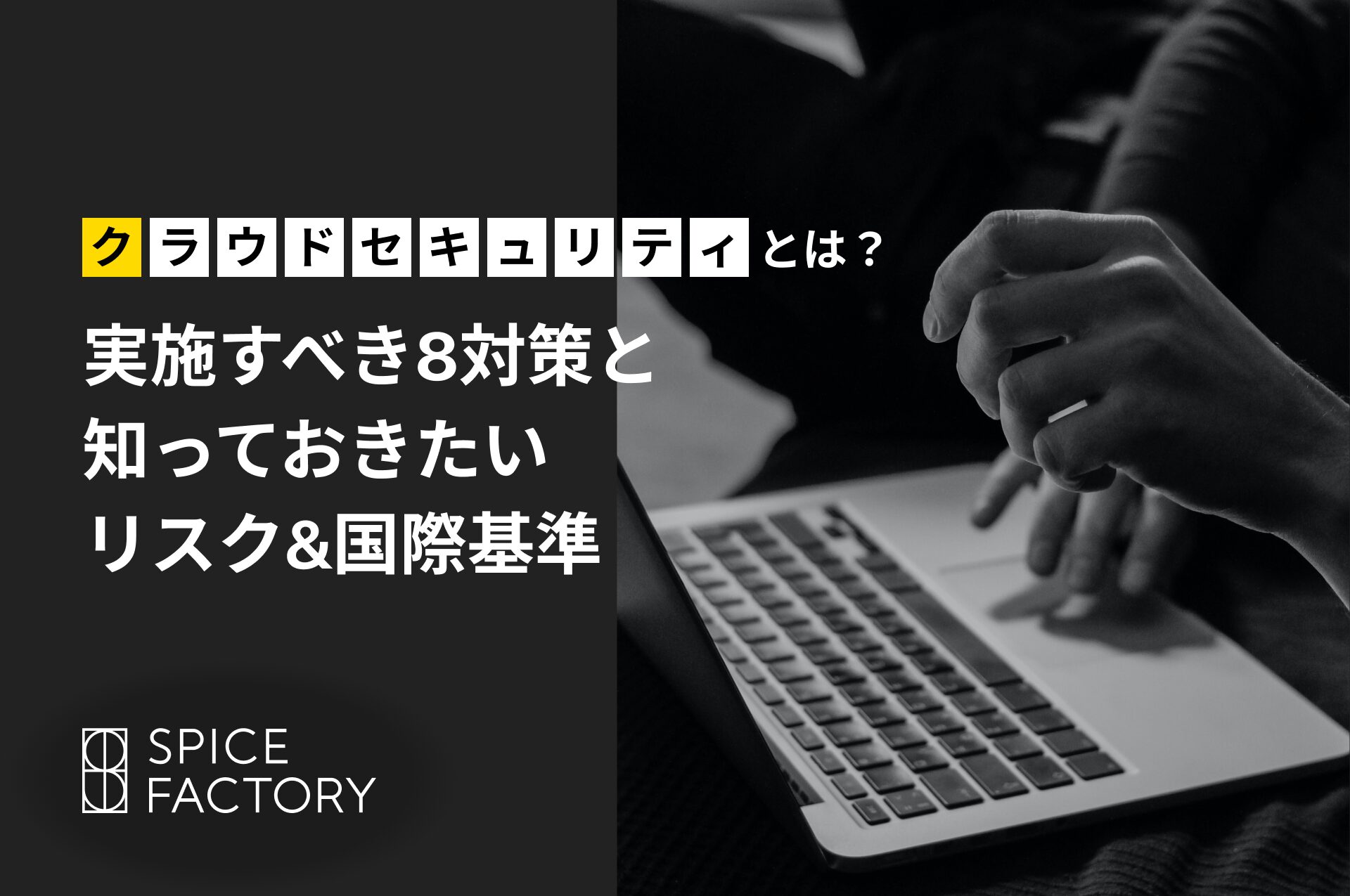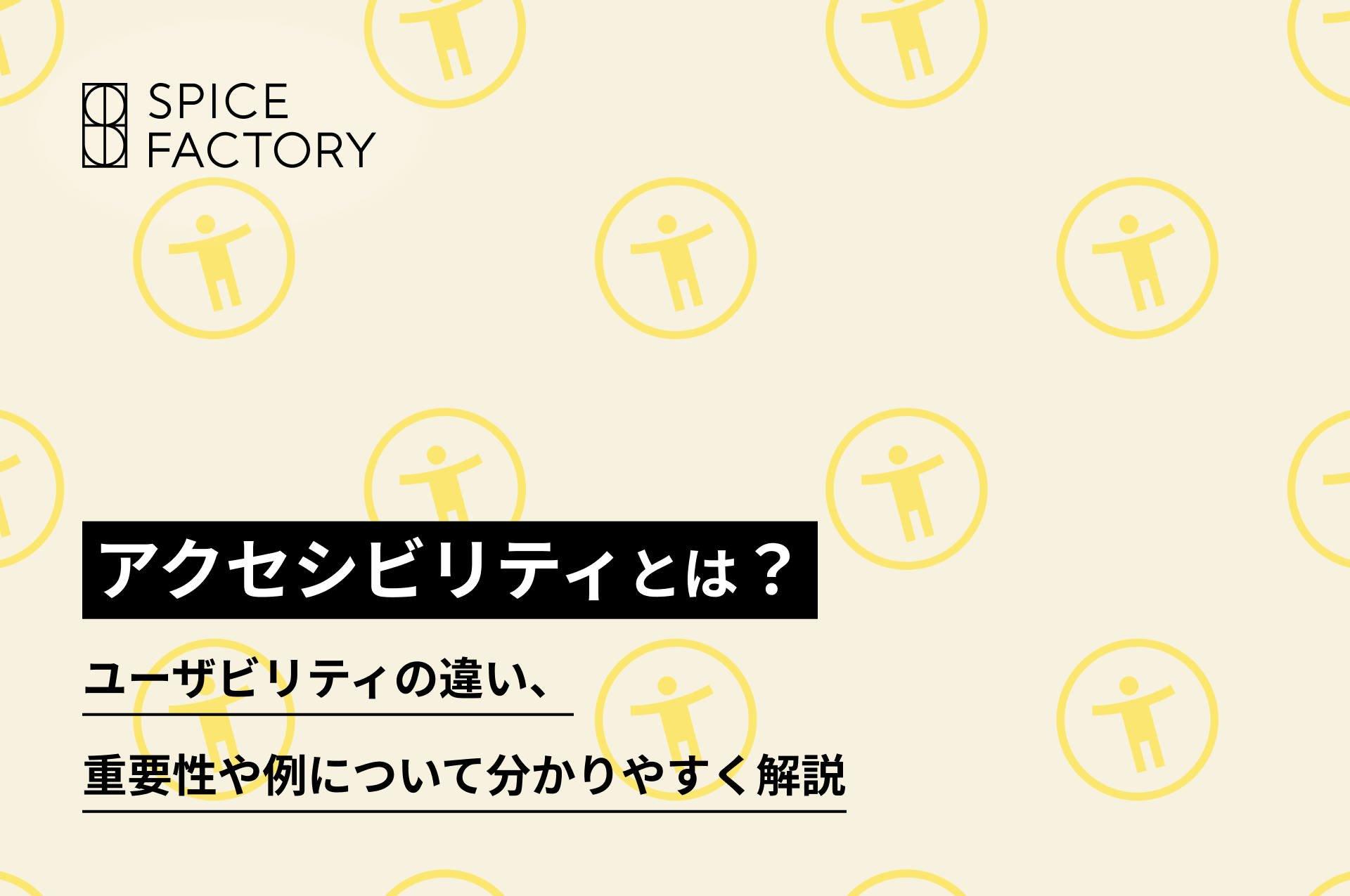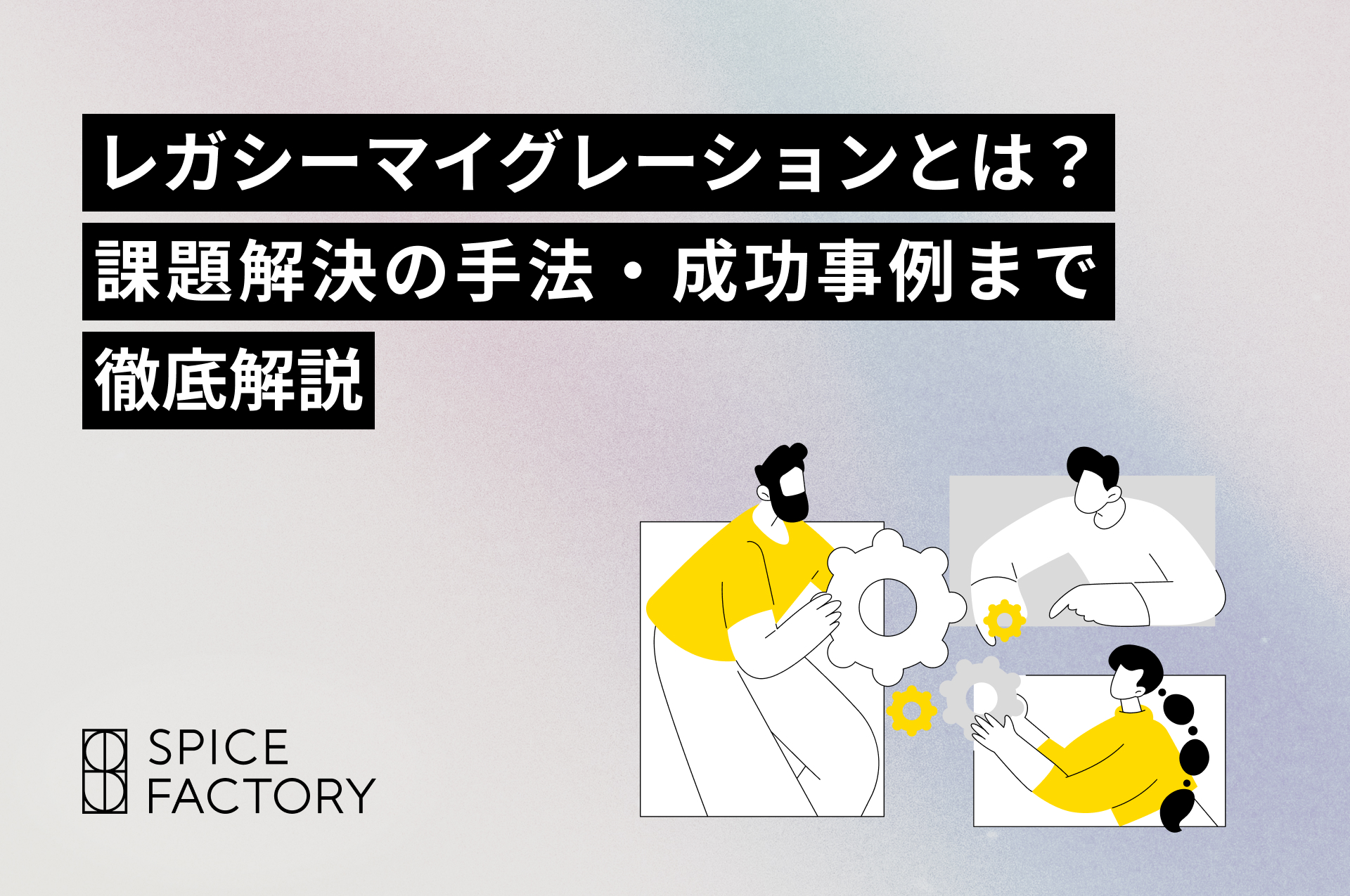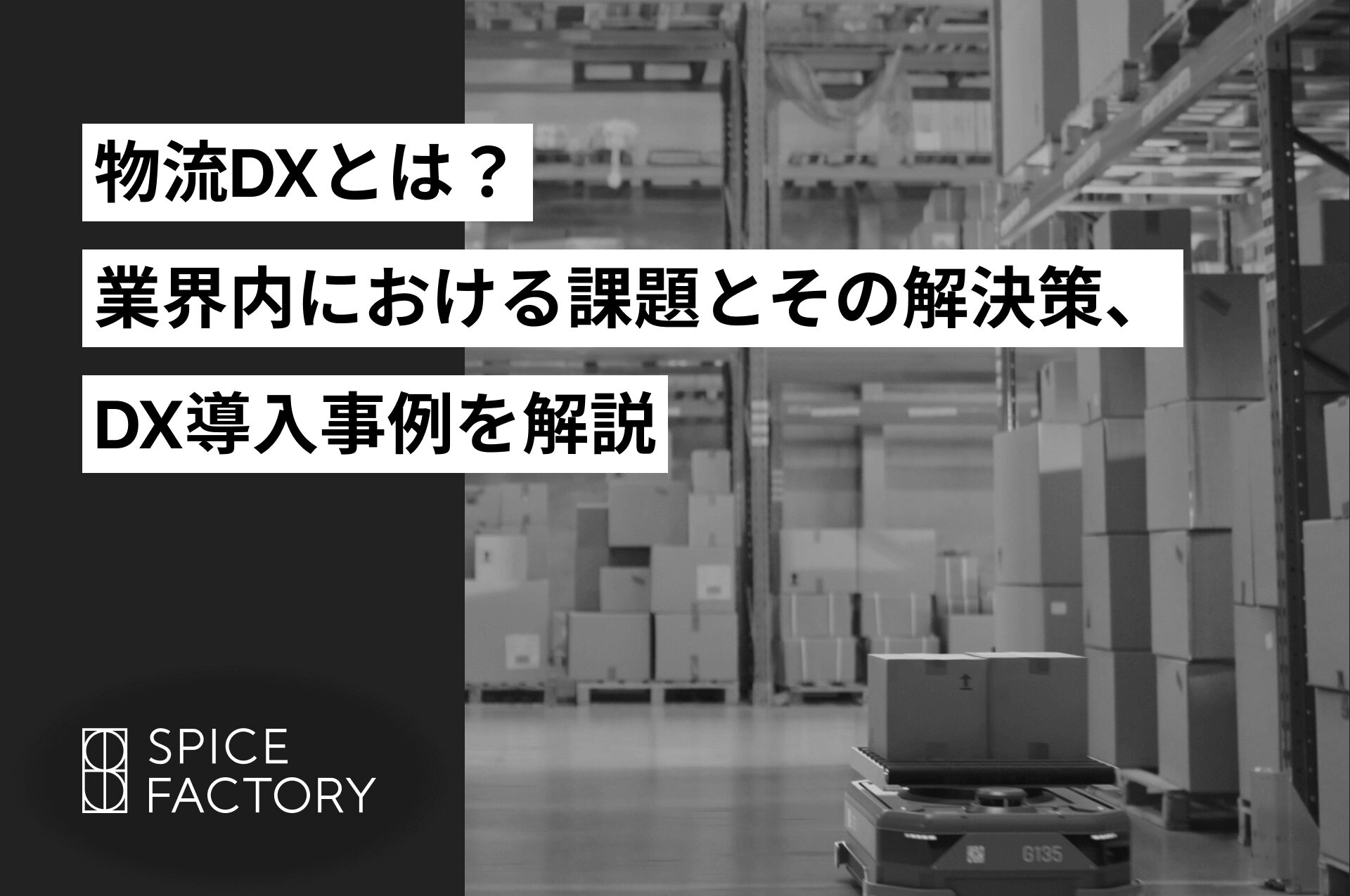アジャイルの強みを活かしつつさらに発展させることができる、ハイブリッドアジャイルに注目が集まっています。ハイブリッドアジャイルは、組織としての意思決定と現場での迅速な対応を両立させられる開発手法です。この記事では、ハイブリッドアジャイルの考え方や必要性、ハイブリッドアジャイルによる開発フローについて解説します。
かつては製品の見た目や広告のビジュアルを整えることが主な役割だった「デザイン」は、現在では課題解決やイノベーション創出のためのスキルとして、あらゆる領域で必要とされています。誰でもデザインをする時代が訪れている一方で、ま […]
VOC(Voice of Customer=顧客の声)が、ビジネスの成長を支える資産として注目されています。本記事ではVOCの基本的な意味からマーケティングに活用するメリット、具体的な収集・分析方法、成功事例まで詳しく解説します。生成AIとの組み合わせによる最新の活用法についても触れますので、ぜひ最後までご覧いただき貴社のマーケティング戦略にお役立てください。
変化の激しい時代において、「変化への適用力」は企業の成長を左右する重要な要素となっています。アジャイル開発は、システム開発やデジタル活用における変化対応力を高める手法として、現在ではソフトウェア開発にとどまらず、人事・マーケティング・営業・オペレーションなどの非IT部門にも広がっています。本記事では、アジャイル開発の基本からウォーターフォール開発との違い、代表的な手法である「スクラム」について、そして実際の導入事例まで、アジャイル開発に初めて触れる方にもわかりやすく、網羅的に解説を行います。
近年、デザインの現場において「デザインシステム」という言葉を聞く機会が増えました。デザインシステムは、企業が提供するWebサイトやアプリのデザインを統一し、品質と効率を高めるための指針です。ブランディングの観点だけでなく、効率化や品質担保の観点からもデザインシステムの構築と適用が有効です。本記事では、デザインシステムの基本から導入メリット、具体的な作り方、活用ツール、事例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
UX設計を失敗せずに進めるには、ギャレット氏が提唱した「UX5段階モデル」が効果的です。UX5段階モデルとは、戦略から具体的なビジュアル設計までを段階的に整理するためのフレームワークで、一貫したUX設計が実現できます。本記事では、UX5段階モデルの概要と各層の特徴、導入のメリットや活用ポイントについて解説します。
「生成AIを使えば、エンジニアなしでもシステム開発ができるのでは?」と考える方もいるでしょう。ノーコードツールやAIエージェントの進化により、開発のハードルが下がったのは事実です。しかし、現実は「AIにどう指示すればいいのかわからない」「生成されたコードの品質や保守性に不安がある」といった声も多く、AIだけに頼る開発には限界があります。生成AIはあくまで「補助ツール」であり、効果を最大限に引き出すためにエンジニアは必須です。本記事では、生成AIを活用して開発を効率化している企業の事例とともに、実際に使われているAIツールの種類や特徴について詳しく解説します。
生成AIは、文章作成や画像生成、音声合成など、さまざまな用途のツールが登場しています。しかし、目的に合わないAIを選ぶと「業務に活かせなかった」「現場で定着しなかった」といった失敗をする可能性も高くなるでしょう。そこで本記事では、生成AIの種類を「業務目的別」に整理したうえで、おすすめのAIツールを15個を紹介します。
スマートフォンやWebサービスの進化で、企業の成長には「ユーザーにとって使いやすい」画面設計が不可欠となりました。その基盤を支えるのが、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)です。UIとUXはそれぞれ異なる役割を担っています。ユーザー満足度を高めるには、両者の正しい理解と適切な設計が重要です。本記事では、UIとUXの違いを明確にし、ユーザー中心設計がもたらす顧客体験の価値や成功事例、実践のポイントについてわかりやすく解説します。
「LLMとSLMの違いは?」「SLMを導入するメリットはある?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。SLMは、LLMと比べてパラメータ数が少なく動作が軽量なため、エッジデバイスやオンプレミス環境でも運用できる点が魅力です。コストを抑えつつ、必要な範囲でAIの導入を実現できる手段として、各業界で活用が広がっています。本記事では、SLMの概要やLLMとの違い、導入するメリットに加えて、代表的なモデル10選を詳しくご紹介します。
物流業界は人手不足や再配達問題、環境負荷、業務の属人化など、さまざまな課題を抱えています。改善のためには、現場の課題を的確に見極めてテクノロジーやシステム導入を通じた物流効率化への取り組みが欠かせません。この記事では、物流効率化の成功事例や成功に導く考え方について解説します。課題解決の糸口を探している物流業界の担当者の方はぜひ、参考にしてください。
要件定義とは何か?具体的な進め方とポイントを解説します。要件定義はシステム開発プロジェクトにおいて最も重要な工程です。新規事業開発で参考にしてください。
クラウドセキュリティとは何か?実施すべき8つの対策知っておきたいリスクと国際基準を書いた記事。クラウドサービスは利便性が高く業務効率化につながるため、多くの企業で導入が進んでいる一方で情報漏洩や不正アクセスのリスクもあり注意が必要です。企業の信頼性を守るために特性を正しく理解し適切な対策を講じましょう。
より多くのユーザーに対するニーズを満たすために、製品開発やサービス改善を行う際には、ユーザビリティとアクセシビリティの両方を考慮し、分かりやすく使いやすいサービスを開発することが重要です。本記事では、アクセシビリティの改善に興味がある担当者の皆様に向けて、アクセシビリティとは何か?ユーザビリティとアクセシビリティの基本的な違いや、アクセシビリティを考慮する重要性、また、アクセシビリティの改善例について分かりやすく解説します。
サプライチェーンDXとは、サプライチェーンマネジメントを変革するためにデジタル技術を活用する取り組みです。人材不足や企業競争力の強化、効率性の向上、コスト削減など、サプライチェーンの課題を解決する手段として注目されています。しかし、「何から始めればいいのか」「どのツールを使うべきか」「効果が出るのか」といった不安を抱えている企業も多く、日本では期待するほどDX化が進んでいない状態です。本記事では、サプライチェーンにおけるDXの基本、現在直面している課題、成功に導くための改革ポイントについてわかりやすく解説します。
レガシーシステムの問題を解決するためには、レガシーマイグレーションによりシステムを刷新し、モダンなシステムへと作り替えていく必要があります。一方で、レガシーマイグレーションの取り組みは簡単ではありません。システムの特性や自社の環境などによって最適なアプローチは異なります。この記事では、「レガシーマイグレーション完全ガイド」というテーマで、レガシーシステムの課題を解決するための手法やポイント、事例などを網羅的にご紹介します。
物流現場では慢性的な労働力不足が深刻化しており、物流ロボットはこうした課題に対応する有効なソリューションとして大きな注目を集めています。しかし、物流ロボットの機能や種類は多岐にわたるので、「何から取り入れるべきか分からない」と悩む企業も少なくありません。本記事では、物流ロボットの役割、導入のメリット・デメリット、導入事例についてわかりやすく解説します。物流現場における人員不足やコストの増大、業務効率化をお考えの方はぜひ参考にしてください。
原材料を調達して商品を製造し消費者の手元に届くまでの、物流を含めた一連の流れをサプライチェーンと呼びます。これを効率化し最適に管理するのが、サプライチェーンマネジメント(SCM)です。サプライチェーンマネジメントはクラウドやIoTなどのテクノロジーとの連携が進み、企業の競争力を左右する重要な戦略のひとつとして注目されています。しかし、「どのように取り組めば良いか分からない」と悩む企業も少なくありません。本記事では、サプライチェーンマネジメントの仕組みや必要性、メリット・デメリット、成功のポイントをわかりやすく解説します。
現在、システム開発やサイト制作などのものづくりにおいて、ユーザー起点で使いやすさを考えることが求められています。
ただイケてるもの、かっこいいものを作ったとしても、使いやすさがなければユーザーはついてきません。そのためにまずやるべきこととして重要視されているのが「ユーザビリティテスト」です。本記事では、ユーザビリティテストとは何か、その種類や評価項目、やり方について説明します。
物流DXとはデジタル技術を活用して物流業界のビジネスプロセスやサービスを革新する取り組みです。近年、物流業界には人手不足や環境問題、小口配送の増加、システムの老朽化などさまざまな課題を抱えており、これらの問題を解決する手段としても注目されています。しかし、物流DXの種類は幅広いため「何から始めたらいいか分からない」「取り組み方が分からない」と迷う企業は少なくありません。本記事では、物流DXの市場動向や、物流業界の課題解決に役立つ導入事例を中心に解説します。