近年、デザインの現場において「デザインシステム」という言葉を聞く機会が増えました。
デザインシステムは、企業が提供するWebサイトやアプリのデザインを統一し、品質と効率を高めるための指針です。
ブランディングの観点だけでなく、効率化や品質担保の観点からもデザインシステムの構築と適用が有効です。
本記事では、デザインシステムの基本から導入メリット、具体的な作り方、活用ツール、事例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
Contents
デザインシステムとは何か
まずは、初めてデザインシステムという言葉を聞いた方にもわかりやすく概要をご紹介します。
デザインシステムの定義
デザインシステムという言葉に明確な定義があるわけではありませんが、デジタル庁の解説が一つの参考となります。
デザインシステムとは「WebサイトやWebアプリケーションを作る際に参照するルールのまとまり」のことです。
※出典:デジタル庁「デザインシステムβ版」
デザインシステムは、企業や組織が提供するアプリやWebサイト、プロダクトにおいて、デザインの一貫性と再現性を保つためのルールとなります。
例えば、Googleが提供するサービスであれば、Google検索だけでなくGoogle DocsやGoogle Maps、Gmailなど、あらゆるサービスにおいて「Googleらしさ」を感じ取れるのではないでしょうか?
このように、デザインシステムに基づくアプリやWebサイト、プロダクトは、共通のブランドイメージやユーザー体験を提供できます。
こうした一貫性を保つために、デザインシステムでは色やフォントなどの視覚的な要素に加え、それらを決定するための前提となる、自社やプロダクトのブランドイメージや設計思想も含めて共通のルールとして定義します。
関連記事:なぜ今、アジャイル開発×デザイン思考が新規事業開発に必要なのか
スタイルガイドとデザインシステムの違い
デザインの一貫性を保つために作成されるものとして「スタイルガイド」という概念があります。スタイルガイドとは、ブランドやプロダクトのデザインにおいて、色やフォント、ロゴなどの使用方法を定め、統一感のあるビジュアル表現を実現するためのルール集です。
一見、両者は似た概念に思えますが、デザインシステムはスタイルガイドを含むより広い概念です。
スタイルガイドが「見た目の統一」に焦点を当てるのに対し、デザインシステムはブランド価値やユーザー体験を支える設計思想、運用ルールまでを含みます。
デザインシステムの構成要素
デザインシステムは、設計思想や価値観を示す「デザイン原則」と、視覚的なルールを定めた「スタイルガイド」、これらに基づき作成された再利用可能な「コンポーネントライブラリ」の要素から構成されます。
デザイン原則
デザイン原則は、プロダクト全体の設計思想や価値観を示す指針です。単なる見た目のルールではなく、ユーザー体験やブランドの理念を方向づけます。
例えばデジタル庁のデザインガイドでは、その公共性の高さから「アクセシビリティファースト」「汎用性と利便性」を重要視しています※1。このほかにも、自動車メーカーであるポルシェでは「高品質で視覚的に美しいデザイン」を重視し、同社の品質と理念を体現しています。
これらの原則は、デザイナーや開発者が日々の判断に迷ったときの拠り所となり、自社のWebサイトやプロダクトの方向性をぶらさないための土台となります。
※1参考:デジタル庁「デジタル庁デザインシステムの特徴」
※2参考:Porsche「Welcome to the Porsche Design System」
スタイルガイド
スタイルガイドは、ブランドカラー、フォント、アイコン、余白の使い方など、視覚的な要素のルールを体系的にまとめた資料です。
デザイン原則に基づき作成されたスタイルガイドにより、複数のデザイナーが関与しても、統一感のあるデザインが保たれます。
スタイルガイドは、印刷物やWebサイト、アプリなど、あらゆる媒体でブランドイメージを統一し、ブランド価値を損なわないための指針です。
外部パートナーや委託先と連携してコンテンツを作成する際にも、スタイルガイドの共有により品質のばらつきを防ぐことができます。
コンポーネントライブラリ
コンポーネントライブラリは、ボタンやフォーム、ナビゲーション、カードなどのUI部品を再利用可能な形でまとめたものです。コンポーネントライブラリは、スタイルガイドを基盤として作成されます。
各コンポーネントは、デザイン上だけでなく、コーディングにおいても共通で利用できるようにします。デザイナーとエンジニアでコンポーネントを共通化することで、デザイナーと開発者の連携をスムーズにし、デザインから流れるように実装を行うことができます。
また、アクセシビリティ対応やレスポンシブ対応といった要件に準拠したコンポーネントライブラリを用意することも重要です。ルールとして定めただけでは適用漏れが起きる可能性があります。
あらかじめコンポーネントライブラリを用意しておくことで、品質向上にも寄与します。
関連記事:エンジニアとデザイナーによるペアデザインを用いたWeb開発とは。流れやメリットを大公開
デザインシステムの作成メリット
デザインシステムの作成には、デザインの一貫性確保だけでなく、効率性や品質の向上といったメリットがあります。
デザインの一貫性確保
デザインシステムを作成する最大のメリットは、プロダクト全体におけるデザインの一貫性を保てる点だといえるでしょう。
自社が提供する複数のWebサイトやサービスを横断しても、色使いやフォント、UIコンポーネントの配置などが統一されていれば、ユーザーは違和感を持つことなく操作できます。
例えば、ある企業のサービスAとサービスBでボタンの形状や動作が異なっていた場合、ユーザーの混乱につながります。デザインシステムによりこうしたばらつきを防ぎ、ユーザー体験を高められます。
デザイン効率の向上
デザインシステムによって用意された再利用可能なコンポーネントにより、デザイナーの作業効率も高まります。毎回ゼロからデザインを作成する必要がなく、既存のコンポーネントを活用して設計を進められます。また、開発者にとってもコード化されたコンポーネントがあれば、実装の手間も減らせます。
さらに、レビューやテストの工程でも、共通の基準があることで、全体の作業効率が向上します。
デザインの品質向上
品質向上もまた、デザインシステムを作成する効果の一つです。
デザインシステムには、自社の品質基準を満たしたコンポーネントが含まれています。
これらを活用することで、デザイナーやエンジニアの経験値や作業レベルに関係なく、高品質なUI/UXを提供できます。
また、ルールに基づいたデザインが行われるため、個々のスキルによる品質のばらつきも抑えられます。
特に複数のチームが関与する大規模プロジェクトや、共通のブランドで複数のプロダクト・サービスを提供するケースにおいては、デザインシステムによる品質向上のメリットは大きいといえるでしょう。
デザインシステムの作り方

デザインシステムを作る上では、原則やスタイルガイド、コンポーネントライブラリの構築といった要素に加えて、社内への浸透による実効性の確保まで行うことが重要です。
1 デザイン原則の定義
デザインシステムの構築は、まず組織としての「デザイン原則」を明文化することから始まります。デザイン原則は、プロダクトやブランドの価値を反映したものとすべきです。
例えば、「ユーザーの年齢や性別を問わず誰にでも使いやすい」「情報を簡潔に伝えられるシンプルさ」など、自社やプロダクトのコンセプトに準拠した形で、デザインの方向性を定めます。
2 スタイルガイドの整備
次に、色、フォント、余白、アイコンなどの視覚的要素を体系化したスタイルガイドを作成します。
自社に既存のブランドガイドラインがある場合は、それをベースに整備するとブランドイメージの一貫性を確保できます。
スタイルガイドは、自社のデザイナーが日々の制作で参照するだけでなく、外部パートナーとの連携にも活用されるものです。
Web形式など、共有可能な形にしておくと運用がスムーズになります。また、一般向けに外部公開することで信頼性や透明性の確保にもつながります。
3 コンポーネントライブラリの構築
ボタンやフォーム、ナビゲーションなどのコンポーネントを整理し、再利用可能な形でライブラリ化します。
流れとしては、まずデザイナーがFigmaやAdobe XDなどのデザインツール上で定義したうえで、エンジニアが実装のためのコードを作成します。
コンポーネントライブラリの構築に当たっては、階層分けや上下関係を意識します。「画面全体に影響を与える要素」「複数のコンポーネントを組み合わせて利用する要素」「ボタンやアイコンなど最小の要素」といったように階層を分けて整理することで、利用しやすいものとなります。
4 テンプレート定義
利用頻度が高いデザインについては、テンプレート化することも有効です。よく利用するページの構成やコンポーネントの配置をテンプレートとして定義することで、Webサイトやプロダクトによらず構造を統一できます。
例えば「トップページ」「一覧ページ」「詳細ページ」など、よく使われる画面パターンをテンプレート化しておけば、新規ページのデザインも効率化できます。
5 ガイドライン化
ここまで整理してきた各要素をガイドラインとしてまとめます。
ガイドライン化においては、デザインシステムの運用ルールや更新手順を合わせて整理するとよいでしょう。
誰がどのようにコンポーネントを追加・変更するのか、承認フローはどうするのかなどを明確にすることで、継続的な運用がしやすくなります。
整備したガイドラインは関係者がいつでも参照できるように、社内ポータルなどに掲示しておくことが推奨されます。
6 社内への浸透
最後に、デザインシステムを効果的に運用するには、社内全体への浸透が欠かせません。どれほど完成度の高いシステムでも、認知されていなければ意味がありません。
デザインシステムを浸透を促すために、関係者への説明会や勉強会、研修を実施し、実際の業務で活用できる環境を整えます。
これらの取り組みにおいては、実際にデザインシステムを利用するデザイナーやエンジニアからフィードバックを受けることも重要です。
利用者の声を反映しながら改善を続けることでデザインシステムを「一部のチームのツール」ではなく、より使いやすく、効率のよいデザインシステムにアップデートしていきます。
そうすると、デザインシステムは全社の共通資産として運用できるようになります。
デザインシステムに用いられるツール
以下では、デザインシステムの構築・運用に用いられる代表的なツールをご紹介します。
設計・プロトタイピングに利用できるFigmaやAdobe XD、ドキュメント共有向けのZeroheight、開発連携に利用できるSupernovaなど、デザインシステムの構築・運用においては、これらのツールを併用することがポイントです。
Figma
FigmaはクラウドベースのUIデザインツールです。複数人によるリアルタイム編集が可能であり、ブラウザ上で動作するため環境依存が少なく、社内外のメンバーとの共同作業にも適しています。
Figmaはコンポーネントの再利用やバージョン管理、プロトタイプ作成などの機能が充実しており、デザインシステムの構築においてよく利用されています。
複雑なUI設計にも対応できるため、大企業や大規模プロジェクトにおいてデザインシステムを構築に適したツールです。
Adobe XD
Adobe XDは、Adobe製品群との連携に強みを持つデザインツールです。
IllustratorやPhotoshopで作成した素材をスムーズに取り込めるため、既存のブランド資産を活用しやすい点が特徴といえます。
プロトタイピング機能やアニメーションの設定も可能であり、ユーザー体験の検証に役立ちます。Figmaと比べると柔軟性や機能性はやや劣りますが、Adobe環境に慣れたチームにとっては導入しやすい選択肢といえるでしょう。
Zeroheight
Zeroheightは、デザインシステムのドキュメント化に特化したツールです。
Figmaなどのデザインツールと連携し、スタイルガイドやコンポーネント情報をWeb上で共有できます。ノーコードで編集可能なインターフェースを備えており、デザイナーだけでなく非技術者でも扱いやすい点が魅力です。
デザインルールや運用方針を社内外の関係者にわかりやすく共有するためのプラットフォームとして活用されています。
Supernova
Supernovaは、デザイン資産をコードに変換するプロセスを支援するツールです。Figmaなどで定義されたコンポーネントをReactやFlutterなどの開発環境に取り込む際の橋渡しとして機能します。
Supernovaを利用することで、デザインと実装の乖離を防ぎ、開発効率を高めることができます。コンポーネントの品質を保ったままコードベースに反映できる点が、Supernovaを利用するメリットです。
デザインシステムの事例
ここでは、代表的なデザインシステムの事例として「Google」「デジタル庁」「2025年大阪・関西万博」の取り組みを取り上げます。
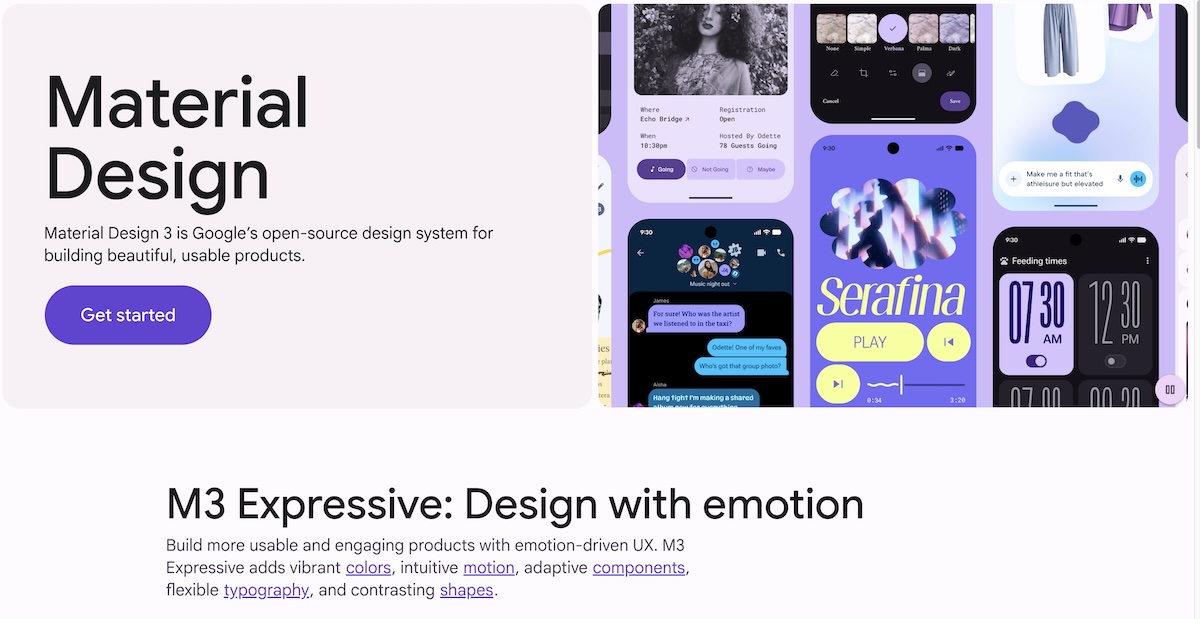
Googleが展開する「Material Design」は、世界的に広く採用されているデザインシステムの代表例です。
色彩、動き、レイアウト、タイポグラフィなどのルールが体系的に整理されており、Androidアプリや同社のWebサービスにおいて一貫性のあるユーザー体験を提供しています。
特に、影や奥行きの表現を用いた「マテリアル感」のあるUI設計が特徴で、視覚的な階層構造が明確化されており、ユーザーの操作性を高めています。
また、Material Designは開発者向けにコンポーネントのコードも公開されており、設計から実装までを支援する仕組みが整っています。
Material Designは、Google製品以外でも広く利用されており、多くのWebサイトやアプリなどでも利用されています。
※参考3:Google「Material Design」
デジタル庁

引用:デジタル庁
日本のデジタル庁では、行政サービスの利便性と統一感を高めるためにデザインシステムを公開しています。
このデザインシステムは、アクセシビリティや多言語対応が重視されており、誰もが使いやすい行政サービスの提供を目指しています。
色のコントラストやフォントサイズ、操作のわかりやすさなど、ユニバーサルデザインの観点から細部まで配慮されている点が特徴です。
さらに、自治体や外部ベンダーが活用できるよう、スタイルガイドやUIコンポーネントをWeb上で公開し、全国で統一されたデザインの実装を支援しています。
※参考4:デジタル庁「デザインシステム」
2025年大阪・関西万博

引用:EXPO2025
2025年4月13日〜10月13日に開催された大阪・関西万博では、公式サイトや関連アプリにおいて統一されたデザインシステムが導入されています。
万博のデザインシステムは、「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現するために、動的な要素のある構造となっています。
同デザインシステムの特徴として「アナログ・デジタルの境界線を超えて一貫した体験を提供する」という点が挙げられます。
このコンセプトに基づき、実際の万博でもWeb上でのアカウント作成や事前予約から、実際の現場での体験、さらにグッズまでも、一貫したデザインとユーザー体験が提供されています。
また、アクセシビリティやモバイル対応にも配慮されており、国内外の幅広いユーザーに対応した設計が実現されている点も特徴の一つです。
デザインシステムの導入により、情報の構造や操作性が統一され、訪問者が言語や文化の違いを超えてスムーズに情報にアクセスできるよう工夫されています。
※参考5:EXPO2025 「Design System」
スパイスファクトリーにおけるデザインシステム導入事例
スパイスファクトリーでは、デザイン制作の属人化やルール未整備、理解のばらつきなどの課題を背景に、チーム全体が同じ品質で効率よくデザインシステムを構築できる「デザインシステムテンプレート」を開発しました。
Figmaを中心に運用できるこのテンプレートは、導入ガイドの「Guide」、基礎設計の「Foundations」、色・影・余白などのスタイル定義「Design Token」、そして実装コンポーネントをまとめた「Components」で構成され、誰でもすぐに実践できる仕組みです。
チーム全員がすぐに活用できるようesa上で使い方とURLを整理し、テンプレートを開けばすぐに作業を始められる導線も整備しています。これにより、チームメンバーは学びながらデザインシステムを活用でき、制作のスピードと品質が飛躍的に向上しました。
実運用を通じて継続的にアップデートを行っており、2025年6月にはVariablesやStyles、アイコンキットの追加や、カラーや余白の名称整理、スタイル指定の変数化などを実施し、より柔軟で再利用しやすい環境へと進化させています。
今後はFigma MCP連携によるトンマナを崩さないプロトタイプ生成や、チェックリスト連携による運用ルールの体系化を進め、「誰でも・すぐに・高品質に」デザインシステムを運用できる文化を育てていきます。
テンプレートは単なる設計ツールではなく、チーム全員が共通のデザイン言語で協働し、創造力を最大化できる学べる仕組みとして機能しています。
まとめ
今回は、デザインシステムについて詳しく解説しました。
デザインシステムを構築し、自社のWebサイトやプロダクトにおけるデザインを一貫したものとすることで、ブランドイメージの向上や作業効率の向上、品質の担保など様々なメリットを得られます。
一方で、自社だけでデザインシステムを完成させることは簡単ではありません。
デザインシステムに興味があるものの、作成方法に悩まれている企業は、ぜひ当社スパイスファクトリーにご相談ください。
当社では、これまで多くの企業をUI/UXの強みを活かしてサポートしてきました。
UI/UXに精通したプロフェッショナルだけでなく、技術力のあるエンジニアも多数在籍しており、デザインからコーディングまですべてのプロセスを支援します。
ご興味のある方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

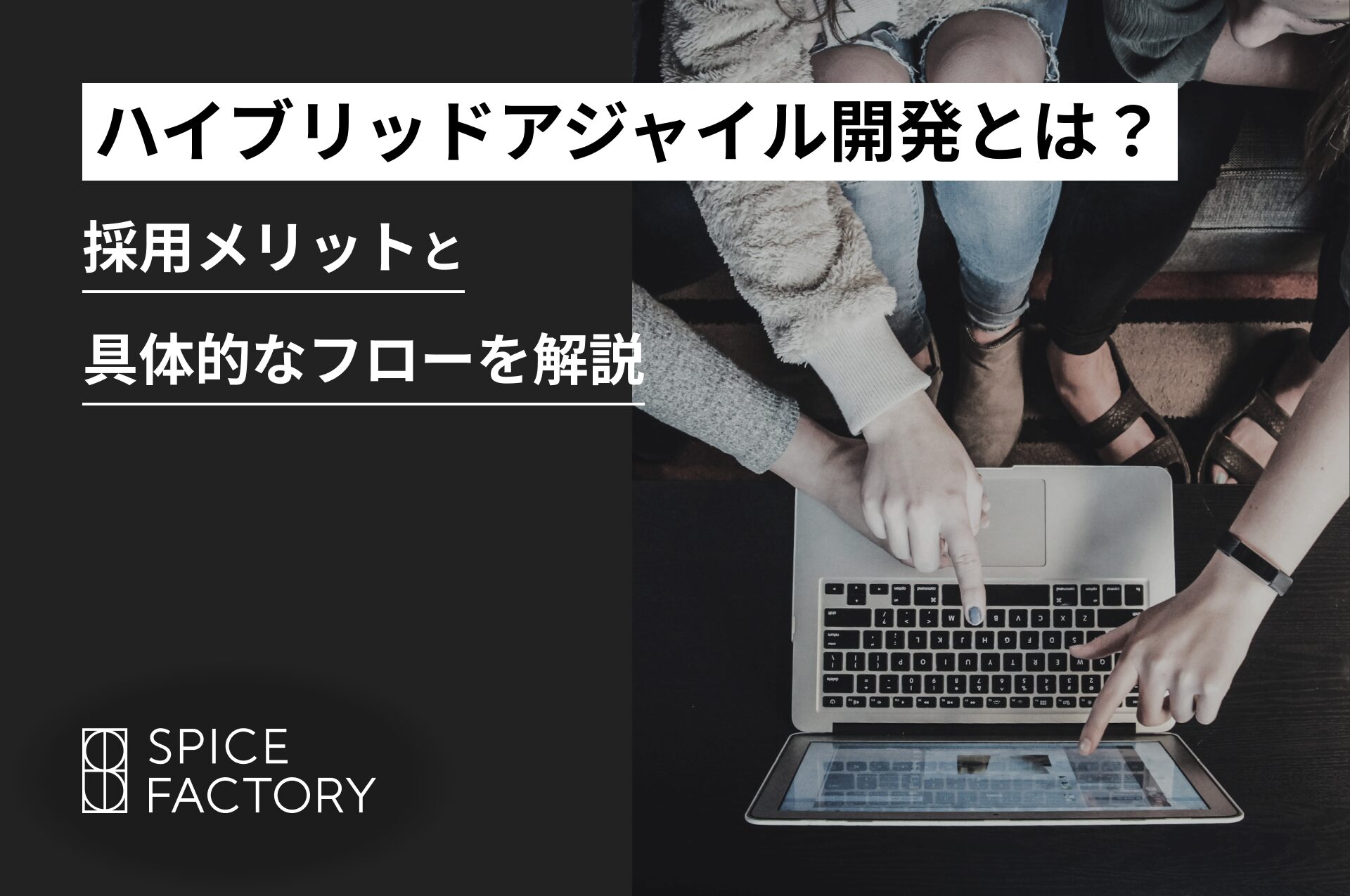
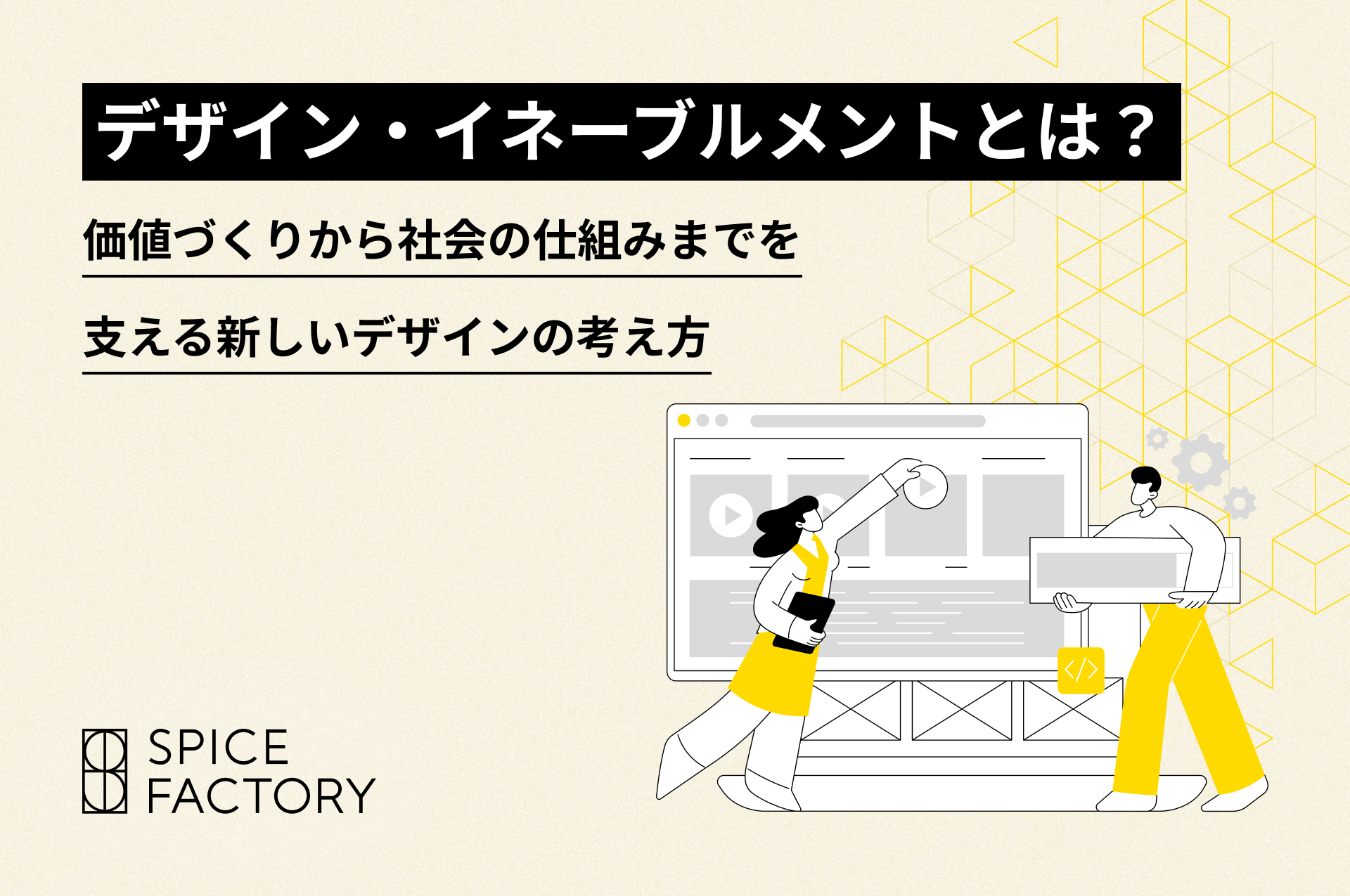

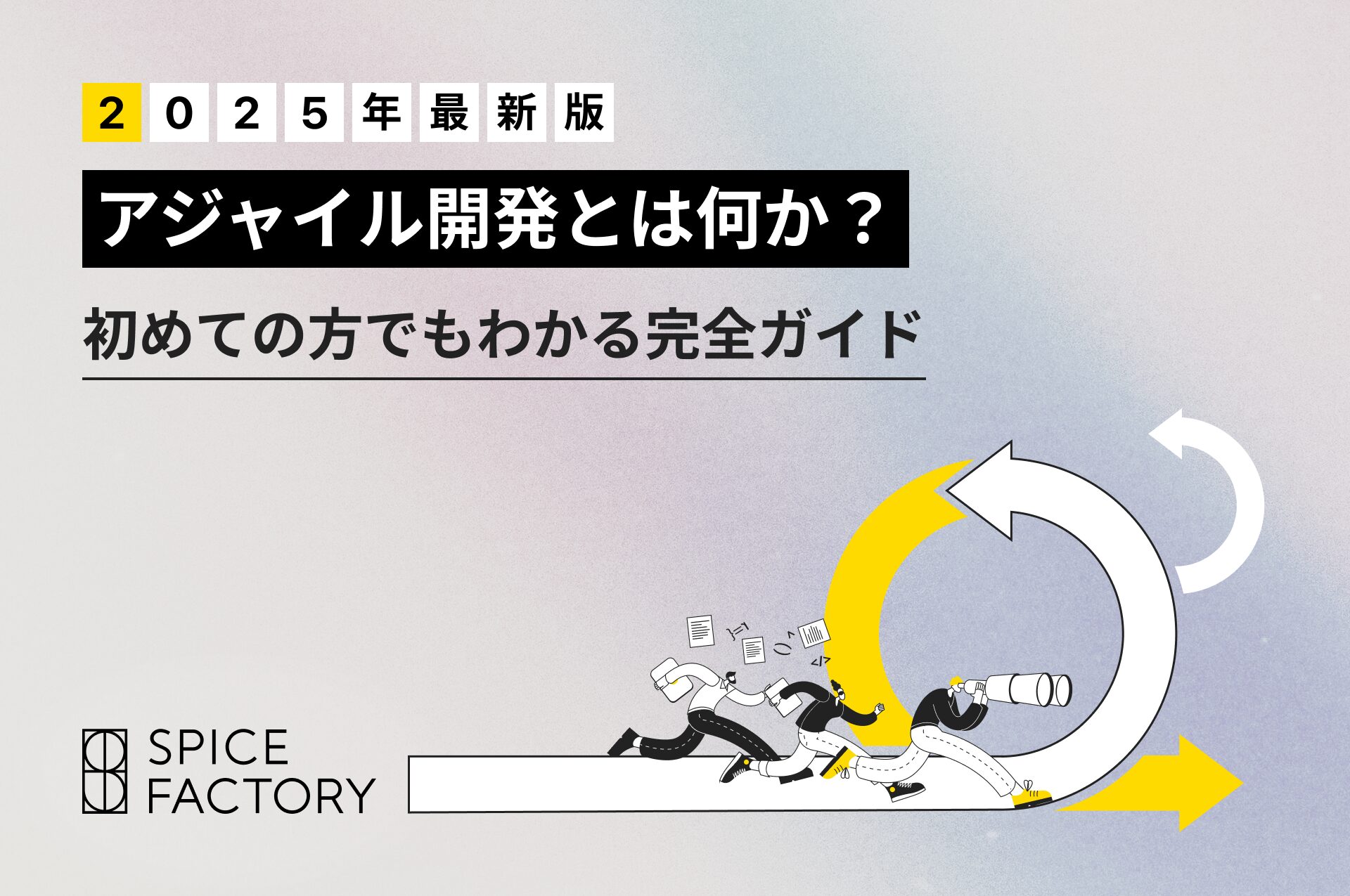


About The Author
スパイスファクトリー公式
スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。