「オンプレミスのままで、本当に大丈夫なのか」と、不安を感じている担当者の方もいるでしょう。
近年、多くの企業がクラウドを活用し、ITインフラの効率化を進めています。しかし、オンプレミスにも依然として強みがあるため、クラウド移行に踏み切れない企業も少なくありません。
本記事では、オンプレミスとクラウドの違いや費用の比較、メリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、「オンプレミスが向いているケース」「クラウドが向いているケース」についても紹介しますので、参考にしてください。
Contents
オンプレミスとは
オンプレミスとは、企業が自社内にITインフラを構築し、システムを運用・管理する形態です。サーバーやネットワーク機器などのハードウェアだけでなく、業務アプリケーションやデータも自社で管理します。
運用や管理は社内のシステム部門やエンジニアが担当するのが一般的です。外部のクラウドサービスに依存せず社内ネットワークを活用できるため、インターネット環境がなくてもシステムを利用できます。
クラウドが普及するまでは、オンプレミスが企業のITインフラの標準的な形でした。
オンプレミスは時代遅れなのか?
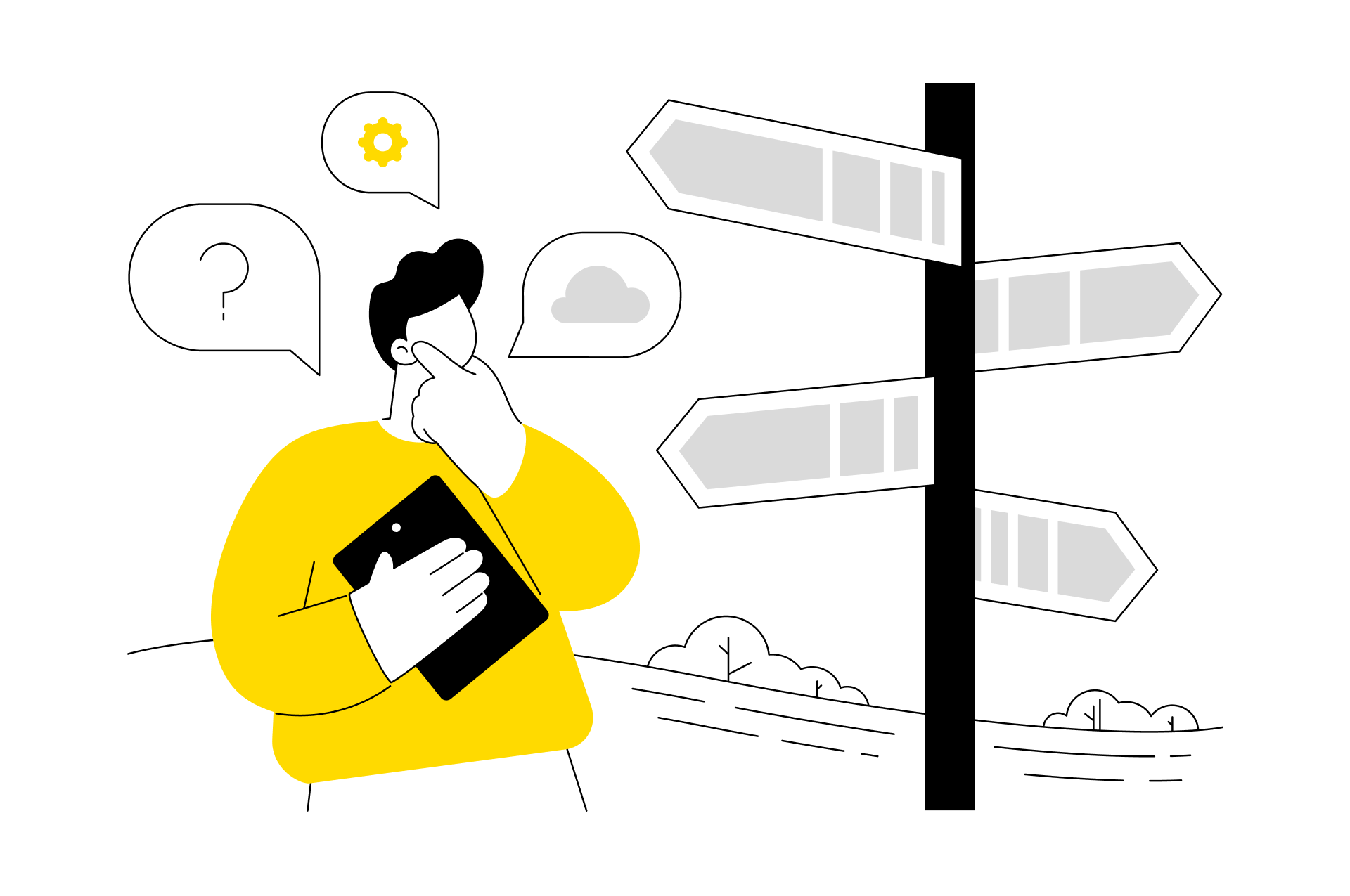
総務省の調査によると、日本における企業のクラウドサービスの利用率は2023年時点で77.7%です。
そのなかで、クラウドとの比較もせず古いレガシーシステムのオンプレミスを使い続けている企業は、技術的な制約やコストの増大が問題視され「時代遅れ」とみなされることもあるでしょう。
一方、高度なセキュリティ要件が求められる政府機関や金融機関やリアルタイム制御が必要な製造業loTシステムなどでは、最新技術を活用しながらオンプレミスを活用しています。また、クラウドとオンプレミスを組み合わせた「ハイブリッドクラウド」を採用する企業もあります。
そのため、オンプレミスだけを理由に「時代遅れ」と言い切ることはできません。
2026年問題について
ガートナージャパンは、2026年にはクラウド導入の遅れが企業の競争力に大きな影響を与えると指摘しています。
「2026年問題」として挙げた、6つの課題は次のとおりです。
- クラウドはまだ早いと考え導入を見送っている(30%)
- 「2025年の壁」を乗り越えられず、2030年までレガシーシステムを継続する懸念
- オンプレミス対クラウドの議論を続け、採用に至らない(40%)
- ベンダーへの丸投げから脱却できない(30%)
- クラウド化してもコスト削減できない(40%)
- SI(システムイングレーション)・仮想ホスティングとクラウドの違いが分からない(30%)
2026年問題を乗り越えるには、単にクラウドへ移行するだけでなく、IT戦略の見直しや社内の理解促進が不可欠です。
クラウドとは
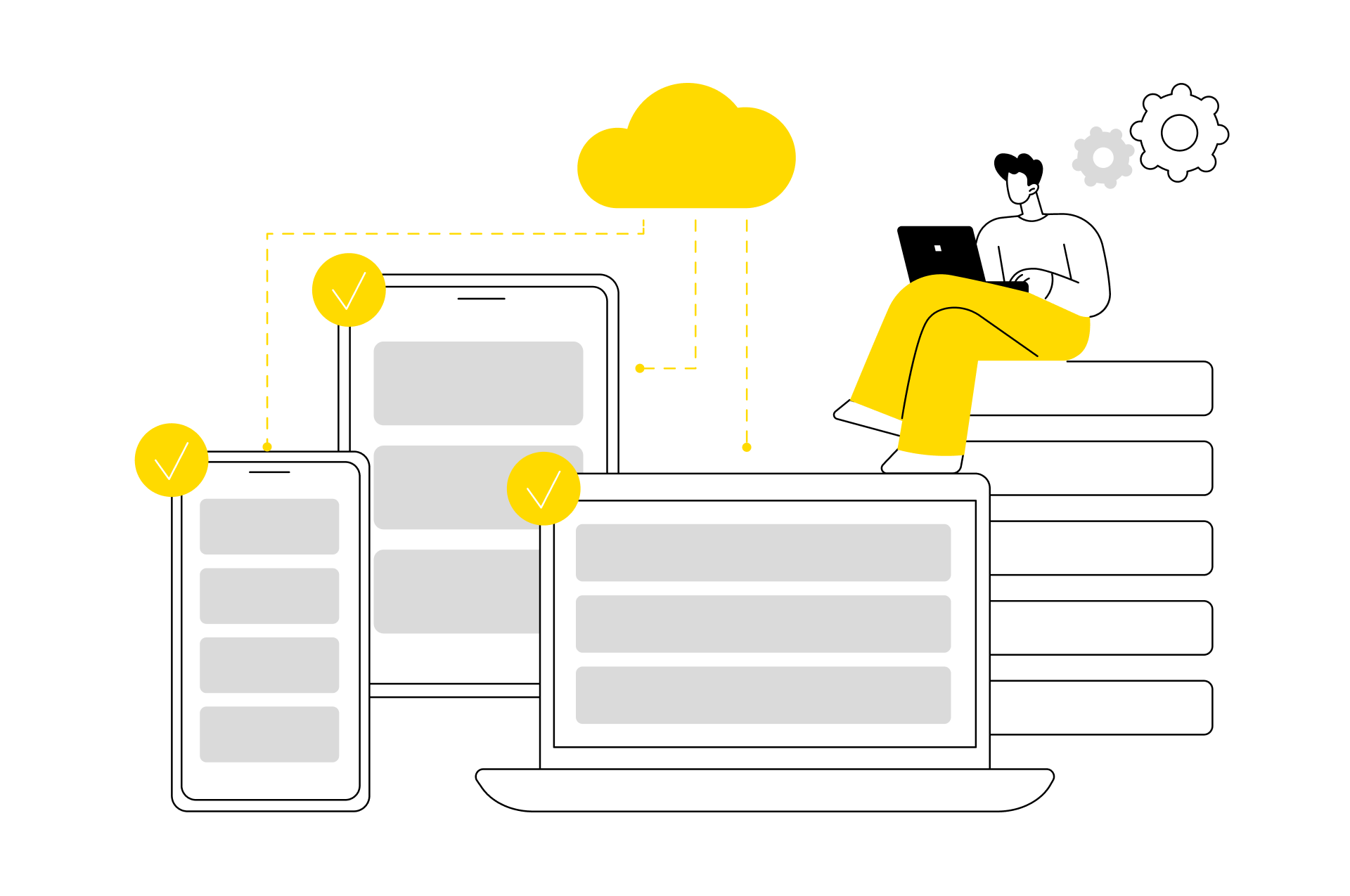
クラウドとは、インターネットを経由してサーバーやメモリ、データベース、ソフトウェアなど幅広いサービスを利用できる仕組みです。企業が自社でサーバーやハードウェアを準備することなく、クラウドサービスを契約するだけで利用できます。
クラウドサービスは主に、次の3種類です。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| IaaS | サーバーやメモリなど、ハードウェア部分をオンラインで提供するサービス |
| PaaS | データベース、プログラム環境など、アプリ開発のできるプラットフォーム機能を提供するサービス |
| SaaS | メールやチャットツール、会計ソフト、営業ソフトなど、クラウド上で使えるアプリケーション機能を提供するサービス |
機器の導入が不要なので、クラウドを利用すれば初期コストを抑えられます。サービスを契約するだけで運用を始められるため、すぐに導入できる手軽さも魅力です。
ハイブリッドクラウドとは
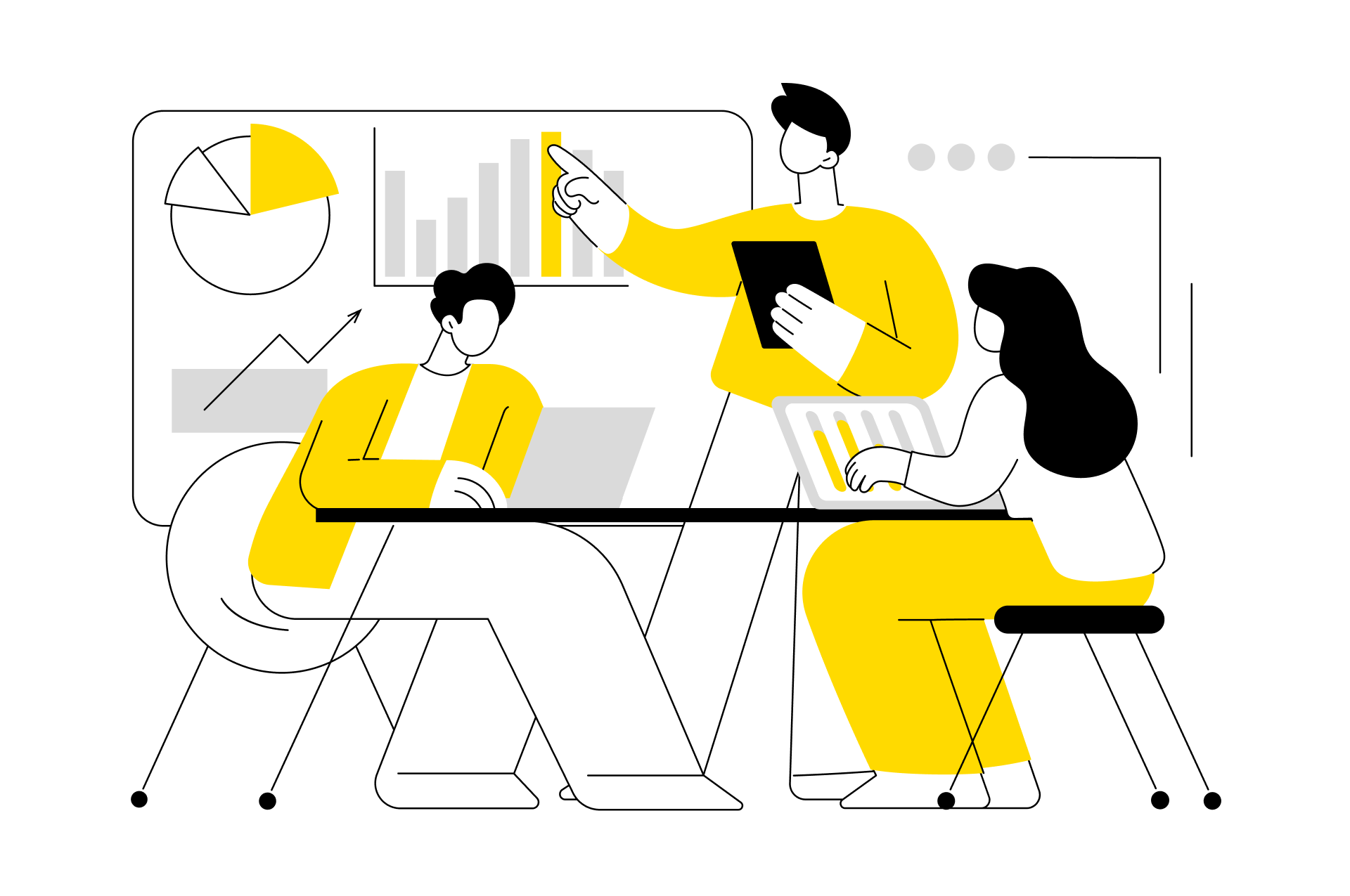
ハイブリッドクラウドとは、オンプレミスとクラウドを組み合わせた運用方法です。
既存のオンプレミス環境を活かしつつ、クラウドの利便性を取り入れられます。たとえば、機密データや基幹システムはオンプレミスで管理し業務アプリやファイル共有はクラウドで運用する、といった使い分けが可能になります。
オンプレミスとクラウドの両方を運用することで双方の強みを活かし、弱みをカバーできます。複数運用になるため、リスクを分散できることもメリットの一つです。
オンプレミスとクラウドの違い
オンプレミスとクラウドの違いを5つの観点で比較します。
項目オンプレミスクラウド
| 項目 | オンプレミス | クラウド |
|---|---|---|
| コスト |
|
|
| セキュリティ |
|
|
| 構築スピード |
|
|
| 災害・障害時 |
|
|
| カスタマイズ性 |
|
|
オンプレミスはカスタマイズ性やセキュリティの高さが強みです。一方、クラウドは初期コストが低く、導入しやすい点で優れています。
オンプレミスとクラウドの費用比較
オンプレミスはハードウェアやOSなどの機器や設備をそろえ、社内で運用管理しなければなりません。
導入時には、ハードウェアやソフトウェアライセンスの購入も必要で、大きなコストがかかります。社内に専用の管理部門やエンジニアを確保するため、人件費も発生します。
一方、クラウドは物理機器を用意する必要がなく、初期投資を抑えられるのが利点です。月々の支払いは、利用量に応じて変動する従量課金制が一般的です。
オンプレミスの導入費用相場
オンプレミスの導入時には、サーバー本体、ストレージ、ネットワーク機器などのハードウェアと、OSやデータベース等のソフトライセンスの購入が必要です。
標準的なサーバー代としては、50万〜300万円程度が目安です。高性能のサーバーは500万円以上が相場で、1,000万円以上かかるものもあります。
さらに、機器設置や環境構築に必要な工事費・設定費・人件費も初期投資として必要です。合計すると、導入費用の相場は数百万円かかります。システムの種類や規模によっては1,000万円以上になることもあります。
クラウドシステムの導入費用相場
クラウドシステムの導入費用は基本的に無料です。特にSaaSを使用する場合は、社内に専門家を雇う必要もなく、契約後すぐに利用を開始できます。そのため、オンプレミスと比べ初期費用を大きく抑えられる点がメリットです。
オンプレミスのメリットデメリット
ITシステムの導入を検討する際は、それぞれの特徴の理解と比較が欠かせません。ここでは、オンプレミスを使用するメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット
オンプレミスのメリットは、カスタマイズの自由度が高くセキュリティ性に優れている点です。自社の要件に合わせたシステム構築が可能で、社内システムとの連携もスムーズです。
外部から独立した環境を構築すれば、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。
さらに、社内ネットワーク内にサーバーを設置するとインターネット接続なしでも運用できるため、通信障害の影響を受けにくいのも利点です。
デメリット
オンプレミスの大きなデメリットは導入コストが高額になる点です。システムを拡張する際も新たな機器の導入やシステムの再構築が必要となり、追加費用がかかります。
管理には、システムの構築・運用・セキュリティ対策を担当できる人材の確保が不可欠です。しかしながら、IT人材の確保や育成には継続的にコストが発生します。
クラウドのような自動復旧機能がないため、災害時に独自の対策が必要になる点もデメリットです。バックアップや遠隔地でのデータ保管など、独自の取り組みが欠かせません。
また、オンプレミスは、システムやネットワーク危機の脆弱性を突かれる攻撃に弱い傾向があります。特に最近の動向としては、VPN機器のみならずメールや偽装サイトから侵入されるランサムウェアの被害が数多く発生している状況です。
一方、クラウドの場合は独立したネットワークで運用しているため、このような攻撃への対策が立てやすくなります。
クラウドのメリットデメリット
クラウドサービスを導入するメリット・デメリットについて解説します。
メリット
クラウドのメリットは、機器購入が不要で初期費用を抑えられる点です。契約後すぐに利用でき、サーバー構築などの手間はありません。
毎月利用した分だけ課金される従量課金制が多く、無駄なコストを抑えられます。さらに、メンテナンスやセキュリティ対策はクラウド事業者が対応するため、自社での管理負担が軽減されます。
社外のサーバーでデータ管理されるため、災害時のリスクが低いのも利点です。
デメリット
提供される機能に依存するため、カスタマイズ性が低い点はデメリットです。自社システムに合うように調整したくても細かい仕様変更が難しい場合があります。
当然のことながらクラウドであるためオフライン環境では使用できません。事業者のメンテナンスや通信障害により、一時的に使えなくなる場合もあります。
外部のクラウド環境にデータを預けるため、情報漏えいや不正アクセスのリスクにも考慮が必要です。リスクを抑えるためには、信頼度の高い事業者選びが重要になります。
オンプレからクラウドへの移行と併用について
企業のIT環境は急速に変化し、クラウドへの移行やハイブリッドクラウドを選択する企業が増えています。
日本でオンプレから移行する企業が増えたのは、災害対策やテレワークの普及が大きく後押ししたためです。
ここでは、オンプレからクラウドに移行・併用する企業が増えた背景について解説します。
オンプレから移行する企業が増えている
総務省の調査によると、企業のクラウドサービスの利用率は、2010年の時点では14.1%と非常に低い水準でした。
転機の一つとなったのが、2011年の東日本大震災です。この震災で、オンプレミスは災害に弱いことが明らかになり、災害対策の一環としてクラウドサービスを検討する企業が増加しました。また、働き方改革や新型コロナウイルスによるテレワーク推奨も、クラウド移行を加速させた一因です。
これらのデジタル環境を取り巻く急激な変化がクラウドへの移行やDX化の推進を推し進め、レガシーシステムの脱却にもつながりました。
このような理由から、オンプレミスからクラウドへと移行する企業は年々増加しているのです。
オンプレミスとクラウドとどっちを選ぶべきか
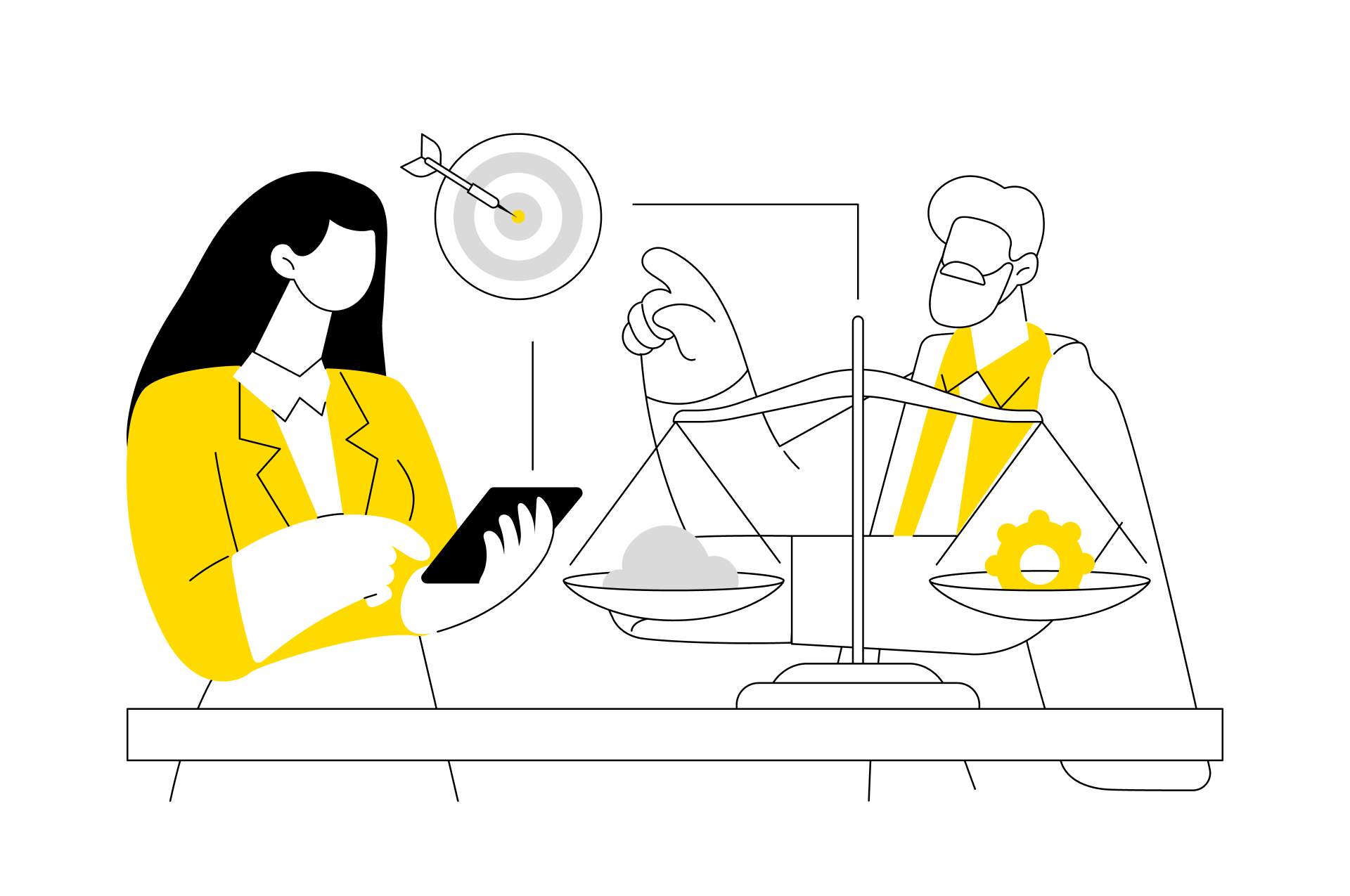
オンプレミスとクラウドには、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがあります。そのため、どちらを選ぶべきか悩む担当者もいるでしょう。
それぞれの特徴を踏まえ、どのような企業に向いているのか詳しく解説します。
オンプレミスが向いているケース
医療機関のように個人情報の保護が求められる企業では、オンプレミスが適しています。たとえば、オンプレミス型電子カルテを導入して院内にサーバーを設置すると、ウイルス感染や個人情報漏えいのリスクを抑えられます。柔軟性が高いため、「診療科別のカスタマイズ」が容易な点も強みです。
IoTシステムや制御システムを扱う製造業のように、リアルタイム処理が必須の場合にも向いています。クラウドはインターネット接続が必要になるため、遅延リスクがあります。
毎月、大容量のデータやストレージを扱うため、クラウドサービスでは運用コストが膨らむ企業にも、オンプレミスがおすすめです。
クラウドが向いているケース
小売業やサービス業のように、需要の変動が大きく、システムの規模を柔軟に調整したい場合はクラウドが向いています。チームで情報を共有しながら業務を進めたい場合にも最適です。日報や顧客情報を簡単に共有できるので、業務効率化につながります。
月額料金のみで利用でき大規模な設備投資が不要なため、初期コストを抑えたいスタートアップ企業や中小企業にも適しています。
リモートワークや外部アクセスが必要な企業にもクラウドはおすすめです。在宅ワークはもちろん、支店や店舗が多数ある場合でも、クラウドを利用すればどこからでも同じ環境で業務を進められます。
ハイブリッドクラウドという選択肢もある
オンプレミスとクラウドの両方を活用する「ハイブリットクラウド」という選択肢もあります。
かつて、金融機関のようにセキュリティ要件と厳格な法令遵守が求められる業界ではオンプレミスを選択するのが一般的でした。しかし、コスト削減や新サービスの導入を目的として、ハイブリッドクラウドを採用する企業も増えています。
オンプレミスのみでは災害発生時にデータ消失リスクが高まります。ハイブリッドクラウドを採用すれば、バックアップやデータ保護を強化できるのも利点です。
ハイブリッドクラウドはコストの最適化を求める企業にも適しています。たとえば、頻繁にアクセスするデータはオンプレミスで管理し、使用頻度の低いデータをクラウドに保存することも可能です。それぞれの強みを生かしてコストを抑えながら柔軟に運用できます。
クラウドの種類
世界のシェア率トップを占めるクラウドは次の3つです。
| クラウド | 概要 |
|---|---|
| AWS(Amazon Web Services) |
|
| Microsoft Azure |
|
| Google Cloud Platform(GCP) |
|
どれもセキュリティ性が高く、システムの規模や使用量に応じて柔軟に調整できるため、幅広い業界で活用されています。それぞれの特徴を解説します。
AWS(Amazon Web Service)
AWSはAmazonが提供するクラウドサービスです。サーバーレスの先駆者として、多様なクラウド技術を展開しています。
データ分析、AI、IoT、セキュリティなど、200以上のサービスを提供し、幅広い分野を網羅しています。世界最大のシェアを誇り、業種・業界を問わず幅広いニーズに対応できるのが強みです。
Microsoft Azure
Microsoft AzureはMicrosoftが提供するクラウドサービスです。Microsoft製品との親和性が高く、Office365、Microsoft Teamsなどとシームレスに連携できます。
オンプレミス環境との親和性も高く、Windows Serverを活用したハイブリッドクラウドに適しています。既存のMicrosoft環境を活かしながら、クラウド化を進められるのが特徴です。
Google Cloud Console
Google Cloud ConsoleはGoogleが提供しているGCP(Google Cloud Platform)を管理するツールです。
GCPは150以上のサービスがあり、特にビッグデータ処理や高度なAI活用が求められる分野を中心に広く活用されています。
BigQueryやTensorFlowなど、Googleのサービスと親和性が高くデータ活用に取り組む企業に適しています。
オンプレミスからクラウドに移行した事例
オンプレミスからクラウドに移行すると、どのような効果が得られるのでしょうか。ここでは、実例を紹介します。
佐川ヒューモニー株式会社様
佐川ヒューモニー株式会社では、インターネット電報サービス「VERY CARD」を提供しています。長年オンプレミスで運用していましたが、システムの老朽化・複雑化による運用負担やコストの増大が課題でした。事業拡大を機に、クラウド環境へ移行し、システム基盤を刷新しています。
結果として、運用負担の軽減とコスト削減を実現しています。さらに、画面設計を見直し、直感的に操作できるデザインに改善し、顧客満足度の向上にもつながりました。
まとめ
オンプレミスとクラウドサービスには、それぞれ異なる特徴があります。
費用対効果やセキュリティ、柔軟性を考慮し適切に使い分けることで、業務効率化や顧客満足度の向上が期待できます。また、クラウドの利用はレガシーシステムの課題解決にも有効です。
さらに、クラウドは災害対策や働き方改革の側面からも注目されており、現在では約80%の企業がクラウドやハイブリッドクラウドを採用しています。
「クラウド移行はまだ早い」と決めつけず、メリット・デメリットを比較検討し、自社に最適なIT環境を選択しましょう。
UI/UXを得意領域とするスパイスファクトリーでは、レガシーシステムのリプレイス案件も承っております。要件定義の上流から開発・運用まで支援可能です。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
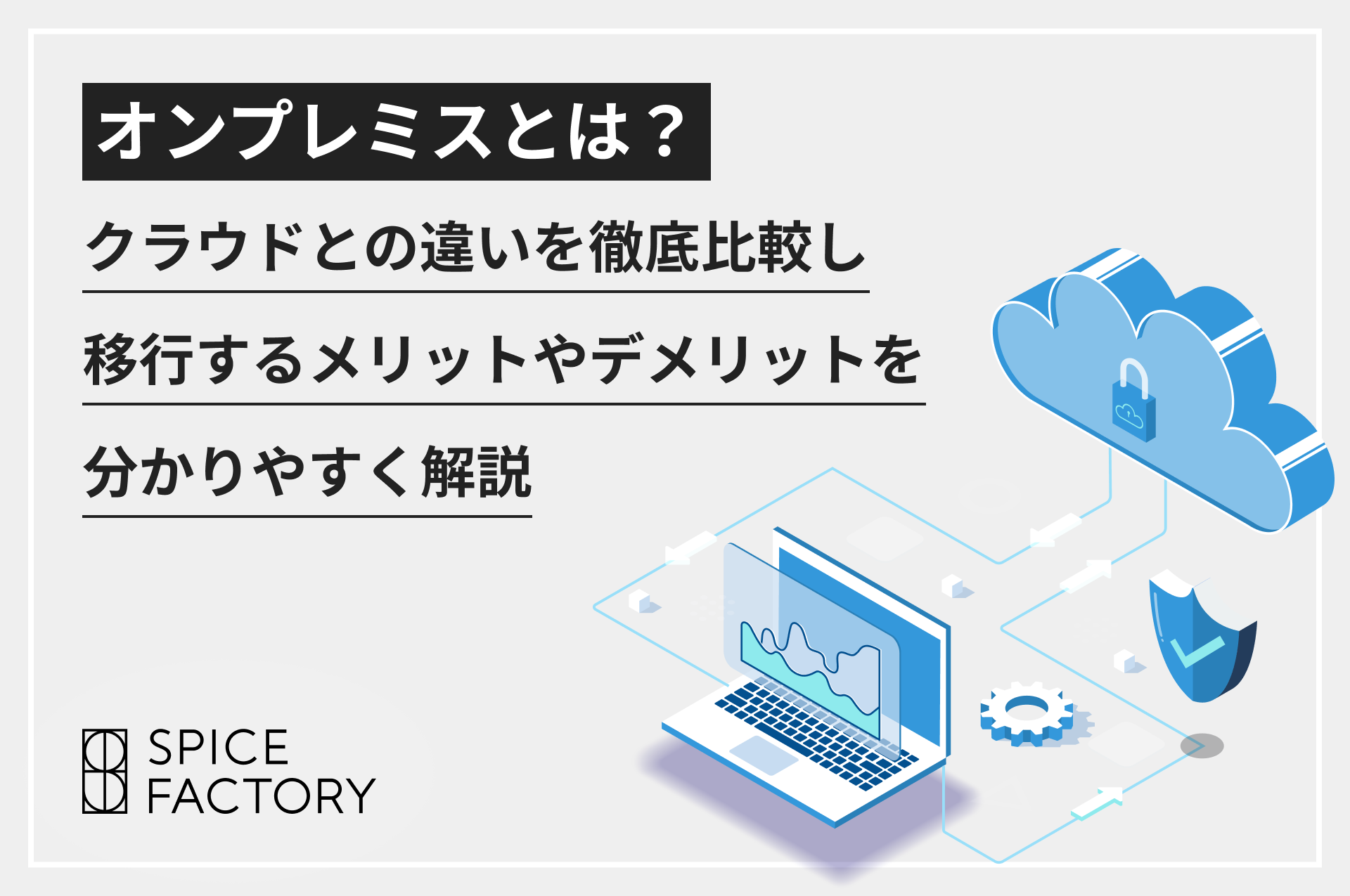
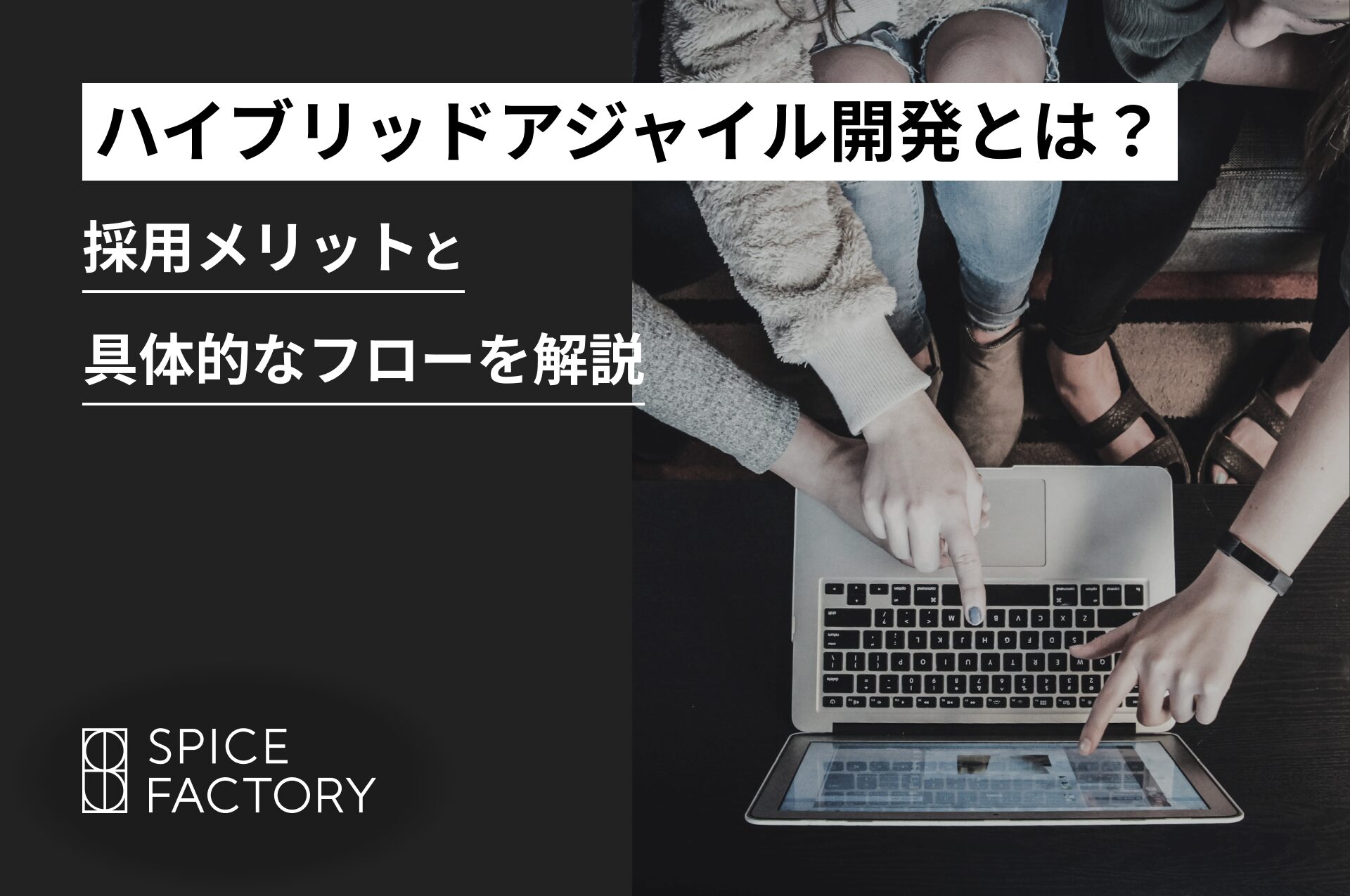
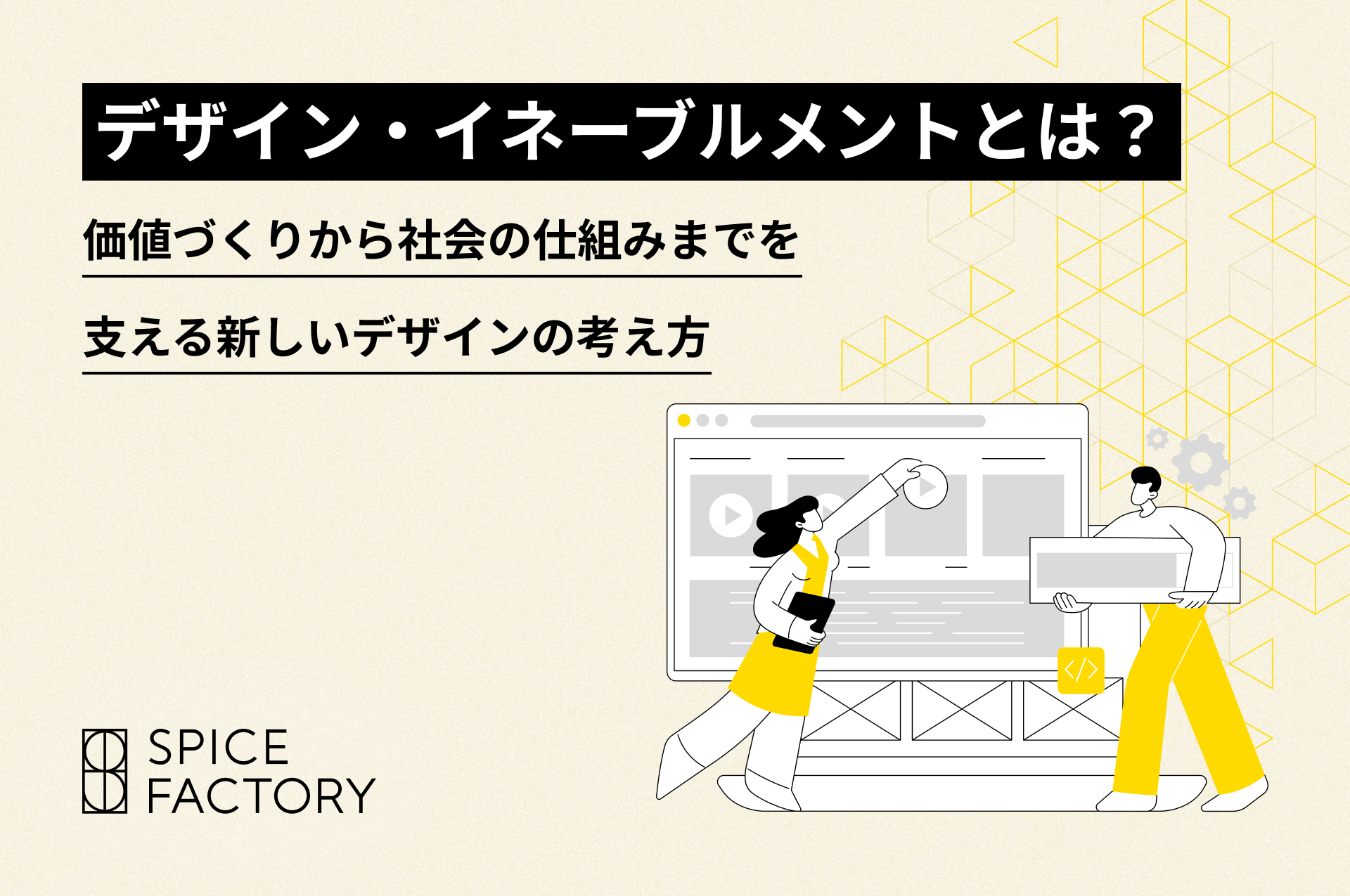

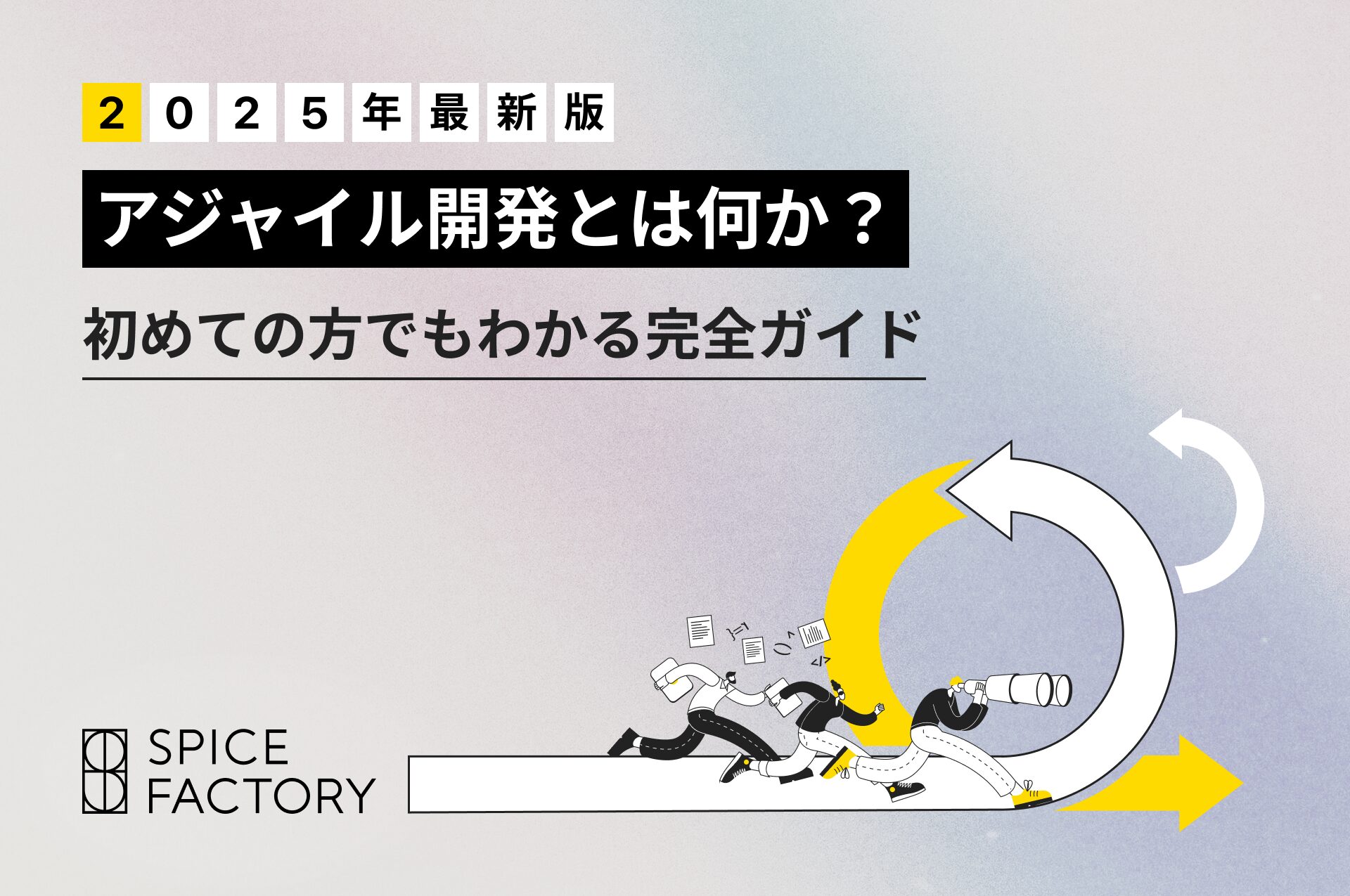


About The Author
スパイスファクトリー公式
スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。