「2025年の崖」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
レガシーシステムは企業の足かせとなり、DX推進や効率的なシステムの運用管理の妨げとなります。レガシーシステムからの脱却が求められますが、一方でその取り組みは決して簡単なものではありません。
今回は、レガシーシステムについて、その概要と課題、脱却のための解決策を詳しくご紹介します。
Contents
レガシーシステムが注目されている背景
なぜ近年、「レガシーシステム」というキーワードが注目されているのでしょうか。
ひとつの契機となったのが、経済産業省が2018年に公表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」です。
このレポートでは「レガシーシステムの存在により企業は最大で12兆円/年の損失が生じる」と警告し、「企業の成長や競争力強化のためにはレガシーシステムから脱却していく取り組みが必要である」としています。
多くのレガシーシステムはブラックボックス化しており、そのメンテナンスコストは高止まりしがちです。また、システムから生み出されるデータも活用しにくい状態となっています。
企業がDXを進め、競争力を強化していく際に、レガシーシステムが障壁となります。レガシーシステムからの脱却が求められているといえるでしょう。
レガシーシステムとは?
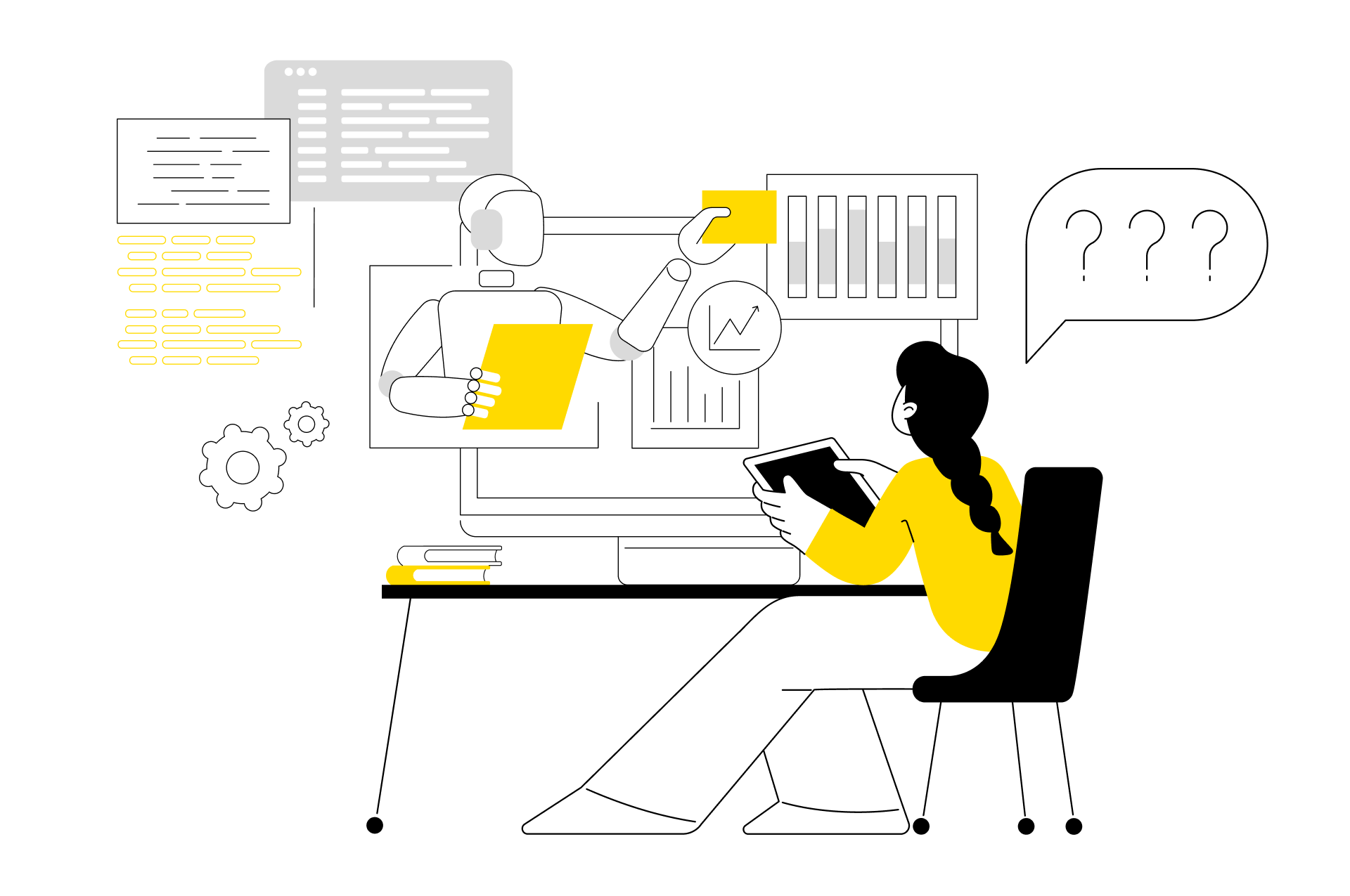
レガシーシステムとは、企業や組織において長期間にわたり使用され続けてきた情報システムやソフトウェアのことを指します。
導入当初は最先端であったシステムも、技術の進化やビジネス環境の変化に伴い時代遅れのものとなってしまいます。
多くの場合、レガシーシステムは自社の業務プロセスに深く結びついており、その置き換えや更新が困難です。また、古い技術が利用されているケースも多く、エンジニアの確保が困難であったり、メンテナンスのコストが高くついてしまったりといった問題もあります。
現代のビジネス環境に合わせたスピード感のある対応や、最新の技術を活用した効率的なシステム活用が求められる中、レガシーシステムの存在は大きな課題となります。
レガシーシステムが生まれる要因
ここでは、レガシーシステムが生まれる要因を以下の観点から解説します。
改修や追加開発による複雑化
企業が利用するシステムは、時間の経過とともに新しい機能の追加や改修が繰り返されていき、システムは複雑化していきます。
すでに利用されていないプログラムや機能がそのままとなっていたり、繰り返し改修を行ったことで無駄の多いプログラムとなっていたりと、初期設計の目的や構造が失われ、パッチワークのような状態になっていることも多いといえます。
開発会社への依存・ブラックボックス化
多くの企業では社内にエンジニアが存在せず、外部の開発会社へと委託を行い、システムの開発や運用を行っています。この状態だと、外部の開発会社に頼りきりとなり、どうしても社内で知識やノウハウが蓄積されていきません。
システム内部の仕組みやプログラムが十分に理解されないまま運用された結果、開発会社の人員入れ替えや事業撤退などをきっかけにメンテナンスやアップデートが困難になってしまいます。
部署ごとの部分最適化
企業内の各部署がそれぞれの要望に基づいてシステムを最適化していくことも、レガシーシステムが生まれる原因となります。
部署ごとに異なる仕様や機能が追加され同じような機能が複数存在してしまったり、処理プロセスが複雑化したりと、全体的な整合性が失われていきます。
人事的な問題
システムに精通した一部の人材に頼ってしまうケースも、レガシーシステムが生まれる原因となります。
システムの運用には長年の経験や専門知識を持つ担当者が必要ではありますが、こうした担当者が退職や異動でいなくなったことをきっかけに、システムの維持や改修が困難になってしまいます。
このようないわゆる「属人化」もまた、レガシーシステム化の原因となります。
レガシーシステムが引き起こす課題
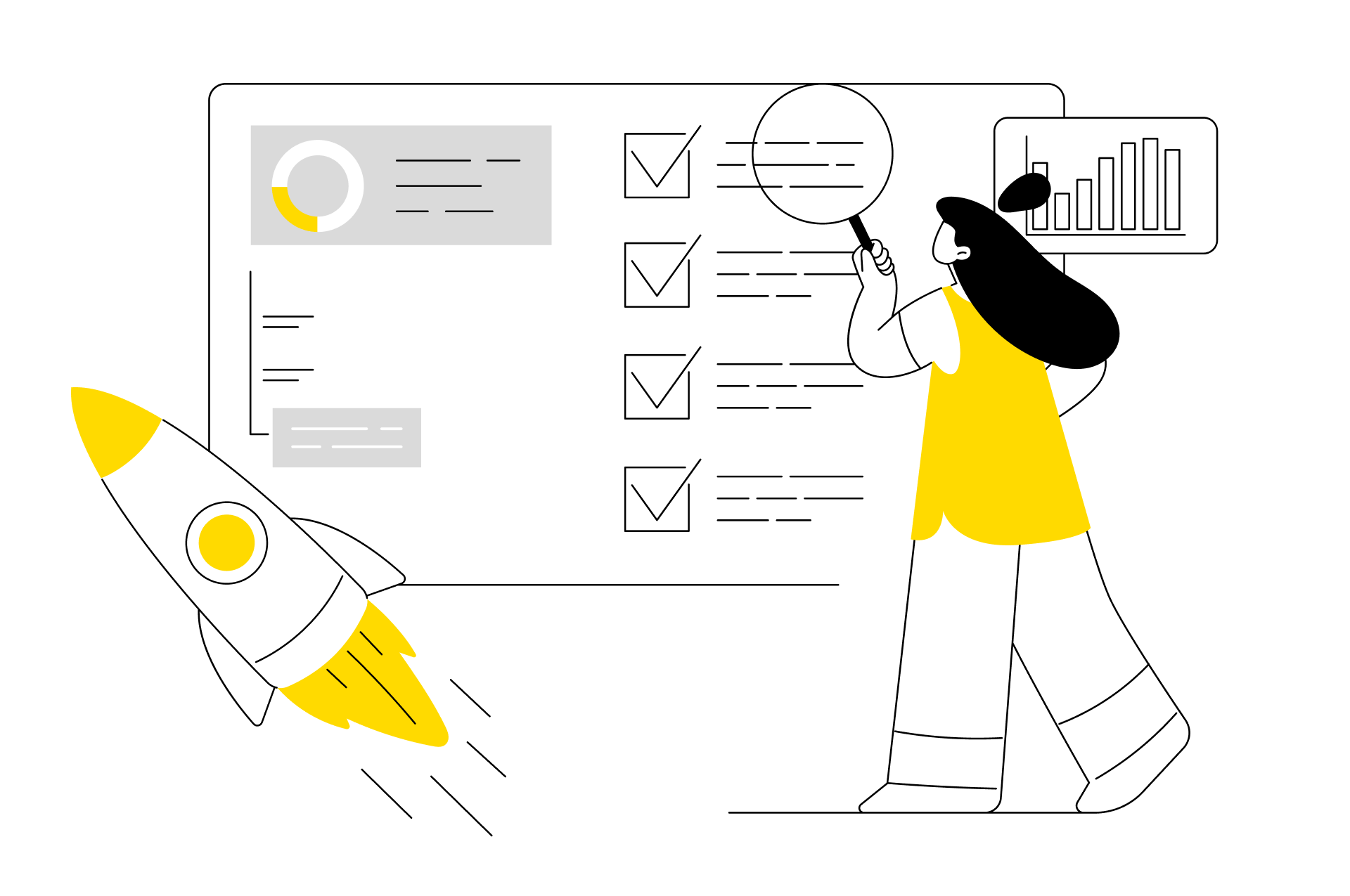
それでは、レガシーシステムの存在は、企業にどのような問題を引き起こすのでしょうか。
以下では大きく4つの観点から解説します。
運用・保守の負担増加に伴うコスト増加
プログラムが複雑化し、またブラックボックス化してしまったレガシーシステムは、運用保守コストが増加してしまいます。
複雑化したシステムは「このプログラムを修正することでどのような影響が起きるか分からない」状態となります。結果として、メンテナンスのたびにコストと時間をかけて大規模な影響調査を行う必要が生じます。
また、古い技術が使われている場合には、その技術に精通したエンジニアの確保も困難です。人材の確保難もまた、レガシーシステムのメンテナンスコストを上昇させる要因の一つとなります。
システムのパフォーマンスの低下
ITが進歩し、様々な製品やアーキテクチャが生み出されている一方で、レガシーシステムは古い技術のまま運用されています。
結果として、同じ処理であってもレガシーシステムでは多くのコンピュータリソースを消費したり、高いライセンスコストが必要になってしまったりします。
また、デザイン面やUI面が過去のものとなっているケースもあります。このようなシステムはユーザーの操作性も悪く、業務効率が悪化してしまいます。
属人化した開発・運用
長期間運用されてブラックボックス化してしまったシステムは、特定の担当者しか管理を行えない状況となってしまいます。
結果として、さらに特定の担当者に依存する属人化が進みます。特定の担当者のみがシステムの内部構造や処理方法に関する知識を持っている状況において、その担当者が退職や異動、病気などで不在になると、システムの維持や改修が困難となってしまいます。
法改正やセキュリティチェック対策に弱い
メンテナンスが困難であることから、レガシーシステムは最新の法規制やセキュリティ基準に適合するための更新を実施しにくいといえます。
新たな法規制が実施される場合、施行日までにシステムを改修し、新たな規制に対応しなければなりません。しかしながら、レガシーシステムの改修には期間もコストも必要であり、迅速な対応は困難です。
また、古い技術が利用されていることから、セキュリティの観点にも注意が必要です。サポートが終了した古いソフトウェアを継続利用してしまっているケースもあり、サイバー攻撃を受けるリスクもあります。
加えて、新たに発見された脆弱性に対応するためには迅速な改修が必要ですが、レガシーシステムでは迅速な対応は難しいといえるでしょう。
レガシーシステムの問題はなぜ解決しないのか?
一方で、レガシーシステムの問題を解決することは、必ずしも簡単ではありません。
なぜでしょうか?
刷新のためにコストがかかる
レガシーシステムを刷新するためには投資が必要となります。特に企業の基幹システムがレガシー化してしまっている場合、刷新のためには大規模な投資が必要です。投資コストはレガシーシステム刷新の意思決定を妨げる原因となりがちです。
また、古いアーキテクチャから最新のアーキテクチャへと移行するためには、データの移行やユーザーのトレーニングなど、様々なタスクも必要となり、IT部門・利用部門の人的リソースも必要です。
これらのコストは短期的には企業にとって大きな負担となり、レガシーシステム問題の解消を躊躇させる要因となります。
投資対効果が理解されにくい
さらに、レガシーシステムの刷新に対する投資対効果は理解されにくい点も課題です。
「すでに導入されており、業務でも問題なく利用されているシステムをリプレイスしても、新たな価値は生まれないのではないか」という認識を持たれてしまい、レガシーシステムの刷新にGoが出ないケースもあります。
このように、多額の投資を行ってレガシーシステムの刷新を実施する正当性が理解されにくいという点も問題です。
要件定義が困難
一般的にシステムの移行を行う際には、現行システムを分析して新たなシステムにどのような機能を持たせるか、要件定義を行います。
一方で、レガシーシステムでは設計書などのドキュメント類が整備されていないことも多く、現行システムの分析が困難となりがちです。
結果として、プロジェクトのスタート地点となる要件定義に多くの時間やコストがかかってしまいます。
このようにレガシーシステムの刷新にあたっては様々な課題があります。
しかし、レガシーシステムの問題は放置できません。メンテナンスコストの増加やシステムパフォーマンスの低下、セキュリティリスクの増大など、レガシーシステムは企業の競争力や信頼性に影響を及ぼします。
レガシーシステムの刷新は一時的な負担を伴いますが、将来的な利益とリスク軽減を考慮すれば必須で解決すべき課題であると言えるでしょう。
レガシーシステムから脱却するための解決策
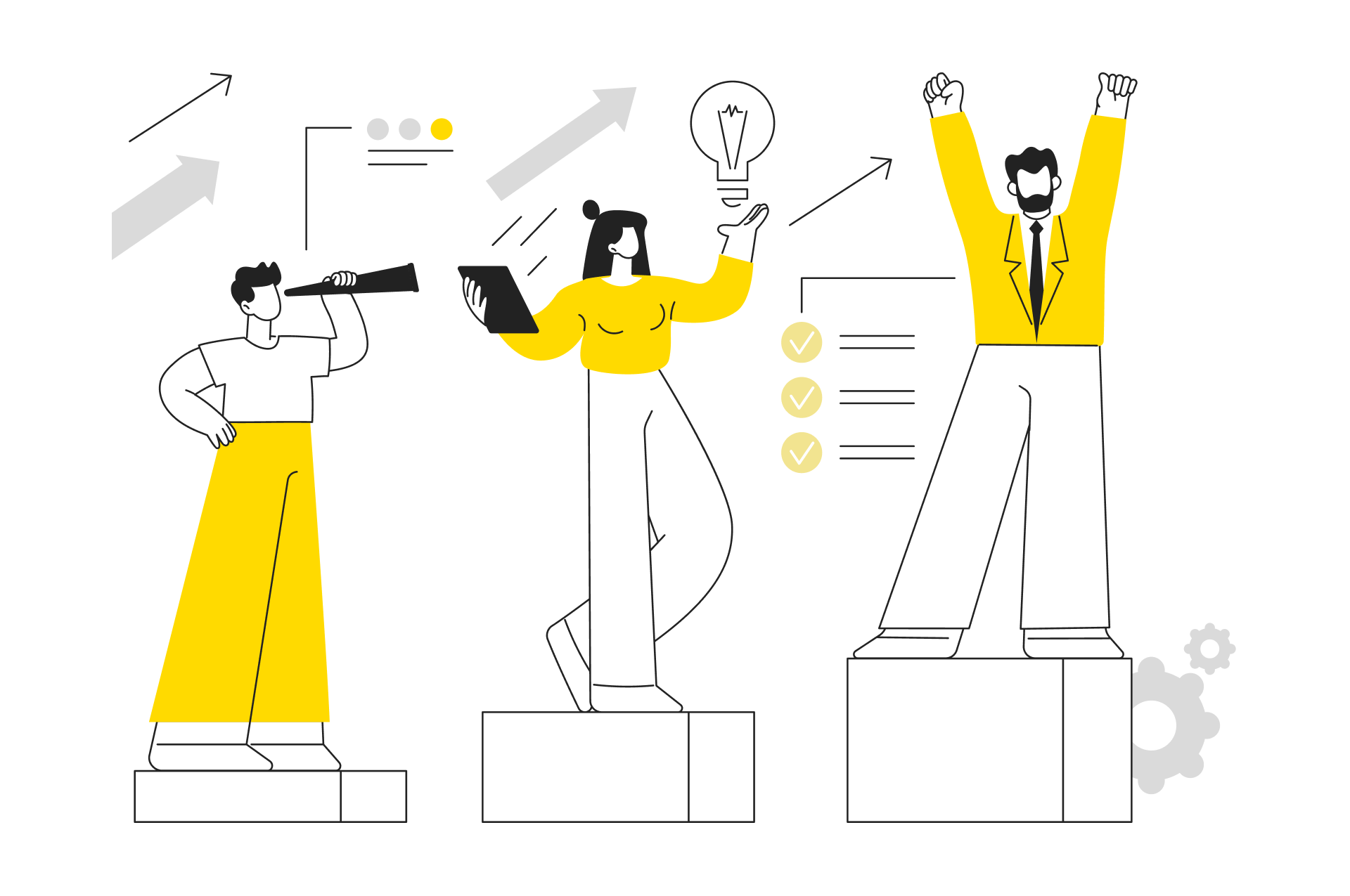
それでは、レガシーシステムから脱却するためにはどうすればよいのでしょうか。
以下では、解決のための具体的なアプローチをご紹介します。
レガシーマイグレーション
レガシーシステムから脱却するための一つのアプローチ例は、レガシーマイグレーションです。レガシーマイグレーションでは、レガシーシステムを新しいプラットフォームやクラウド環境へとそのまま移行します。
システムを刷新する際には、「現行の機能を担保できるのか」「データ移行はうまくいくのか」といった様々なリスクが発生します。レガシーマイグレーションにより現行の仕組みをそのまま新しい環境に移すことで、これらのリスクを抑えられます。
レガシーモダナイゼーション
レガシーモダナイゼーションは、既存のシステムを最新の技術やアーキテクチャに改修する手法です。
システムのアーキテクチャを最新化したり、新しいプログラミング言語やフレームワークを導入したりと、システムの全体的な設計を見直しつつ、新システムへと移行します。
レガシーモダナイゼーションは、さらに様々な手法に分類されます。具体例としては下表のとおりです。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| リビルド | 既存のシステムを完全に再構築し、新しい技術やアーキテクチャを使用して一から作り直す手法。 |
| リプレイス | 既存のシステムを新しい商用ソフトウェアやパッケージソリューションで置き換える手法。 |
| リライト | 既存のシステムを新しいプログラミング言語やフレームワークで作り直す手法。 |
| リファクタリング | 既存のシステムの内部構造を改善し、プログラムの品質やパフォーマンスを向上させる手法。 |
これらのアプローチによりシステムの柔軟性や拡張性を向上させ、メンテナンスコストの削減と迅速なメンテナンスの実現を目指します。
クラウドサービスの活用
近年では、新たにシステムを開発せずともすぐに利用できるクラウドサービスが多く登場しています。これらを利用することもまた、レガシーシステムから脱却するための効果的な手法の一つです。
自社の業務に適合するクラウドサービスがあれば、積極的に導入していくことで、コストを抑えてレガシーシステムからの脱却を実現できます。
要件定義段階からUXデザイナーが参画
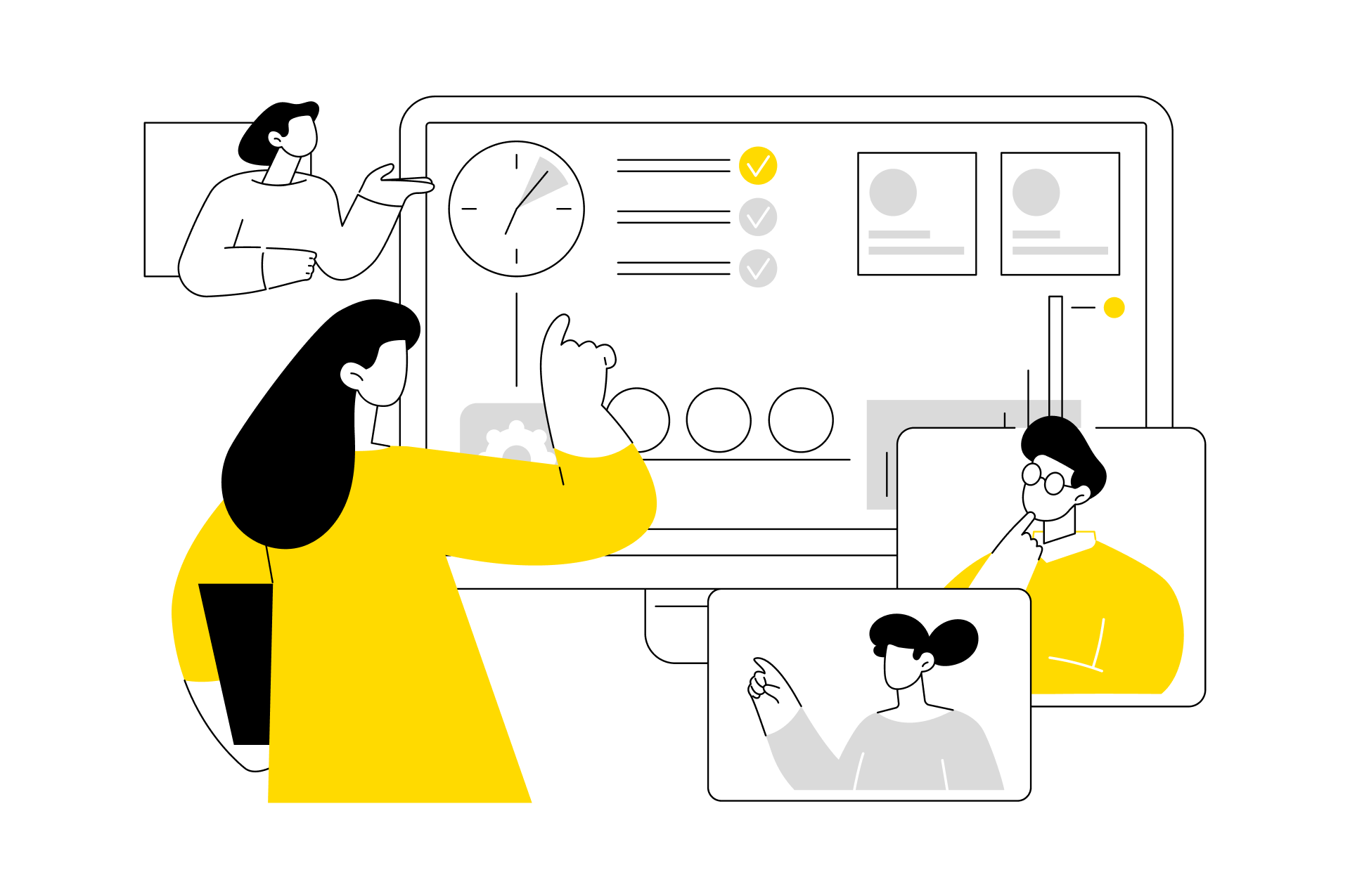
レガシーシステムからの脱却において困難となりがちな要件定義ですが、その解決方法の一つとして、「要件定義段階からUXデザイナーが参画する」というアプローチがあります。
要件定義においては「ユーザーとの目線合わせ」「関係者の巻き込み」「要件の精緻化」といった観点が重要ですが、UXデザイナーによりインセプションデッキやワイヤーフレーム、プロトタイプも作成しながら、ユーザーの要望を可視化することができます。
また、可視化により関係者での議論や意見出しも活発化させることができます。
このように、要件定義段階からUXデザイナーが参画するメリットは大きいといえるでしょう。
なお、当社スパイスファクトリーでは、豊富な実績をもつUXに関するプロフェッショナルが要件定義の段階から参画し、ユーザー視点からのシステム開発を支援しています。アジャイルマインドを意識し、素早くアウトプットし良い失敗を繰り返すことで、要件定義の精度を高めていきます。
また、当社は総合システムインテグレーターである株式会社DTSと資本提携を行い、同社が提供するシステム基盤とユーザー体験を重視した直感的で使いやすいシステムの設計を融合させるDXソリューションの展開も進めております。
PoCの活用
レガシーシステムの刷新にあたり検討したいのが、PoCの活用です。
PoCとは、「Proof of Concept」の略で概念実証のことを指します。ビジネスアイデアや技術の実証の他、レガシーシステムの刷新にあたっても活用できます。
PoCにより、新たなシステムが業務と適合するかを検証しつつ、システム刷新に向けた課題を洗い出すことで、失敗のリスクを抑えられます。
特に基幹系システムの刷新など、リスクの高いプロジェクトにおいてはPoCの実施を検討すべきでしょう。
DX人材の育成・採用
これらの取り組みを進めていく上で必要となるのが、人材育成や採用です。
レガシーシステムの刷新にあたっては、最新のアーキテクチャや技術に精通した人材や、プロジェクトマネジメント能力を持った人材が求められます。これらの役割を担う候補者への研修が有効となります。
また、社内で十分に人材が確保できない場合は、レガシーマイグレーションやレガシーモダナイゼーションに精通した外部人材の活用も検討すべきでしょう。
特にレガシーマイグレーションやモダナイゼーション、DXの推進においては、アジャイルの知識に精通した人材も重要となります。以下の記事では、DXとアジャイルの関係性について解説しておりますので、併せてご覧ください。
レガシーシステムの刷新に成功した事例
最後に、レガシーシステムの刷新に成功した具体的な事例をご紹介します。
佐川ヒューモニー株式会社:「VERY CARD」創業以来のシステム基盤刷新
グリーティングカードや慶弔関連ギフトなどの通信販売事業を営む佐川ヒューモニー株式会社様では「様々なライフステージにおいて人と人を結ぶサービスとして選ばれる企業」を目指し、人生の様々な節目に大切な人に想いを伝える電報類似サービス「VERY CARD」を提供しています。
一方で、VERY CARDを運用するためのシステムは2002年の開発当初から継続利用されており、システムが複雑化してしまったことで商品追加やシステム改修に時間がかかるという課題がありました。
そこで同社では、同システムを最新のクラウド技術基盤を利用したシステムへと移行するべく、刷新プロジェクトを立ち上げました。当社スパイスファクトリーは本プロジェクトを支援させていただき、アジャイル型によるシステム開発やUI/UXの見直しなどを支援させていただきました。
同社では、今後もシステムを基盤に、お客さまにとってより利用していただきやすいサービスの提供を目指して機能の開発・改善を進めていくとのことです。
AGC株式会社:メインフレームからのAWSへの移行
「ガラス」「電子」「化学品」など、幅広く事業を展開するAGC(旧旭硝子)では、これまでメインフレームで運用してきた自社のシステムをAWS基盤へ移行しました。
本取り組みはレガシーマイグレーションにより、既存のシステムに大きな変更を加えず、AWSへ移行する形で進めました。
AWSへの移行により、システムの運用コストは約40%削減。また、5年ごとのハードウェア更改作業も不要となり、システム管理部門の負荷は大きく低減されています。
※参考:独立行政法人情報処理推進機構「レガシーシステムモダン化委員会 第3回 事例紹介3」より
富士通:自社モダナイゼーションにより4000システムを1000システムに圧縮
大手システムインテグレーターである富士通では、「ITガバナンスの不在」「個別最適システムの乱立」といった課題を解決するべく、自社システムのモダナイゼーションを実施しました。
同社では、各部門が構築したシステムなど合計で約4000システムが運用されていました。これらに必要な運用コストやメンテナンスコストを削減しつつ、迅速な改修対応やデータ活用を実現すべく、経営主導でモダナイゼーションを実施。システムの集約や廃止により約1,000システムにまで圧縮しました。
※参考:独立行政法人情報処理推進機構「レガシーシステムモダン化委員会 第3回 事例紹介2」より
まとめ
今回は、レガシーシステムの課題やその解決策、実際の解決事例などについて詳しくご紹介しました。
特に歴史の長い企業であればあるほど、レガシーシステムは自社の負債として経営に大きな影響を与えます。機動的な改修が難しく、また維持コストも高止まりしてしまうレガシーシステムからの脱却が必要です。
当社、スパイスファクトリーでは、レガシーシステムからの脱却を目指されるお客さまの支援を実施しています。
システム刷新に向けた要件定義やUX再設計など、上流からご支援が可能です。レガシーシステムの刷新に悩まれている企業の方は、ぜひ当社までお声がけください。
当社は【2025年最新版】DX支援おすすめ企業4選に掲載されています。
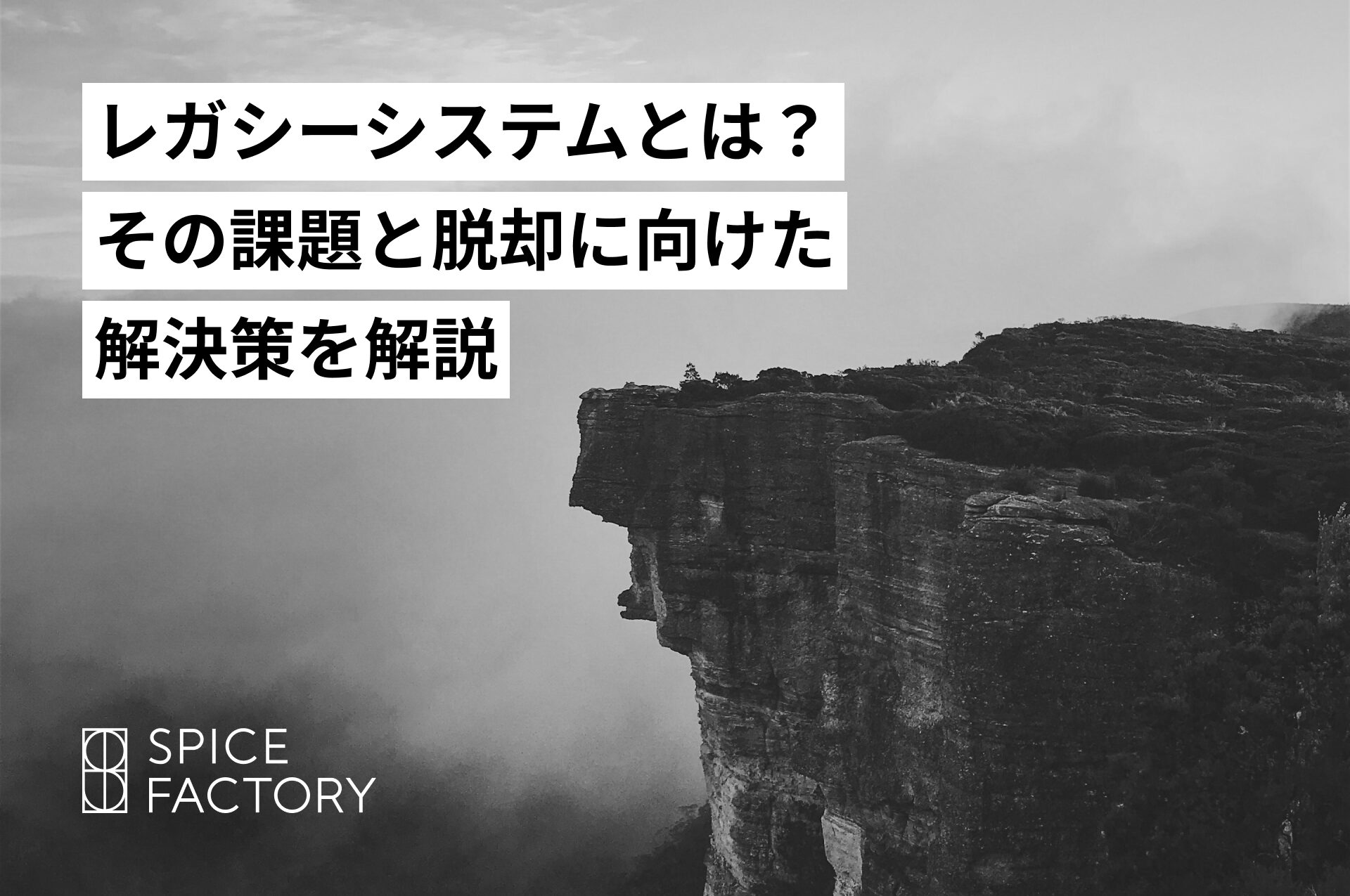
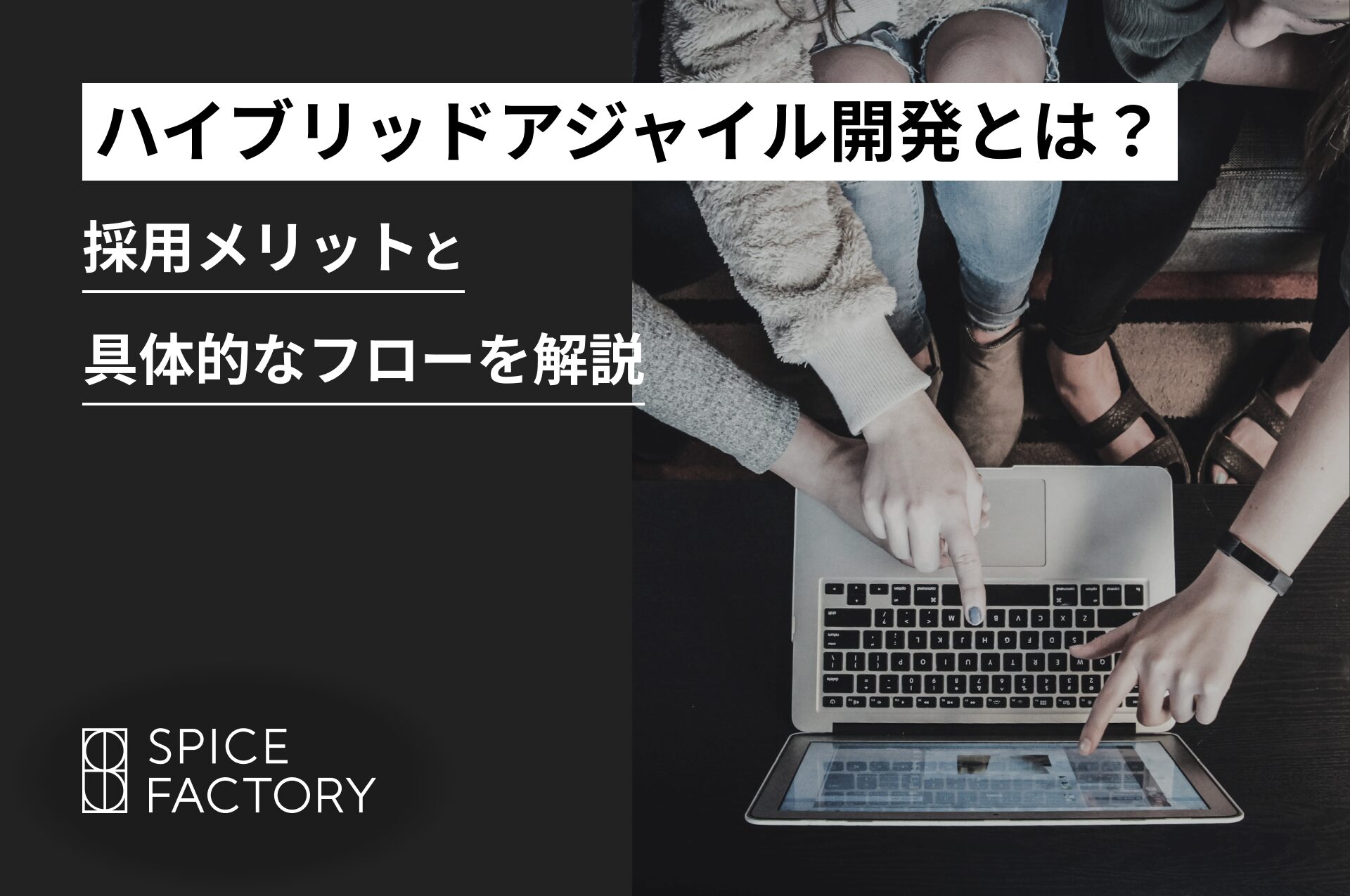
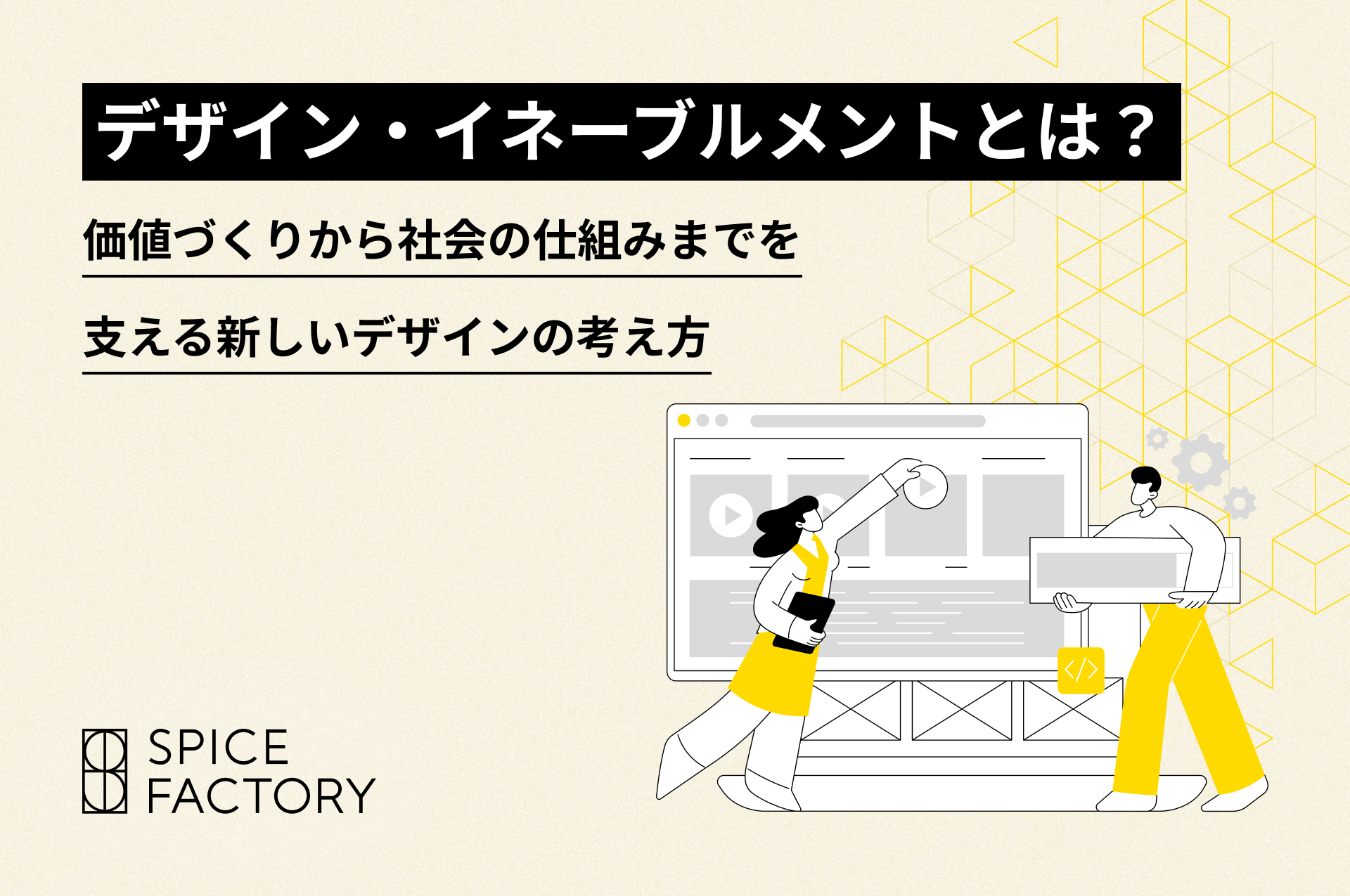

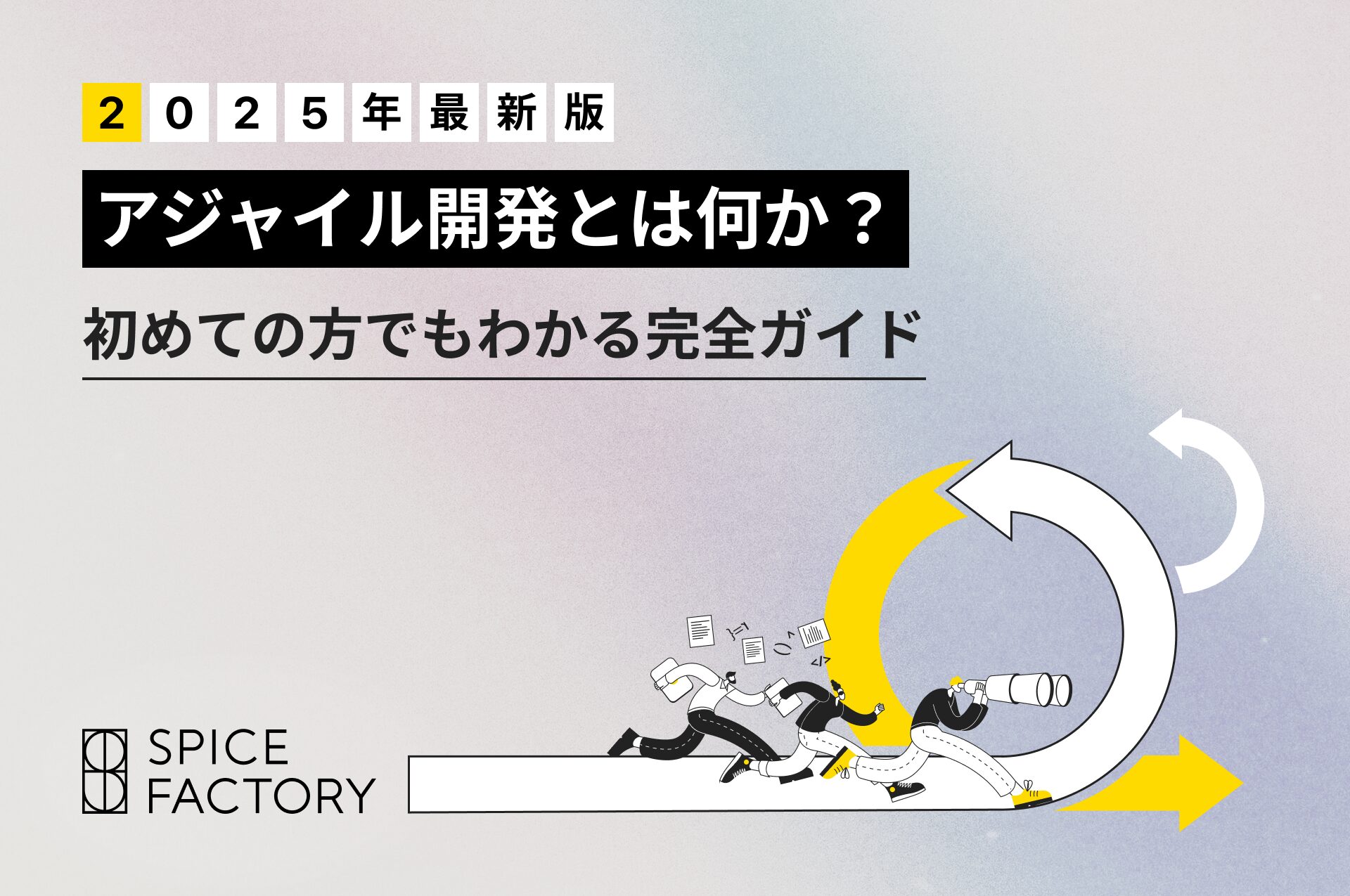


About The Author
スパイスファクトリー公式
スパイスファクトリーは世界がより良い⽅向に向かうよう、変化を加速させる “触媒”(スパイス)としての役割を全うすることをミッションとしたDXエージェンシーです。最新テクノロジー、UIUX、アート、マーケティングなどの技術・メソッドを⽤いて、モノゴトを素早く、美しく、本質的に再定義し、幅広いクライアントのデジタルトランスフォーメーションを⽀援しています。