佐川ヒューモニー株式会社 佐川ヒューモニー「VERY CARD」創業以来の大刷新|長年利用したシステム刷新とアジャイル型のスクラム開発への挑戦
佐川ヒューモニー株式会社が提供する「VERY CARD」は、結婚、出産、入学、卒業など、人生の様々な節目に、大切な人に想いを伝える電報類似サービスです。かつては電話で申し込むのが一般的だった電報サービスですが、近年ではインターネット上で簡単に申し込みができ、豊富な商品から選ぶことができるインターネット電報サービスも活用されています。
スパイスファクトリーはこの度、「VERY CARD」のシステム刷新プロジェクトを支援しました。創業以来運用されてきたオンプレミス環境の既存システムを、AWSへの移行とコンテナ環境の新規構築、そして各環境間の連携システムを整備することで、最新のクラウド技術基盤へと刷新。さらに、ユーザー調査を行いUI/UXを見直し、個人向け電報サービスサイトをリニューアルしました。
今回は、本サービスシステム部の小林様、金子様、菊池様の3名に加え、スパイスファクトリーでプロジェクトマネジメントを担当した角南(すなみ)に、プロジェクトの軌跡を詳しく伺いました。
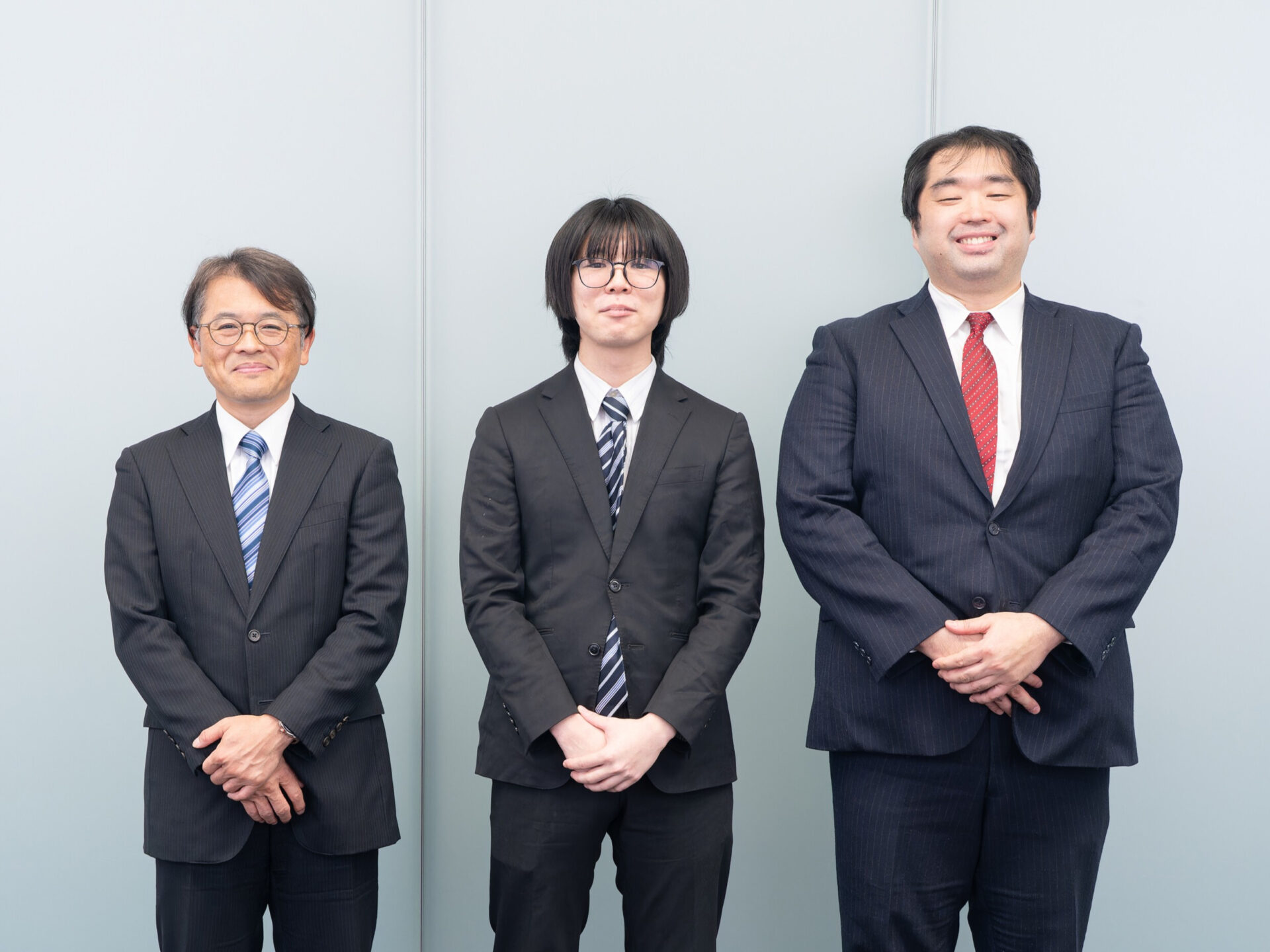
話し手:佐川ヒューモニー株式会社 システム部
(左から)次長・小林 弘明様、菊池 隆様、主任・金子 隆司様
Contents

(左から)[聞き手]スパイスファクトリーCSO・流郷、 [話し手]スパイスファクトリー:角南・スクラムマスターとしての経験も豊富な開発エンジニア。今回のプロジェクトマネジメントを担当。以降、佐川ヒューモニー株式会社:小林様・16年以上にわたりシステム部を支え続けてこられたベテラン社員。今回プロジェクトオーナーを務めた。菊池様・入社1年目。テストの実施やデータ連携などを担当。金子様・開発チームの主任として、既存システムの調査を担当。
創業以来、長年利用したシステムの大刷新
──ベリーカードのシステム刷新に至った背景を教えてください。
小林様:
創業以来、同じシステムをずっと使い続けてきました。度重なる機能追加は、まるでビルに増築を重ねるようなもので、システムは複雑化し、調査や不具合対応に多くのコストがかかるようになっていました。
金子様:
システムを調査してみると、創業以来様々な人が様々な手法で作ってきたため、統一性がなく、非常に読みにくいコードになっていました。いわゆる「スパゲッティコード」*状態でしたね。
*スパゲッティコード:実行順序や構造が複雑に入り組んでいて、整理されていないプログラムのことで、スパゲッティが絡まる様子に例えられたもの
──システム刷新プロジェクトはいつ頃から考えられていたのですか?

小林様:
実は5年ほど前からリニューアルの話は出ていました。しかし、調査範囲や工数を考えるとなかなか実現には至りませんでした。今回やっと動き出すことができ、大変嬉しく思っています。不覚にもプロジェクトのキックオフの時は感極まってしまったのを今でも覚えています。
新システムへの移行とアジャイル型・スクラム開発への挑戦
──今回のシステム刷新では、どのような技術を採用したのですか?
角南:
今回のプロジェクトには大きく2つのフェーズがあります。まず第1フェーズとして、既存システムを新しい基盤に移行しました。 基盤には、最新のクラウド技術を採用しています。 第2フェーズでは、個人向けの電報サービスサイトをリニューアルしました。標準機能の不足などが課題と伺っていましたので、インターネット調査やインタビューを通じてユーザーの声を聴き、より使いやすいUI/UXを目指しました。
システム基盤の移行においては、長年のシステムのコードを解析し、既存の機能を維持しながら新しい機能を追加し、新しいクラウド環境に対応させるという…利用者からは同じサイトに見えるものの、裏側では手間と時間がかかる作業を行っています。
──開発手法としてアジャイル型のスクラム開発を採用したのはなぜですか?
小林様:
当初はウォーターフォール型開発でシステム刷新を進めることを考えていました。しかし、要件定義の段階で、パッケージソフトを利用してのリニューアルから、フルスクラッチでのシステム再構築が必要になったため、ウォーターフォール型開発では本開発のリリースまで期間が長く、その間に要件変更された場合の対応が難しいと判断しました。また、スパイスファクトリーさんの顧客目線に立ったコミュニケーション能力に信頼を置いていました。そのため、ご提案いただいたアジャイル型のスクラム開発に挑戦することで、システム刷新を成功に導くことができると判断しました。
フラットな関係性が築き上げた、スピード感と一体感
──今回アジャイル型のスクラム開発をやってみていかがでしたか?
小林様:
スパイスファクトリーさんは私たちの意見を尊重し対等な立場で議論を重ねて、疑問点を解消してから開発を進めてくれ、手戻りが少なくスムーズにプロジェクトを進めることができたと思います。プロジェクト終盤の結合テストや運用テストの段階では、多くの問題点が見つかり、正直リリースまでに修正が間に合わないのではないかと考えたこともありました。そんな中、スパイスファクトリーさんが1日に何十個も修正を投げ返してくださり、解決を重ね無事リリースを迎えることができ、その技術力と迅速さには圧倒されましたね。
あと、私個人としても、今回のプロジェクトをきっかけに『認定スクラムマスター』の資格取得にチャレンジしています*。角南さんや(以前プロジェクトメンバーだった)角崎さんと一緒に仕事をさせてもらって、とても前向きに取り組まれていたのがとても印象的でした。
*小林様は2024年12月、スクラムマスターに必要なスキルを保持していることを証明する認定資格『スクラムマスター[Scrum Alliance認定Certified ScrumMaster®(CSM®)]』に無事合格されています。

金子様:
私にとって初めての大規模プロジェクト、かつ会社として初めてアジャイル型のスクラム開発を採用しています。最初「なかなかストロングなプロジェクトだな」と思いつつ…(笑)手法についてはウォーターフォール/アジャイル、私は特にこだわりはなかったので抵抗感なく臨みました。結果、今回のプロジェクトにはアジャイル型のスクラム開発が合っていたなと。また、今回スパイスファクトリーのエンジニアさんだけではなく、UIやUXに関わるデザイナーさんなど、適材適所でその専門職の方々と意見交換しながらプロジェクトを回せたことが印象深いです。加えて、SlackやGoogleドキュメントなど、今まで社内では使用していなかった新しいツールや開発環境など、多くの新鮮な知識や経験を得ることができ、プロジェクト自体を楽しむことができました。
今回のリニューアルで、創業以来の蓄積で複雑化してしまっていたコードを1からきれいに作り直すことができ、「美しいコードだな」と感じました。

角南:
今回、毎朝のミーティングやチャットツールなどを活用し、活発なコミュニケーションを取りながら開発を進めることができました。そして小林さんは、プロダクトオーナーとして常に迅速に意思決定をしてくださいました。 また、疑問点があれば、すぐに私たちに確認してくださったので、プロジェクト全体がスムーズに進行できたと感じています。
流郷:
活発なコミュニケーションとフラットな関係性の環境のもと、小林さんの迅速な意思決定、角南さんの的確なサポート、そして開発メンバー同士の活発な意見交換がプロジェクトの成功を導いたということですね、スパイスファクトリーとしても、みなさんの感想とても嬉しいです。
受け継がれる、老舗企業の信頼と挑戦
──菊池さんは入社1年目で今回のプロジェクトに参画されたそうですが、どのような点が印象に残っていますか?

菊池様:
私は入社面接の段階で、あるプロジェクトがアジャイル型のスクラム開発で進められる可能性があること、そして将来的には社内の開発にも取り入れていきたいという話を聞いており、実は入社の動機の一つにもなりました。 特に、大企業では既存のやり方に固執しがちですが、佐川ヒューモニーは新しい開発手法を積極的に導入し、「従来のやり方とは違う、新しいことに挑戦できる」その点に魅力を感じましたね。
実際にこのプロジェクトに参加してみて、経験の少なさによる技術的なスキル不足を感じていましたが、角南さんがいつでも質問しやすい環境を作ってくれたおかげで、安心して仕事に取り組むことができました。
また、大規模サービスをリリースするという作業は人生初めての経験であり、強く印象に残っています。 特に、本番環境でのリリースは緊張感があったものの、テストを重ねてきた成果が形になった瞬間は大きな達成感を感じました。
──最後に、今後の展望について教えてください。
小林様:
新しい「VERY CARD」は、お客様にとってより使いやすく、私たちにとっても運用しやすいシステムになりました。このシステムを基盤に、お客様にとってより利用していただきやすいサービスの提供を目指し、機能の開発・改善を進めていきたいです。
また、今回をきっかけとして法人サイトの刷新など、次なるチャレンジも検討しています。
流郷:
新しい技術や開発手法を積極的に取り入れ、変化を恐れずに挑戦していく佐川ヒューモニーさんの企業文化をみなさんのお話しから感じました。みなさま、貴重なお話しありがとうございました。
 今回のインタビューは、スパイスファクトリーの”いま”をお届けする、みんなで育てて、成長するラジオ「スパイスファクトリーのラジオ(仮)」でも、実際のお話の様子を配信中です。
今回のインタビューは、スパイスファクトリーの”いま”をお届けする、みんなで育てて、成長するラジオ「スパイスファクトリーのラジオ(仮)」でも、実際のお話の様子を配信中です。
プロジェクトを成功に導いたフラットなチームの雰囲気と力強い言葉を、ぜひラジオでもお聞きください。

